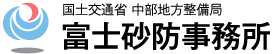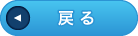富士山と防災
ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>2.富士山の文学 -万葉から昭和まで文学にあらわれた富士山-
富士山と周辺文化
2.富士山の文学 -万葉から昭和まで文学にあらわれた富士山-
| 古典文学 | |
| 奈良時代に作られた20巻・4500余首からなる日本最古の歌集「万葉集」には、富士山を詠んだものが、一説によると11首あるといいます。有名なのは山部赤人の次の一首でしょう。 | 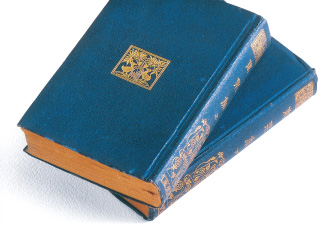 |
| [田子の浦ゆうち出でて見れば真白にぞ 不尽の高嶺に雪は降りける] | |
| (巻三) | |
| これは純粋な叙景歌ですが、噴煙にこと寄せて女性への思いを詠む相聞の歌では次のような例があります。 |
|
| [吾妹子に逢うよしをなみ駿河なる 不尽の高嶺の燃えつつかあらむ] | |
| (巻十一) | |
| [さ寝らくは玉の緒ばかり恋ふらくは 富士の高嶺の鳴る沢のこと] | |
| (巻十四) | |
| 「古今集」905年「新古今集」1205年などの勅撰和歌集にも富士の歌は多くあります。 |
|
| [人知れぬ思いをつねに駿河なる 富士の山こそ我が身なりけれ] |
|
| (古今集 読人しらず) | |
| [ふじの嶺の煙もいとど立ちのぼる 上なきものは思いなりけり] | |
| (新古今集 藤原家隆) | |
| [富士のねをよそにぞ聞きし今は我が 思いにもゆる煙なりけり] | |
| (後撰集 朝頼朝臣) | |
| 叙景も相聞もいろいろとありますが、何かしら類似した歌が多いのがこの時代の特色なのでしょうか。パターン化するのが好きな日本人の一面が見えてくるようです。 さて、詩歌の世界のほかにも平安、鎌倉の文学の中には富士山は数多く登場します。日本最古の作り物語とされている「竹取物語」をはじめ、在原業平が主人公とされる「伊勢物語」、菅原孝標の女作の「更級日記」、そして富士川の合戦が描かれる「平家物語」など富士山はあらゆるジャンルに顔を出しています。 |
|
●江戸俳譜にみる富士山 |
|
| 富士山麓には古来から古文墨客が多く訪れていますが、松尾芭蕉もそんな中の一人です。河口湖畔産屋々崎には「雲霧暫時百景をつくしけり」の句碑が建っています。これは「野ざらし紀行」も終わりの頃、この地を訪れた際、産屋々崎からの富士のみごとさを詠んだものとされています。 富士にちなんだ芭蕉の句としては、やはり「野ざらし紀行」の中の「霧しぐれ富士を見ぬ日ぞおもしろき」が有名です。箱根の関所越えの時の句ですが、見えない富士を詠んで、その逆説的効果がおもしろい。芭蕉及び江戸時代の俳人の句をもう少し紹介してみましょう。 |
|
|
[ひと尾根はしぐるる雲か不二の雪](芭蕉) [目にかかる時やことさら五月富士](芭蕉) [はれて候又曇り候ふじ日記](其角) [不二ひとつうずみ残して若葉かな](蕪村) [かたつぶりそろそろ登れ富士の山](一茶) |
|
| 近代文学 | |
●明治から大正の文学にみる富士 |
|
| 近代山岳文学の先駆者小島鳥水の「不二山」、日本全国に足跡を残す紀文文学者大町桂月の「富士の大観」などが、富士山をテーマにした文学のさきがけとなりました。 他には早稲田文学でデビューした中村星湖の「少年行」、北村透谷の持論「富嶽の詩神を思ふ」などがあり、俳句・短歌の分野では正岡子規、島木赤彦、飯田蛇骨などが特筆されます。 |