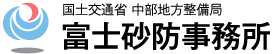富士山と防災
ホーム>富士山と防災>富士山について>富士山知識>7.富士山頂富士「八葉」の歴史
注)剣ヶ峰以外の標高は、2009年10月 航空レーザ計測データ等からの推定値
富士山の基礎知識
7.富士山頂富士「八葉」の歴史
| 富士山頂部には「八葉」と呼ばれる8つの峰があります。古来、仏教でいう八葉蓮華(はちようれんげ:仏が坐(すわ)る八枚の弁をもつ蓮華座)にたとえられていたことに由来するもので、この八葉はこれまで様々な呼び名で呼ばれており、資料ごとでその名称が異なっています。明治時代の神仏分離令の影響を受け、富士山においても廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)運動が起こり、富士山中の仏教系地名が神道系の名称に変えられました。 現在「お鉢巡り」と呼んでいる火口の周りを一周することも、この八葉の峰をめぐる「お八めぐり」が転化したものと考えられます。 |
|
| この「八葉」の名称の歴史的名称の変化と、現在の「八葉」の名称及びその背景を紹介します。 | |
| ●「八葉」の名称の由来 | |
|
富士山の八葉についてはいくつかの由来があります。 |
|
| ●歴史的資料に見られる八葉の名称 | |
|
歴史的な古文献(古図)等に見られる富士山頂の「八葉」は表-1の名称で呼ばれていた。 |
|
| ●現在の八葉の峰の名称由来と関係のある神仏 | |
明治時代の廃仏毀釈前の神仏と関係の深い名称(表-1の名称)と現在の名称を繋ぐ山頂名と神仏との関係を表-2に示す。 |
|
 |
| 表-1 資料に見られる富士山頂の名称 |
| 芙蓉亭 富士日記 |
村山浅間 修験大鏡 坊興法寺 歴代写 |
大鏡坊 富士山略 縁起 |
中谷顧山 富嶽の記 |
北口登山 富士山参詣 名所図会 |
駿河 新風土記 須山村 浅間社 |
大日本 名辞書 |
|
| 地蔵獄 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 阿弥陀獄 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| 観音獄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 釈迦獄 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 弥勒獄 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 薬師獄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 文殊獄 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 加来獄 | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 大日岳 | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 宝生獄 | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 勢至ヶ獄 | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 浅間ヶ獄 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 剣ヶ峰 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 普賢獄 | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 雷之獄 | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 経ヶ獄 | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 駒ヶ獄 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 馬背ヶ獄 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 鋸ヶ獄 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 中将獄 | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 作成年代 | 文政6年 1823年 |
不明 | 不明 | 江戸時代 中期 |
不明 | 江戸時代 文化13年 ~天保6年 |
明治33年 |
表-2 現在の「八葉」の地名由来と関係神仏 |
| 現在名称 | 標高(m) | 地名由来等 | 関係のある神仏 |
| 剣ヶ峰 | 3,776 | 剣ヶ峰という呼び名は土俵の最も外側をいい、 大山の外輪山の最高位を示す。 |
阿弥陀如来 熊野三大権現 |
| 白山岳 (釈迦ヶ岳) |
3,756 | 釈迦の垂迹が白山妙理大権現であつたため | 釈迦牟尼如来 白山妙理大権現 |
| 久須志岳 (薬師ヶ岳) |
3,725 | 久須志神社(薬師如来を祀る)があるため | 薬師如来 鹿島金山大権現 |
| 大日岳 (朝日岳) |
3,735 | 大日如来観音菩薩の垂迹は、浅間大菩薩でもある。 ただし、既存資料では朝日ヶ岳とされているものも ある。 |
大日如来 中央の本尊には胎蔵界 |
| 伊豆岳 (観音岳・阿弥陀岳) |
3,749 | 観音菩薩の垂迹が伊豆大権現であったため。 明治8年に改称 |
観世音大菩薩 伊豆大権現 |
| 成就岳 (勢至ヶ岳・経ヶ岳) |
3,733 | 明治8年に改称 | 不空成就岳 |
| 駒ケ岳 (浅間ヶ岳) |
3,722 | 聖徳太子が駒(甲斐の黒駒)に乗ってやってきた地で あることに因むといわれ、黒岩で出来ている。 |
文殊大菩薩 箱根大権現 |
| 三島岳 (文殊ヶ岳) |
3,734 | 明治8年に改称されている。昭和年間に経筒が 発見されている。三島岳とは神仏混沌時代に文殊 ヶ岳の垂迹に三島大明神があったためか。 |
宝生如来 三島大明神 |
 |
 |
 |
| 釈迦の割石と白山 | 三島岳 | 成就岳 |
 |
 |
 |
| 雷 岩 | 虎 岩 | 大日岳・伊豆岳 |
 |
 |
 |
| 剣ケ峰 | 駒ケ岳 | 久須志岳 |
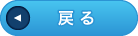 |
||