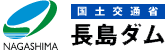ダム周辺で見られる動物の記録 昆虫
このページでは、長島ダム周辺で見ることのできる昆虫(ミヤマクワガタなど)を一部紹介しています。観察される際は近づいたりさわる等を控えて頂きますようお願い致します。なお、ゴミ等は周辺の自然及び動物達に悪影響を与える可能性がありますので必ず各自で持ち帰って頂きますようご理解とご協力をお願い致します。
※写真データご提供いただきました方にはこのページを持ちましてお礼申し上げます。
※各動植物の大きさなどについてはあくまで参考値です。観察される際の目安として記載しています。また写真データは掲載上の都合により加工修正しています。

カラスアゲハ
黒く大きな羽が特徴の蝶。フワリフワリと優雅に飛ぶ姿が綺麗です。
チョウ目アゲハチョウ科アゲハチョウ属
Papilio bianor

ミヤマクワガタ
ニホンに生息するクワガタの中では大型の部類に入るクワガタで、まるで戦国武将の兜ようなカクカクした頭が特徴。
甲虫目クワガタムシ科ミヤマクワガタ属
Lucanus maculifemoratus
体長:32mm~72mm

ナナフシモドキ
エダナナフシに似ていますが、エダナナフシより触角が短いのが特徴。必死で逃げようとするものの動きが遅いのですぐに捕まるのが、少しかわいそうです。
ナナフシ目ナナフシ科
Baculum irregulariterdentatum

ヒメアカタテハ
落ち着いた色が特徴的な蝶。ちょっと地味な感じもしますが、飛んでいる姿がとてもかわいらしい蝶です。
チョウ目タテハチョウ科アカタテハ属
Vanessa cardui
前翅長:3cm前後

オオシオカラトンボ
水辺の岩などによく留まっています。シオカラトンボに比べ青っぽく太いのが特徴です。
トンボ目トンボ科シオカラトンボ属
Orthetrum albistylum speciosum
体長:50mm~60mm

エダナナフシ
動きが遅く木に紛れるとさっぱり分からなくなるのが特徴です。
ナナフシ目ナナフシ科
Phraortes illepidus
体長:100mm前後

アサギマダラ
長島ダム周辺ではよく見かけることのできる蝶。少し青みがかっていたり茶色が入っていたりと似た模様のものを見つけることが難しいです。
チョウ目タテハチョウ科マダラチョウ亜科アサギマダラ属
Parantica sita
前翅長:50mm~60mm

アカアシクワガタ
足の付け根が赤いコクワガタより少し大きいクワガタ。付け根の赤い足が採取した特に少し嬉しい気持ちにさせてくれますよね。メスもすぐに見分けがつきました。
甲虫目クワガタムシ科オオクワガタ属アカアシクワガタ亜属
Dorcus rubrofemortus
全長:24mm~55mm

シロスジカミキリ
日本最大のカミキリムシ。生きているものは黄色いスジがあるのが特徴。アゴの力が強く胴横が棘のような形をしているので持つときは上羽のところを持つようにしましょう。
※噛まれると凄く痛いです。
甲虫目カミキリムシ科シロスジカミキリ属
Batocera lineolata
全長:45mm~60mm

ゴマダラカミキリ
街中でもよく見かけるカミキリムシです。シロスジカミキリよりチョット可愛らしい顔かな?
※カミキリムシはアゴの力がとても強いので噛まれない様に気を付けましょう。
甲虫目カミキリムシ科フトカミキリ亜科ゴマダラカミキリ属
Anoplophora malasiaca

ウマオイ(ハヤシノウマオイ)
夜行性で肉食、キリギリスの仲間。尻尾のような長い産卵管があるので写真は雌かな?名前の由来は「スイーチョン」と馬子が馬を追い立てる声に似てるから『ウマオイ』。
バッタ目キリギリス科ウマオイ属
Hexacentrus japonicus

オオカマキリ
木や草茂みからの鋭い目と大きな鎌の様な前足で獲物を狙う孤高のハンター。チョウセンカマキリに似ていますが、背中の色が茶色一色なのが特徴です。その顔からは冷徹なイメージが強いのですが、オスは子供のためにメスに命を捧げる一面を持っています。
カマキリ目カマキリ科
Tenodera aridifolia

キイロスズメバチ
日本にいる一般的なスズメバチの中でも小さな部類に入るスズメバチ。攻撃的なスズメバチなのであまり刺激しないようにしましょう。もしも刺されたらすぐに病院に行くことは当然ですが毒を抜くためにその場にとどまる事は、他のキイロスズメバチが攻撃してくる可能性があるためオススメできません。
ハチ目スズメバチ科スズメバチ属
Vespa simillima
体長:15mm~30mm

ショウリョウバッタ
日本にいるバッタの中では大型のバッタ。写真のバッタは普通は全身緑色ですが、周辺の環境に合わせ茶色の筋が入っています。
バッタ目バッタ科ショウリョウバッタ属
Acrida cinerea
体長:50mm~80mm

コカマキリ
接岨峡温泉周辺で見つけたコカマキリ。小さくすばしっこいのでオオカマキリより捕まえにくいかも・・・。写真のコカマキリはお腹が小さいのでメスかな?
正解はオスです。カマキリはメスの方が大きくお腹が太いです。
カマキリ目カマキリ科
Statilia maculata
体長(オス):35mm~55mm
体長(メス):45mm~65mm

ヒメスズメバチ
ヒメと言う割に大型な体のスズメバチ。スズメバチの中では大人しい方ですが、むやみに近づくのはやはり危険なので止めましょう。
スズメバチは秋に攻撃的になりやすいので秋は特に注意して下さい。
ハチ目スズメバチ科スズメバチ属
Vespa ducalis
体長:25mm~40mm

クルマバッタ
トノサマバッタに似ているが飛ぶと半月状の模様がよく目立つ。音を立てながら飛ぶので音がしたらクルマバッタが見られるかも・・・。
バッタ目バッタ科トノサマバッタ亜科
Gastrimargus marmoratus
体長:40mm~60mm

ニホンミツバチ
長島ダムの周辺では養蜂が行われています。その方法は、巣箱を設置しておくと野生のミツバチが勝手に居座り巣を作る方法です。しかし、侮るなかれ!巣箱の周りにはブンブンとミツバチが飛び回ります。
この巣から採れる蜂蜜はまさに天然そのもの!とても濃くて美味しいです。
ハチ目ミツバチ科ミツバチ属
Apis cerana japonica
体長:15mm前後


ツマグロヒョウモン
ヒョウ柄模様が綺麗なタテハチョウ仲間。小さい写真がオスです。翅をひろげるとオスよりメスの方が色が多くて綺麗ですね。
チョウ目タテハチョウ科ヒョウモンチョウ属
Argyreus hyperbius
前翅長:35mm~45mm

カメノコテントウ
職員の足にくっついたのはカメノコテントウ。日本で一番大きい種類のテントウムシで寒くなると大量に岩陰などに集まっているのを見かけます。
長島ダム周辺にはクルミの木がいくつかあるのでクルミハムシを食べるカメノコテントウは案外簡単に見つかります。
甲虫目テントウムシ科
Aiolocaria hexaspilota
体長:10mm~15mm

オオセンチコガネ
見た目が色鮮やかなため昆虫採集の対象になりやすいコガネムシ。糞虫と呼ばれる動物の糞や腐肉を食べる森の掃除屋さん。
甲虫目センチコガネ科
Geotrupes auratus
体長:15mm~20mm

クロヤマアリ
一番見かけることの多いアリです。働き者で常にエサを求めて移動している姿が印象的です。テントウムシからアブラムシを守ることでもよく知られていますが、アブラムシは害虫としても有名な虫なので農業に携わる方には腹立たしい光景なのかもしれませんね。
ハチ目アリ科ヤマアリ亜科
Formica japonica
体長(働きアリ):5mm前後
体長(オス、女王):10mm前後

スミナガシ
森の中でよく見かけるタテハチョウの仲間です。写真のスミナガシはサルの糞に留まっています。
樹液や果実などに留まることの多い蝶です。
チョウ目タテハチョウ科スミナガシ属
Dichorragia nesimachus
前翅長:30mm~45mm

コノシメトンボ
翅の先が黒っぽいのが特徴の赤とんぼ。カメラで捉えるのが比較的、簡単なトンボです。
トンボ目トンボ科アカトンボ亜科アカネ属
Sympetrum baccha matutinum
体長:35mm~45mm

キアゲハ
アゲハより黄色で鮮やかな蝶。ヒラヒラと舞う姿はとても華麗です。幼虫と成虫でみなさんのイメージも大きく違うのでは?
チョウ目アゲハチョウ科アゲハチョウ属
Papilio machaon
前翅長:40mm~60mm

オオモンクロベッコウ
森の中でよく見かけるタテハチョウの仲間です。写真のスミナガシはサルの糞に留まっています。
樹液や果実などに留まることの多い蝶です。
ハチ目ベッコウバチ科
Anoplius samariensis
体長:10mm~25mm

クロアゲハ
同じ黒いアゲハのカラスアゲハと比べるとかなり地味な・・・落ち着きのある色の蝶です。
幼虫に間違って触ると大変です。そうすごく臭いんです。
チョウ目アゲハチョウ科アゲハチョウ属
Papilio protenor
前翅長:45mm~70mm

ニホンカワトンボ
ロボットのような角張った形とキラキラ光るメタリックな体が格好いいトンボです。
トンボ目カワトンボ科
Mnais costalis
体長:50mm~60mm

モンシロチョウ
フレームの外に出てしまいましたがモンシロチョウです。ヒラヒラ飛ぶ姿が可愛らしい蝶ですね。
チョウ目シロチョウ科モンシロチョウ属
Pieris rapae
前翅長:30mm前後

ヨトウガ(幼虫)
ヨトウムシと言えば腹の立つ農家の方も見えるかと思います。害虫として有名な虫で、次々と野菜や植物を食べてしまう夜行性の困ったヤツです。
チョウ目ヤガ科ヨトウガ属
Mamestra brassicae
前翅長:45mm前後

ミヤマアカネ
翅の模様が特徴的なトンボ。写真は長島公園のせせらぎ水路で撮ったものです。せせらぎ水路には様々な動物たちが集まってきます。
トンボ目トンボ科アカネ属
Sympetrum pedemontanum elatum
体長:30mm~40mm

ヤケヤスデ
ムカデと違い胴節から2対足があるので単純に倍ですね。そのせいで逃げ足が遅いんだそうです。
オビヤスデ目ヤケヤスデ科
Oxidus gracilis
体長:20mm前後

アカスジキンカメムシ(幼虫)
成虫になると緑の光沢のある体に赤いスジが入るので非常に綺麗なカメムシですが幼虫の時は黒い体に赤い線と違う種類かと思ってしまいます。
カメムシ目キンカメムシ科
Poecilocoris lewisi

キクビアオハムシ
全長1cmにも満たない小さな体。実は翅が退化していて飛べないそうです。手で触るとカサカサと走って逃げてしまいました。
甲虫目ハムシ科ヒゲナガハムシ亜科
Agelasa nigriceps

ウスバシロチョウ
よく見ると翅が透き通っているんです。写真では残念ながら分かりませんが・・・。
チョウ目アゲハチョウ科ウスバアゲハ亜科ウスバシロチョウ属
Parnassius glacialis
前翅長:25mm~35mm

ミヤマフキバッタ
フキバッタの仲間であることは間違いないと思いますがミヤマフキバッタかと問われると回答に困ってしまいますが、ミヤマフキバッタとして紹介させて頂きます。
フキバッタの仲間は専門家でないと見分けがつかないそうです。現に職員も時間をかけて調べましたがサッパリ断定できませんでした。
イナゴみたいなので佃煮にすると美味しいかもしれませんね。
バッタ目バッタ科フキバッタ亜科
Parapodisma

コアオハナムグリ
小さな体で花にちょこんと乗っかっていることが多いです。横から見ると実は毛深いものも・・・。
甲虫目コガネムシ科ハナムグリ亜科
Oxycetonia jucunda
体長:10mm~15mm

マメコガネ
幼虫は根を食べ、成虫は葉っぱを食べる害虫の代表格とも言える昆虫。写真の葉っぱもボロボロ・・・。
写真はオスとメスですね。
甲虫目コガネムシ科マメコガネ属
Popillia japonica
体長:8mm~15mm

ネキトンボ
翅の付け根が黄色(オレンジ色)でネキトンボ。ショウジョウトンボとは成熟しても違い足が黒いままなので見るとよくわかります。
トンボ目トンボ科アカネ属
Sympetrum speciosum speciosum
体長:40mm~45mm

ハイイロゲンゴロウ
比較的簡単に飼うことのできるゲンゴロウです。夏の暑い中 せせらぎ水路を一際元気に泳ぎ回っています。水をかぶると灰色に見えるのでよくわかりますよ。
甲虫目ゲンゴロウ科ハイイロゲンゴロウ属
Eretes sticticus
体長:10mm~16mm

マツモムシ
昆虫界で背泳ぎのプロといえばマツモムシ。軽快に泳いでいたかと思うとひっくり返って空中に飛んでゆきます。刺されるとすごく痛いので素手ではさわらないように!
カメムシ目マツモムシ科マツモムシ属
Notonecta triguttata
体長:11mm~14mm

ニンギョウトビゲラ(巣)
成虫は案外簡単に見つけられますが種類を判別することが難しいです。幼虫の巣は水の中なので根気よく探す必要があります。

クロメンガタスズメ
大きいのですぐにわかります。蛾の苦手な人にはたまらない大きさですね。木の幹などに留まるとわからなくなってしまいます。
チョウ目スズメガ科メンガタスズメ亜科
Acherontia lachesis
前翅長:100mm~125mm

ウシアブ
動物の血を吸う大きなアブ。長島ダム周辺には野生のシカやサルなどがいるため夏場によく見かけます。
人の血も吸うので左の写真のように手で触らないようにしましょう。
ハエ目アブ科アブ亜科
Tabanus trigonus
体長:17mm~27mm

ウスヅマクチバ
ネムノキが大好きな蛾の仲間。暗いところでよく見かけるので黒っぽく見えますが、実は光沢のある綺麗な翅をしています。
チョウ目ヤガ科シタバ亜科
Dinumma deponens
前翅長:35mm~45mm

オスグロトモエ
目玉模様が特徴の大きな蛾です。翅の裏は赤く全く違う模様をしています。
チョウ目ヤガ科シタバ亜科
Spirama retorta
前翅長:55mm~70mm

コマツモムシ
マツモムシよりスマートで小柄です。こちらも背泳ぎで泳ぎますがマツモムシよりも深いところを泳ぐようです。
カメムシ目マツモムシ科コマツモムシ亜科
Anisops ogasawarensis
体長:6mm~7mm

マダラカマドウマ
うす暗い場所でカサカサ動くバッタの仲間。雑食性でダム堤体内を掃除してくれる掃除屋さんです。
バッタ目カマドウマ科カマドウマ亜科
Diestrammena japonica
体長:20mm~25mm

アカマダラカゲロウ
小さなカゲロウの仲間。長島水路で溺れていたのを救出してみました。
カゲロウ目マダラカゲロウ科
Uracanthella rufa
体長:5mm~7mm

オオトビサシガメ
冬の日向で日光浴をしていたカメムシの仲間。派手な色が多いカメムシの中でも地味なヤツです。
カメムシ目サシガメ科アカヘリサシガメ亜科
Isyndus obscurus
体長:20mm~25mm

ナミテントウ
皆さんが一番、目にする機会の多いテントウムシではないでしょうか?模様にあまり統一感がないので模様の違いを見つけるのもおもしろいかも・・・。
甲虫目ヒラタムシ上科テントウムシ科テントウムシ属
Harmonia axyridis
体長:7mm~8mm

ヨモギハムシ
左がメスで右がオスです。ハムシの仲間はメスのお腹がとんでもなく膨らむのが特徴です。
甲虫目ハムシ科ハムシ亜科
Chrysolina aurichalcea
体長:7mm~10mm


ツマグロオオヨコバイ
ヨコバイの仲間では大きい部類になるのでオオヨコバイです。右の写真は翅が欠けています。鳥にでも狙われたのかな?
カメムシ目ヨコバイ科オオヨコバイ亜科
Bothrogonia ferruginea
体長:13mm前後

センチニクバエ
サルやシカなどの野生動物の多い川根本町ではよく見かけるハエです。センチとつくとおり動物の糞などをエサとしています。
ハエ目ニクバエ科ニクバエ亜科
Sarcophaga peregrina
体長:8mm~14mm


ヒオドシチョウ
もう飛べないんじゃないかと思えるほど翅がボロボロになっていますがヒオドシチョウは力強く飛んでいきます。ヒラヒラとした中に感じる力強さは勇気を与えてくれる気がしますね。
チョウ目タテハチョウ科タテハチョウ属
Nymphalis xanthomelas
前翅長:32mm~42mm

ミヤマカワトンボ
雨が降ると暴れ川になる大井川も長島ダムより上流になると普段は水の綺麗な渓流です。こんな渓流でよく見られるのがミヤマカワトンボです。
カワトンボ科カワトンボ亜科アオハダトンボ属
Calopteryx cornelia
体長:50mm~75mm

ムラサキシジミ
小さなシジミチョウの中でも広げた翅がとても綺麗な紫色をしているチョウです。閉じた状態では逆にとても地味なのでわかりやすいです。
チョウ目シジミチョウ科ミドリシジミ亜科ムラサキシジミ属
Narathura japonica
前翅長:15mm~20mm

コクワガタ
オオクワガタの仲間になる小さなクワガタ。クワガタを採ろうと意気込んでも採れるのはコクワガタばかりなんて事もよくあるんじゃないでしょうか。
甲虫目クワガタ科オオクワガタ亜科コクワガタ属
Dorcus rectus rectus
全長:20mm~50mm

フクラスズメ
クロメンガタスズメと比べると地味な色をした大きな蛾です。ダムの堤体内で越冬していたものを撮影しました。
チョウ目ヤガ科シタバガ亜科
Arcte coerula
前翅長:30mm~40mm

オオクロバエ
大きな黒いハエです。大きいだけあってすばしっこくというよりはどっしりと動きます。ハエの仲間はとても早い動きをする動物なので翅の動きは全くついていけませんね。
ハエ目クロバエ科クロバエ亜科
Calliphora lata
体長:9mm~14mm

ホソヒラタアブ
ハナアブの仲間で花によく止まっているのを見かけます。さぁ写真をと思ったら喧嘩を始めてしまったので別の一匹を撮りました。
ハエ目ハナアブ科ヒラタアブ亜科
Episyrphus balteatus
全長:8mm~11mm

アカバマルクビハネカクシ
クネクネと腰を動かすハネカクシの仲間。アズマヒキガエルの足に乗っかり逃げられないのか必死に動いていました。
甲虫目ハネカクシ科シリホソハネカクシ亜科
Tachinus gelidus
全長:6mm前後

イタドリハムシ
黒い体にオレンジ模様がとても綺麗なハムシ。名前のとおり生のまま囓ると酸っぱいイタドリを食べるのでイタドリハムシです。
甲虫目ハムシ科ヒゲナガハムシ亜科
Gallerucida nigromaculata
全長:7.5mm~9.5mm

オオクロセダカカスミカメ
小さな体でも立派なカメムシです。かなり小さいので見失わないようによ~く探してみてね。
カメムシ目カメムシ亜科カスミカメムシ科
Proboscidocoris varicornis
全長:4.5mm~5.5mm

コミズムシ
素早い動きで泳ぐ小さな虫。マツモムシとは違い背泳ぎはしません。せせらぎ水路にはたくさんのコミズムシが泳いでいます。
カメムシ目カメムシ亜科カスミカメムシ科
Sigara septemlineata
全長:5.5mm~6.5mm

ナナホシテントウ
日本にいるテントウムシの中では一番有名なのではないでしょうか。農作物を食い荒らすアブラムシを食べる益虫です。
甲虫目ヒラタムシ上科テントウムシ科テントウムシ属
Coccinella septempunctata
全長:8mm前後

ルリシジミ
名前にルリが付くとおり翅を開くと綺麗な青色が特徴の小さなチョウ。シジミチョウの仲間はみんな小さく可愛らしいですね。
チョウ目シジミチョウ科ルリシジミ属
Celastrina argiolus
前翅長:12mm~19mm

ベニシジミ
翅を閉じてもオレンジ色が分かるシジミチョウの仲間。日当たりの良い場所でよく見かけます。
チョウ目シジミチョウ科ベニシジミ属
Lycaena phlaeas
前翅長:13mm~19mm

ヤマトフタツメカワゲラ
カワゲラの仲間は単眼と呼ばれる目が沢山付いていますが二つしかないのでフタツメカワゲラ。
カワゲラ目カワゲラ科ベニシジミ属
Neoperla nipponensis
体長:8mm~12mm

ビロードツリアブ
毛むくじゃらでモコモコした姿が可愛らしいアブ。成虫は花の蜜を吸っていますが幼虫はヒメハナバチに寄生し大きくなります。
ハエ目ツリアブ科
Bombylius major
全長:8mm~12mm

クロチビミズアブ
ハエのように見えますが立派なアブです・・・といってもアブはハエの仲間なので似ていて当然ですよね。小さなアブなのでよ~く目を凝らして見ないと分からないかも?
ハエ目ツリアブ科
Xylopachygaster japonica
全長:5mm前後