ドライブマップ
木曽路の宿場町マップ
妻籠宿
妻籠宿は、1601年に中山道の宿として整えられた宿です。
厳しい山道だった馬籠峠を通ることなく、馬車でもいける新しい道(現在の国道19号)が1892年に完成し、妻籠や馬籠は寂れていきました。しかし、昭和51年(1976年)に国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれ、今は江戸時代の街並みがよみがえり、大勢の観光客が訪れています。町の中を歩くと、江戸時代の日本の街の中を散歩している気分が味わえます。
地図
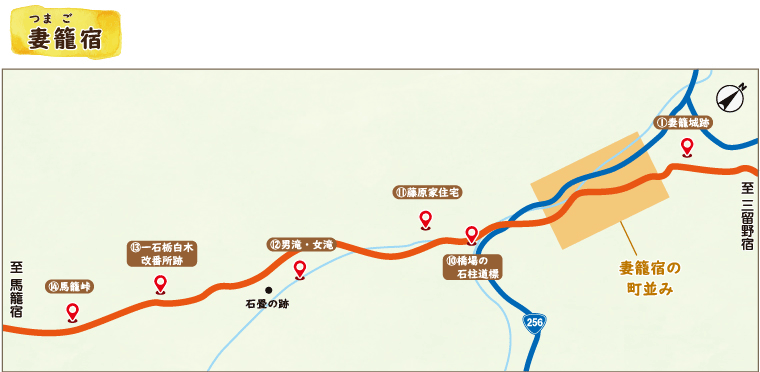
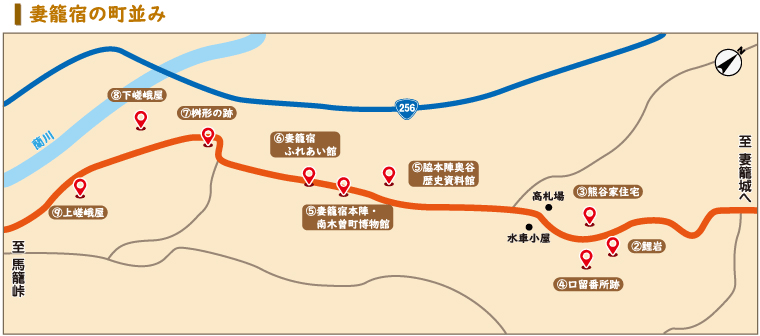
見どころ
妻籠城(つまごじょう)あと
昔から、妻籠は木曽の要でした。妻籠城は大きな山城で、城からは妻籠、三留野を見渡すことができます。
鯉岩(こいいわ)
昔のガイドブック「木曽路名所図会」にも、魚の鯉が空に向かって泳ぐ絵で紹介されている岩です。しかし、明治24年の大きな地震で形が変わってしまいました。
熊谷家住宅(くまがやじゅうたく)
19世紀に建てられた長屋です。左右の半分ずつが1軒の家として使われていました。
口留番所跡(くちどめばんしょあと)
ここに17世紀半ばまで関所が置かれ、中山道の旅人を調べたり、見張ったりしていた場所です。
南木曽町博物館(なぎそちょうはくぶつかん)
妻籠宿本陣(つまごやどほんじん)
脇本陣奥谷(わきほんじんおくたに)
歴史資料館(れきししりょうかん)
本陣は、作家・島崎藤村の母親の家で、建物は明治時代になくなりましたが、平成7年に元のように作り直されました。
脇本陣奥谷は、ヒノキを使って作られた、優れた建物で、国の重要文化財になっています。
歴史資料館は、木曽の歴史や街並みの保存のことを知ることのできる施設になっています。

妻籠宿ふれあい館(つまごじゅくふれあいかん)
木曽ヒノキなどの地元の木材で造られた建物で、みんなが使える休憩施設になっています。
桝形(ますがた)のあと
敵が入ってくることを防ぐため、道にわざと直角の曲がり角を2つ作っておいた道を「桝形」といいます。ここの桝形は江戸時代のままの姿で残っています。
下嵯峨屋(しもさがや)
江戸時代の庶民の住まいである長屋を元のように建て直したものです。
上嵯峨屋(かみさがや)
18世紀に普通の旅人たちが泊まっていた旅館を建て直したものです。
橋場の石柱道標(はしばのせきちゅうどうひょう)
明治14年に国道(現在の19号)の完成を祝って、地元の商人たちが建てた、高さ3mの大きな石の柱です。
藤原家住宅(ふじわらけじゅうたく)
17世紀よりも前に建てられた、古い建物で、昭和63年に元の形に建て直されました。
男滝(おたき)・女滝(めたき)
有名な吉川英治の小説「宮本武蔵」にも登場していた滝です。滝壺に金色の鳥が舞い込んだ伝説があります。
一石栃白木改番所跡(いちこくとちしらきあらためばんしょあと)
木曽の木の中には、許しがなく山から伐り出すことが禁止されていた木もありました。ここではそうした木曽の木の取り締まりなどを行っていました。
馬籠峠(まごめとうげ)
790mの高さから、妻籠から三留野までを見渡すことのできる峠です。ここを通って妻籠と馬籠を行き来していました。今は人気のハイキングコースになっています。
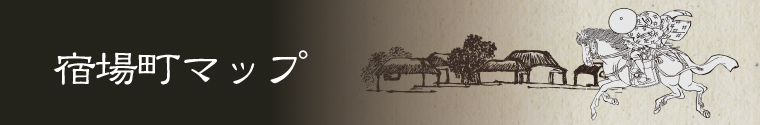
Copyright © 国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 All rights reserved.

