ドライブマップ
木曽路の宿場町マップ
三留野宿
三留野宿は、昔、木曽をおさめていた木曽氏の館があり、そのお屋敷が、「御殿」と呼ばれていたため、「みどの」になったといわれています。
ここは中山道の時代よりも前から、交通の重要な場所として、栄えてきましたが、1881年の火事で、ほとんどが焼けてしまいました。かつての本陣跡は、町のほぼ中心にあり、今は南木曽町森林組合の建物があります。
この付近は、1500mほどの高く険しい山が木曽川沿いに切り立ち、大雨が降ると土砂崩れがよく起こり、それをこの地域では「蛇抜け」と呼んでいます。
地図
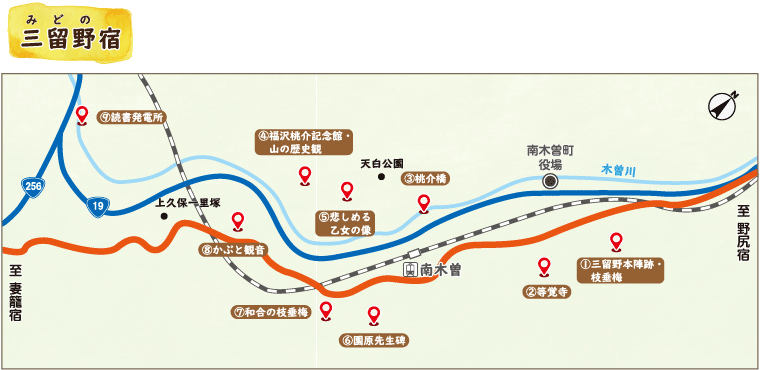
見どころ
三留野本陣跡(みどのほんじんあと)・枝垂梅(しだれうめ)
本陣の中にあった枝垂梅の古い木が、中山道の時代の名残をとどめています。
等覚寺(とうがくじ)
江戸時代に、木彫りの仏像をたくさん作ったお坊さん・円空が作った弁才天、天神、韋駄天などの像があるお寺です。

桃介橋(ももすけばし)
電力王とよばれた福沢桃介が、大正じだいにつくらせたつり橋です。ながさ247mと大きな木の橋で、近代化遺産としてしゅうりなどされ、国の重要文化財として保護されています。

福沢桃介記念館(ふくざわももすけきねんかん)・山の歴史館(やまのれきしかん)
電力王と呼ばれた福沢桃介が、大正時代に造らせた吊り橋です。長さ247mと大きな木の橋で、近代化遺産として修理などされ、国の重要文化財として保護されています。
悲しめる乙女の像(かなしめるおとめのぞう)
昔からこのあたりは土砂崩れの「蛇抜け」がときどき起こり、この像は、昭和28年の蛇抜けの犠牲者を偲んで作られました。
園原先生碑(そのはらせんせいひ)
江戸時代の学者である園原旧富は、尾張・美濃・信濃に大勢の弟子がいました。その屋敷の跡の石碑が建てられています。

和合の枝垂梅(わごうのしだれうめ)
江戸時代の木曽の酒造家の庭木として愛されていた古いウメの木です。
かぶと観音(かぶとかんのん)
木曽義仲が北陸へ兵を出すときに、かぶとの観音像を奉った所と伝えられています

読書発電所(よみかきはつでんしょ)
桃介橋・柿其水路橋と共に、近代化遺産になっており、大正時代につくられた、代表的な水力発電所です。
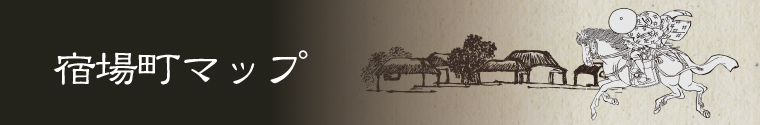
Copyright © 国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所 All rights reserved.

