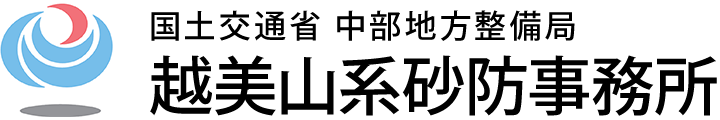クマタカ通信
vol.184 i-Construction技術を活⽤した砂防工事の現場で意⾒交換会を開催しました〜令和元年度第1回越美砂防意⾒交換会〜
2019年08月14日
クマタカ通信vol.184
今年は平年より遅めの梅雨明けとなりましたが、当事務所のある揖斐川町は梅雨が明けてから連日猛暑日が続いており全国一の暑さを記録する日もありました。8月最初のクマタカ通信では、7月30日(火)に開催したi-Constructionの意見交換会を紹介します。
i-Construction技術を活用した砂防現場で
意見交換会を開催!
【開催内容】
●日時:令和元年7月30日(火) 13:30~16:10
●場所:高地谷第1砂防堰堤(揖斐川町小津地先)/坂内白谷第1砂防堰堤(揖斐川町坂内坂本地先)
●意見交換の内容
①砂防ソイルセメント工の転圧管理について〔振動ローラ転圧による施工:INSEM(インセム)工法〕
②型枠、資材搬入仮設について
③レーザースキャナーによる法面管理について
④ウエブカメラによる現場立ち会いについて
⑤その他
●参加者:56名
建設コンサルタント:22名/施工業者:20名/発注者(中部地方整備局・越美山系砂防事務所):14名
【意見交換】
説明用資料はメールで参加者に事前配布し、内容に目を通した上で各自で準備、持参してます。(事前配布資料は記事の一番下に添付しています)
まず、高地谷第1砂防堰堤に集合し、所長挨拶のあとさっそく意見交換会を行いました。
砂防ソイルセメントの転圧管理の説明
追尾型トータルステーションの説明
転圧回数を表示画面で確認
意見交換会のようす
現場を坂内白谷第1砂防堰堤に移動し、意見交換会を再開しました。
レーザースキャナーによる法面管理を説明
出来形管理図の説明
電波状態の良い所に定点カメラを設置
意見交換会の様子
【まとめ】
砂防では他の分野に⽐べ現場条件等の制約からICT技術の活⽤がなかなか進んでいませんが、その中でも先進的に取り組んでいる現場で開催しました。現場では、事前に集めた質問に対して以下の回答を説明しました。
【質問と回答】
質問1)
INSEM材の敷均し作業について、このような広範囲な敷均し作業現場では、マシンコントロールなどが有効かと思うが導入予定はないか。
回答1)
以下の理由から採用をしなかった。
①巻出し厚が30cmで1日の施工量が平均300m3。約1,000m2を超えて作業する事はなく作業効率化は望めない。
②当初、BDによる敷均しも行ったが、機械が載ることで平坦性が悪く、BHによる敷均しを実施。材料上に乗らないことで規格値プラスマイナス3cm以内に収めやすくなった。
③最大粒径は10cmの材料のため、プラスマイナス3cm内に仕上げるのは困難なため、各層毎の管理が困難。
質問2)
ウエブカメラによる現場立会について、今回工事で実施予定なのか。また、実施するにあたり機材等が何が必要なのか。通信環境はどうなのかお聞きしたい。
回答2)
現位置での通信ができない場所では有線で映像を通信できる場所まで送ることで、現場立会として実施している。
質問3)
法面工について三次元出来形管理をしているが、縦方向・横方向の切土の間、斜め方向の切土勾配(通常過掘りとなる箇所)はモデル作成した段階ですでに1:0.3等の切土勾配を採用しているのか?
回答3)
法面工での出来形管理については、3次元設計データは利用しない。掘削完了時と法面工完了時では、ラウンディング等により形状が変わってくるため、吹付完了後の測定値で各測点、変化点ごとを3次元から2次元に変換し、机上で求める数値を出来形管理値として使用する。3次元設計データについては掘削工で必要となり、それについては各測点で1:0.3、1:1.0の勾配を採用している。
意見交換では以下の質問や意見、回答がありました。
【意見交換の内容】
凡例:
○:施工業者
●:建設コンサルタント
◎:中部地方整備局、越美山系砂防事務所
■高地谷第1砂防堰堤
◎:RIによる締固管理を行っているのか?従来の工法と今回のトータルステーションを使用した転圧管理で施工日数が短くなったのか?
○:事前に試験施工を行い転圧回数8回で締固め密度がでることを確認、念の為RIによる転圧管理システムを併用し、1回目、中層で行いすべて規定値に収まった。施工日数は短縮になっていないが品質の向上にはなっている。また、RIは割愛しており、線源棒などの掘る手間が無くなり安全性は向上した。
○:当初設計の残存型枠コンクリートパネルから鋼製型枠に変更した経緯は?。施工性と経済比較等で検討されたか。
○:事前に試験施工にてコンクリートパネルと鋼製型枠で同一条件による必要支保の重量を比較し、鋼製型枠の施工性が良いことを確認した。また、メーカーにコンクリートパネルを1割勾配で設置した使用実績がほとんど無いことを確認し、これら2点を理由に発注者と協議を行って変更した。
◎:盛土転圧システムで追尾トータルステーションを使用した理由は?また施工性、安全性はどうか?
○:自動追尾のトータルステーションでないとシステム的に機能しない。安全性の面では、転圧システムに不慣れな者が転圧作業を行うと、転圧システムのモニターばかりに気をとられ、事故につながるような危険な場合がある。
●:コンクリートとインセムの間のギザギザ状になっており、どうやって仕上げを行ってるのか?
○:本堤の法勾配は1:0.2の仕上げになっているが、当初は1:0.8だった。ギザギザの階段部において下面部の保護コンクリート強度が出るまでインセム材が設置できない為、協議を行い現在は、エキスパンドメタルを使用して施工している。
◎:過転圧の管理はしているか?
○:インセム材なので過転圧管理は行っていない。
●:今後の設計において参考にするため設計時の要望などあれば教えて欲しい。
○:当初、インセム材と保護コンクリートの間は8分勾配で、インセム材、保護コンクリート強度が出ないと次のステップに進めず工期の問題があった。あと、保護コンクリートを超えるための1リフトごとの仮橋の設置についても当初設計から検討して欲しい。
○:両端部での転圧不足は無いか?
○:肩より30cm離れたところまでは振動有のローラー転圧で行って両端部は転圧プレートで行う。
●:インセム材は、現場発生土を使用するが、全部この現場の残土を使用しているのか?
○:この現場の残土のみ使用して他工事からの持ち込みはしていない。表土除去の草などの有機物が混入したものは使用してなく、フルイ別けした粒径10cm以上の石などは除去し、この現場で発生した残土の約8割程度を使用している。
●:仮設道路を作る時のタイミング、施工日数は?
○:1リフト、90cmごとに作成している。仮橋付け替えは半日程度、工事用道路半日で計1日は掛かる。

●:インセム材の強度について現地で資料を採取して確認していると思われるが、設計強度のσ=5N/mm2も同様な配合で強度は出たか?
○:配合強度は7.5N/mm2で現地ではσ=5N/mm2以上だった。
■坂内白谷砂防1砂防堰堤
○:3Dスキャナーで法面展開図を測量ソフトで作成した実際の精度は?
○:1~2cmの誤差があった。
●:モデルデータはどこまで作り込んだか?
○:法面の面だけしか作成していない。景観は作成していない。
○:今後の展望として発注図面から3次元データーを使用したもので行うのか?
◎:中部地整では試行段階でやっており、事務所ごとでモデル的に1つまたは2つ実験的にやっている状況。今後の課題だが、山岳部は地上・衛星ともに電波状態も良くないので測量機器、トータルステーション、ドローン、WEBカメラも使用が制限され、ICT技術が普及するまで時間が掛かる。
●:現在、実験的で3次元モデルを作成するには木とか障害物などがあり、開けている場所でないと作成は困難。航空レーザー測量は可能。
また、アンケートでは引き続き意見交換会を開催していってほしいとの要望が多く寄せられました。
■参加者の代表的な感想
1)ICTを活⽤した施⼯現場の⾒学、話を聞いて、ICTが品質や安全性の向上につながっていると実感した。現段階では、施⼯⼿間は、従来とあまり変わらなかったという話もあったが、今後、ICTが当たり前に利⽤されるようになっていけば、施⼯期間も短縮され、かつ⾼品質な施設が整備されていくのではないかと感じる。CIM、3次元データの分野では、砂防はまだソフトがなかったりと課題もあるが、将来的には3次元での設計図が使⽤されることが想定されるため、設計者として、知識や技術を⾝に付けていきたいと思う。
2)砂防のICTを活⽤した現場はなかなかないので、貴重な事例を確認することができた。現場サイドは少しずつ慣れてきているとはいえ、まだまだ効率化には⾄ってない⾯もあり、現場条件が厳しい等の理由により課題が多いように感じた。
3)現場の担当者に説明してもらい、⽣の意⾒(効果のある、ない等)が聞けたのがよかった。
意見交換会解散後、足を止め、樋工(といこう)を眺めている参加者もありました。
樋工(仮排水路)の設置のようす
仮排水路の施工は、ポリエチレン管や鋼製のコルゲートパイプでの施工が多くなり、このような大規模な鋼製樋工の施工は珍しくなりました。
-----------------------
Twitter、やってます♪
越美山系砂防事務所が所管する揖斐川及び根尾川上流域の
砂防事業に関する情報を中心に発信しています。
みなさまのフォローをお待ちしております!

国土交通省 越美山系砂防事務所
@mlit_etsumisabo
発行 国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所
〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137
Tel:0585-22-2161 Fax:0585-22-2174
E-mail:cbr-etsumikouhou@mlit.go.jp
※クマタカ通信の感想やご意見もお待ちしています。
※文中の敬称は省略しています。
令和元年度第1回越美砂防意見交換会事前配布資料.pdf![]() (3931KB)
(3931KB)