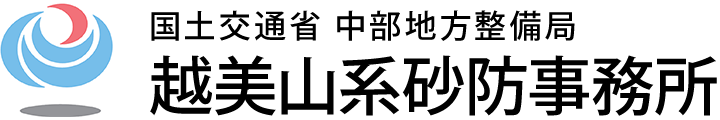クマタカ通信
vol.199 砂防工事現場で設計と工事について意見交換会を開催しました~令和元年度第2回越美砂防意見交換会~
2019年12月23日
クマタカ通信vol.199
今年も残すところわずかとなり、早朝には吐く息が白くなってきました。年末の多忙な時期ですが、体調管理には十分留意していかなくてはいけません。今号では、11月26日(火)に開催した越美山系砂防事務所主催の意見交換会のようすをお伝えします。
砂防工事現場で設計と工事について意見交換会を開催!
越美山系砂防事務所では、建設コンサルタント・施工業者・発注者の3者が工事現場に集まり、設計と工事の課題、疑問を議論する意見交換会を開催しました。
【開催内容】
●日時:令和元年11月26日(火)13:30~15:40
●場所:ナンノ谷砂防ダム3号工事現場(揖斐川町坂内川上地先)
●意見交換の内容
①仮設道路(仮橋)の設計と施工
②仮設水路の設計と施工
③堤体部地盤と設計と施工
④道路部地質条件(地盤部・法面部)と設計と施工
⑤砂防ICTについて
⑥その他
●参加者:51名
建設コンサルタント:22名/施工業者:19名/発注者(越美山系砂防事務所):10名
【意見交換会の概要】
現地に集合し、所長の挨拶のあと意見交換会を開始しました。
説明資料はメールで参加者の事前配布し、内容に目を通した上で各自で準備・持参しています。(事前配付資料は記事の一番下に添付しています)
最初に施工業者からの説明の後、質問を受け、回答や意見交換をする形で進めました。
実際に仮設道路や仮設水路を施工する上での設計との相違点や実施する上での課題と対応について意見を交換しました。また、地質調査資料による設計と実際の現場での対応や今後の地質調査設計、工事の進め方について意見を交換しました。
途中、堰堤施工現場の近くまで行き、施工状況を見学し、その後、もう一度集合し、地耐力の判断や、湧水処理、砂防ICT、3次元データの取り扱い、残存型枠等について意見交換を行いました。
最後に、今回の意見交換会がCPDS(全国土木施工管理技術士会連合会)の認定プログラムとなったので、受講証明書を参加者に配布し終了しました。

施工業者による概要説明

意見交換会のようす

仮設橋を渡って堰堤施工現場へ

堰堤施工状況を見学

意見交換会のようす
【意見交換の内容】
■ナンノ谷砂防ダム3号工事現場概要の説明
〇既設堰堤の崩壊に伴い、新設の砂防堰堤を築造する。工期は、平成31年3月からで、法面保護工を先行して作業を行い、実際の掘削工事は6月から掘削を開始した。災害復旧工事であり施工期間の短縮を考慮して、堰堤築造に伴うコンクリート打設は2ブロック同時に打設を行い、一日で最大240m3打設をした。また、現時点で約4,000m3のコンクリート打設を行ってきている。
凡例:
〇:施工業者
●:建設コンサルタント
◎:中部地方整備局、越美山系砂防事務所
◎本工事の施工方法を少し詳しく説明してほしい。
〇施工方法については、直径3.0mのコルゲート管にて水替工を行い、右岸側法面の法枠工を施工しつつ、左岸側の堰堤の床掘りに着手し、法枠工終了後、右岸側の堰堤に着手した。
●堰堤中央部のコンクリート打設時の仮排水は、施工済みの堰堤の水抜き暗渠を使用するのか。また、排水流量の考え方を教えてほしい。
〇水抜き暗渠を使用する。また、排水流量は考慮していない。仮設水路は施工性を重視して計画し、自社の手持ち資材を活用して施工した。仮設橋梁部を除いて、出水時の被害や手もどりはやむを得ないとして、施工している。
〇コンクリートの打設の管理方法を教えてほしい。
〇コンクリート打設量が多いと作業時間が長くなるので、作業員の健康状態に注意を払っている。また、現場での管理はコンクリート示方書に従って行っている。
◎日打設量240m3のコンクリート打設した時の施工状況を教えてほしい。
〇生コン工場が現場から比較的近隣に位置していて、ミキサー車を約20分で運行させることが出来たため、1.2m3のバケットを使用して、午前6:00から午後4:00の間で2ブロックの打設を完了させた。
◎設計と工事が並行して進められ、地盤反力を確認して設計していたが、その概要を説明してほしい。
●当該工事箇所は過去、天然ダム化していた場所と推察され、地盤はN値15以下の堆積物で地下水も高い状況である。下流の隣接した過去の設計事例を参照しても堰堤を設計する際に10m以上の地盤改良を計画した例もあった。堰堤を設計検討する段階で、現場を掘削して測定した平板載荷試験での支持地盤反力を用いて設計を行った。
◎ボーリングを実施した時期はいつ頃だったか。
●昨年の暮れ位に行った。
◎実施したボーリングデータで設計は出来なかったのか。
●当該ボーリングデータでの堰堤計画地盤面の地盤反力200kN/m2(砂礫)を用いて設計検討した時の堰堤の形状が、堰堤の後ろ転びが1:3近くとなってしまう。実際に掘削した地盤はボーリングデータからの推定値より良質な地盤が確認されたので、平板載荷試験で測定した支持力を採用した。
●平板載荷試験は何箇所で実施したか。
◎平板載荷試験が実施できる場所、代表1箇所で実施した。工事着手後、大きく地質が変化すればその都度平板載荷試験をするつもりだった。
■ナンノ谷砂防堰堤1号改築工事現場概要の説明
◎ナンノ1号堰堤新設に伴い、現道が埋まってしまうため、嵩上げした新設道路を設計するにあたり、当該区間で5箇所のボーリングを実施してN値が11程度だったため地盤改良工にて設計した。しかし、工事着手後、現場にて平板載荷試験を行ったところ、許容支持力が306.5kN/m2確認されたため、地盤改良工は施工対象外とした。
●何処の位置で平板載荷試験を行ったのか。
〇計画地盤の一番低い、地質がよくなさそうな場所3箇所で実施した。土質的には、礫質土だった。
■ガラン谷第1砂防堰堤工事現場概要の説明
〇副堤右岸の法面にて、切土補強工として鉄筋挿入工が設計されており、現地を掘削した結果、設計に記載されていた想定岩盤線が確認出来なかったため、法面業者に依頼して再計算を行い、アンカー配置を変更した。
◎事前にボーリング調査をしていなかったのか。
〇副堤であったため、中央しかボーリング調査は行っていなかったようだ。
〇想定岩盤線を記載する手法を教えてもらいたい。
●基本的にはボーリングデータ及び地形の状況を確認して、推定で安全側を考慮して記載する。
◎設計と現場の相違点等がある場合は、現場推進会議を行って調整してほしい。
◎今後、現場推進会議や合同現地調査に地質の技術者に同行してもらいアドバイスをしてもらえるような場を設けたい。現在はあくまで試行として進んでいる。
(現場見学 15分)
●施工ヤードに設けてあるくぼみはどのような用途に使用するのか。
〇コンクリート打設をする際のバケットを置く場所である。
●工事の変更を行う際、仮設工の工種が多くなるが、設計段階の仮設計画をそのまま発注用の仮設計画としているのか。
◎設計段階での仮設計画をそのまま発注用としている。
◎請負工事業者で施工計画を行った時点で、協議書等を速やかに提出してほしい。
〇砂防堰堤の基礎地盤において、地質が土砂部だと600kN/m2の地耐力を確認することになるが、600kN/m2の根拠は礫質土ではないのか。
●600kN/m2の地耐力は岩塊玉石の地質だと思われる。ボーリングデータに基づいて地耐力を決定している。礫質土では400kN/m2。地質によって地耐力は推定値が決められている。
〇残存型枠の設置歩掛りは人力で積算されているか。現場では人力で設置しているが、型枠重量が60kg/枚あり非常に苦労している。
◎人力で積算している。現在現場で使用している残存型枠は、一番安価な製品でお願いしている。今後、現場での施工性を勘案して協議し変更してはどうか、各砂防現場では現場の実情に合わせた積算を行うように本局からも指示が来ている。今後も現場の声をどんどん上げてほしい。
●現在施工が完了している法枠工の右端部裏の地山が崩れ水が流れているが、この状態は施工前からか施工後に崩れたのか。また、今現在は非常に不安定になっているため、対応が必要だと思われる。対応策としては、法枠工を施工する前に表土のはぎ取りを行い安定させ、横ボーリングを打ち込み地下水の流れを変えて法枠工を施工する等、今後検討が必要だと思われる。
〇現場着手前から原位置で水が湧いていた。
◎現在、水処理等も含めて検討中である。また、処理が完了するまでは上流側の仮橋を残すかどうかも併せて検討している。
●出水に対しての安全管理はどのように行っているか。
〇出水(増水)に対して、現場には雨量を設定して警報器とサイレンの設置、避難訓練、避難路の確認である。降雨量が多くなると予測されるときは、現場は休工となる。
◎ワイヤーセンサーは設置しているか。
○設置していない。
〇砂防ICTを行った具体的な施工箇所を教えてほしい。
〇砂防ICTを行った事例としては、当地区はGPSの受信波が弱いため建設機械は使用していない。起工測量、出来形測量に点群データ、地上型のレーザスキャナを利用して3次元で管理を行った。
〇高地谷ではインセム材の盛土にて盛土転圧システムを利用した。
〇平成28年度に根尾で、測量から掘削までの一連の管理を3次元データで行っている。
●設計の段階で3次元データを使用するが、施工段階の変更時に3次元で確認出来た方が便利なのか。また、使用するか。
◎図面関係の3次元データを使用できるか。
●全員使用できるわけではないが、対応できる体制は整えている。
◎今後、アンケートで何処までなら可能であるかを回答してもらう。結果を皆で共有していく。
〇残存型枠の積算方法を見直したらどうか。
◎残存型枠について、安全対策の有無等を考慮すると、単価的には通常型枠の方が安価ではないのかとか、同等の場合でも地元へお金を落とす通常型枠の選択をすべきだと議論している事務所も出てきている。
●初めて砂防の施工現場を拝見させて頂いて勉強になることが沢山あった。
●今回の意見交換会に参加させて頂き、ありがとうございました。コンサルの立場として、施工計画は共通仕様書に従って作成したが、実際の施工業者の考え方との相違があることが分かり、今後、現場推進会議等を行い議論することにより、より良い施工計画ができあがると思った。
●残存型枠の施工性や経済性を見直す良い機会となった。
◎本日の会での意見や質問事項をアンケート形式で、集約して情報の共有をはかってゆきたいと思う。
-----------------------
Twitter、やってます♪
越美山系砂防事務所が所管する揖斐川及び根尾川上流域の
砂防事業に関する情報を中心に発信しています。
みなさまのフォローをお待ちしております!

国土交通省 越美山系砂防事務所
@mlit_etsumisabo
発行 国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所
〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137
Tel:0585-22-2161 Fax:0585-22-2174
E-mail:cbr-etsumikouhou@mlit.go.jp
※クマタカ通信の感想やご意見もお待ちしています。
※文中の敬称は省略しています。
R1第2回越美砂防意見交換会配布.pdf![]() (2801KB)
(2801KB)
R1第2回事前説明要望(質問)回答.pdf![]() (439KB)
(439KB)