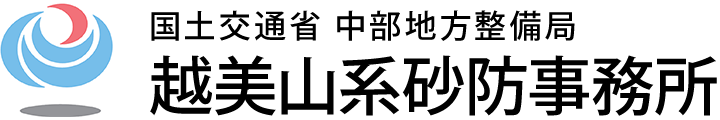クマタカ通信
vol.193 砂防学会東海支部が越美砂防管内を視察
2019年10月24日
クマタカ通信 vol.193
令和元年度 砂防学会東海支部現場見学会
【実施概要】
日時 2019年10月1日(火) 11:00~16:45
現場 蛇抜谷・地震断層観察館・根尾白谷・徳山ダム・ナンノ谷・高地谷
参加人数 砂防学会東海支部会員 16名
今回の現場視察では、1891年(明治24年)10月に発生した我が国観測史上最大内陸型直下地震であり、マグニチュード8.0を記録した濃尾地震の震源となった揖斐川上流域を対象として、地震に伴う流域の荒廃や砂防施設による対策状況を見学しました。2018年9月の北海道胆振東部地震では、大規模な土砂移動により甚大な被害が発生し大規模地震時の土砂災害防止の必要性が再認識されました。東海地方においても南海トラフ地震などの大規模地震の発生が危惧されていることから、砂防学会東海支部が本見学会を企画し開催したものです。
最初に蛇抜谷を対岸側から見学しました。見学に同行した当事務所山村副所長から、谷の下流に国道157号が存在しており、崩壊地を監視するカメラや伸縮計を設置して斜面の状況をモニタリングすると共に、国道の道路管理者である岐阜県岐阜土木事務所と情報共有し、異常時の通行規制をかけている等の説明を行いました。
蛇抜谷での現場説明
その後、地震断層観察館に向かい濃尾地震の震源となった根尾谷断層を見学しました。
断層展望広場から見た根尾谷断層
道の駅うすずみさくらの里・ねおでお昼休憩を挟み、午後は1965年9月の奥越豪雨によって大規模崩壊が発生した根尾白谷崩壊地を視察し、当時の状況を説明しました。その後徳山ダムをまわり、ナンノ谷においては2018年9月に被災し現在災害復旧工事を進めているナンノ谷砂防ダム3号の現場で被災時の状況やそのメカニズム、現在行われている工事の概要についての説明がありました。また、濃尾地震発生から4年が経過した1895年に崩壊して天然ダムを形成し、その後決壊して下流域にも被害を与えたナンノ谷崩壊地の現場を見学しました。
ナンノ谷砂防ダム3号での集合写真
最後に、砂防ソイルセメント工法(セメントと現地発生土砂を混合し堰堤の材料とする工法)としては日本最大の高さ27mの高地谷第1砂防堰堤を見学しました。
堰堤上の道路から望む高地谷第1堰堤
参加した砂防学会員からは
・これまで来る機会がなかった濃尾地震災害の現場について、今回見学できて有意義であった
・フローティング砂防ダムの被災状況を直に見ることができ、今後の対策等を考えていく上で非常に参考になった。
・深層崩壊が発生した渓流の緊急対策について、具体例や計画の考え方を確認でき参考になった。
などの意見がありました。
-----------------------
Twitter、やってます♪
越美山系砂防事務所が所管する揖斐川及び根尾川上流域の
砂防事業に関する情報を中心に発信しています。
みなさまのフォローをお待ちしております!

国土交通省 越美山系砂防事務所
@mlit_etsumisabo
発行 国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所
〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137Tel:0585-22-2161 Fax:0585-22-2174
E-mail:cbr-etsumikouhou@mlit.go.jp
※クマタカ通信の感想やご意見もお待ちしています。
※文中の敬称は省略しています。