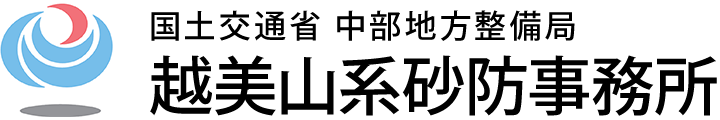クマタカ通信
vol.168 レーザースキャナによる施工管理の意見交換会を開催しました~砂防現場におけるi-Construction技術活用研修(平成30年度 第2回越美砂防意見交換会)~
2018年12月28日
クマタカ通信 vol.168
年末の多忙な時期ですが、落ち着いて行動したいものです。また、年末年始は健康管理に留意し、体調を崩さないようにしましょう。今号では、先日行われたレーザースキャナによる施工管理の意見交換会について紹介します。
レーザースキャナによる施工管理の
意見交換会を開催!
越美山系砂防事務所では、建設コンサルタント・施工業者・発注者が参加して、レーザースキャナ(LS)による施工管理の課題などについて議論する意見交換会を平成30年12月4日に開催しました。5月15日に行った第1回意見交換会に続く開催で、ICT砂防※を実施中の坂内白谷第1砂防堰堤を題材とし、工事現場の見学、施工業者及び測量会社によるLSを利用した施工管理についての解説、課題や疑問等の意見交換を行いました。
※ICT砂防:中部地方整備局が平成29年11月から始めた国土交通省が提唱するi-Construction(以下i-Con)に基づく取り組みで、急峻で落石等のおそれがある自然斜面において、起工測量、出来形管理にUAV等のICTを最大限活用することにより、工事現場の生産性、安全性を大幅に向上させることが期待されている。
【開催内容】
●日時:平成30年12月4日(火) 13:20~17:00
●場所
現場見学:坂内白谷第1砂防堰堤(岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本地先)
意見交換会:揖斐建設会館大会議室
●内容
意見交換:LSを活用した施工管理について/LS導入における課題と対応について
話題提供:国土交通省砂防部からの話題提供
●参加者:52名
建設コンサルタント:21名/施工業者:16名/砂防施工管理研究会:1名/国土交通省:14名
【現場見学】
現場見学を行った坂内白谷第1砂防堰堤において、工事に携わる西建産業(株)ならびに(株)イビソクから、ICT活用工事におけるLSを活用した出来形管理の実施方法について説明がありました。
■西建産業(株)
坂内白谷第1砂防堰堤は発注者指定のICT砂防(ICT活用工事)として施工しており、当該工事の工種のうち法面吹付工をICT活用工事の対象とした。
その法面吹付工の出来形管理を行うにあたり、施工前の起工測量及び吹付後出来形測量をLSを使用して実施した。
■(株)イビソク
まずLSによる起工測量を現場環境を鑑み複数回に分けて実施し、点群データを取得。次に複数回に分けて取得した点群データを評定点座標を使用して繋ぎ合わせ、座標交換し、3次元起工測量成果を作成。
このデータの第1段階のデータ化がオリジナルデータ。続いて地表面のデータ抽出とともに不要点を削除し(グラウンドデータ)、格子状に点群の間引き、補間を実施し(グリッドデータ)、最後にグリッドデータを元にTIN(Triangulated Irregular Network:不規則三角形網)メッシュデータを作成し、施工面の位置情報を3次元で表現可能とした。
一方、3次元設計データを作成し、吹付施工後に起工測量と同様にデータを取得し、3次元の法面展開図を作成して吹付施工前後の差分を把握すれば、吹付の厚みを確認可能。その他、吹付の厚みだけでなく、3次元設計データで土量確認も可能になった。
工事現場における説明
工事現場を見学しながらの意見交換
【意見交換会:坂内白谷第1砂防堰堤におけるLS導入による施工管理、課題等】
現場見学終了後、揖斐建設会館に会場を移動して意見交換会を行いました。意見を募る前に西建産業(株)ならびに(株)イビソクからICT活用工事における施工管理について説明が行われました。
■西建産業(株)
1)3次元測量について
現状の受注実態では自社にてICT用の測量データ処理機器を購入することは減価償却が困難なため、今回は外注対応。仮にICT機器を自社持ちとなれば人材育成が課題。
2)起工測量のタイミング
従来の手法では樹木等が繁茂した法面でも伐採前に測量可能であったが、LSでは樹木繁茂で地表面が計測しにくいため、伐採前に計測不可能。よって伐採前の測量ができず、天候などで工程が手持ちになる影響がある。
3)測量のみでは効果半減
現場法面吹付施工前の地形は急峻なため、測位衛星からの電波を受信しにくく、また現場に応じたICT建設機械もなく、丁張りが必要。現場条件に制約されないICT建設機械の普及を望む。
4)3次元設計データ作成
砂防工事の現場は不規則変化点が多く3次元データ作成に苦労。さらに当該工事は測量を外注対応したための変更設計データ作成時の説明までも苦労が波及。但し起工測量の3次元データを現場不一致の確認に活用できた利点有り。
5)出来形測量
元請けから外注先の測量業者へ出来形管理の精度を可視化(ヒートマップで表現)を依頼したが不可能との回答。よって点群データから2次元の出来形展開図を作成し実施。
6)ICT活用の効果
外業の測量作業は遠隔で可能なため安全性が向上するとともに作業人工も縮減されたが、内業の設計データ作成作業等が増加し、結果的に超すと増大。発注前に設計データが完成していることが望ましい。
■イビソク(株)
1)有効だったこと
安全に作業可能/良質なデータを大量取得可能/従来の測量に比して人員縮減可能/内業は専門技術ではなく一般者でも処理可能/断面追加の際に現地臨場不要
2)問題点、課題と対応策
現場条件で機材の可搬設置が困難であり作業道や機器設置箇所の確保が必要。
3次元設計データ作成に手間が必要。将来、ソフトの機能や技術開発が進み作成手間が省力化可能と考えられるが、現状では工事着手前に3次元設計データの必要性を検討したうえで判断すべき。従来の測量成果でも効果あり。
ICT活用工事における施工管理の説明
【意見交換会:導入事例やアンケートを踏まえた意見】
現場見学や意見交換会場での説明及び事前に行った意見交換会参加者への以下のアンケートへの回答を元にLS導入における課題と対応について意見を交わしました。
【事前アンケートと回答】
項目1:技術者が適用するために習熟を求められている技術等の獲得の実態や課題について
・企業研修やOJTなどによる技術知識の習得
・次世代を担う土木技術者の確保と熟練技術者からの技術継承
・i-Conに対する技術
・2Dモデルから3Dモデルへの転換における対応
・企業として技術投資及び技術協力体制が出来ているかが課題である。企業毎に全然取組姿勢が違う。
・機器や処理ソフト等、高額であるため使用したことがない。このため実際使用した時の課題等がわからないのが現状。
・受注者、施工業者によって能力にバラツキがあるのが実態である。そのための技術講習会を適時開催してもらい、能力の均一化が必要だと思う。
・当社では河川工事にて初めてLS測量に使用している。しかし、3D測量、点群作成(点群測量)も外注にて委託している。LS測量を実施したばかりなので操作方法、解析方法も解らない状態である。現場にて勉強会を行ったが技術を把握しきれていないのが実態である。これからLSによる施工管理を行うのであれば、勉強会、操作講習などの機会を設けて技術を身につけないといけない。また、LSを使用する箇所が無いと覚えることができない。
・現場で実施するためには施工計画書からの作成が必要だが、やってみて初めて分かることが多く、適用すべき工種であったとか、すべきではなかった事項等は後になって(やりながら)分かることが多いのが現状。施工計画書に書いてあるからやらないとダメとか、書いてないことでもやれば評価する等柔軟な対応が可能な体制も欲しいと思う。(結果出来なかったと言うこともデータになると思う。)
項目2:機材や工程をアウトソーシング・レンタルする場合の課題や対応策について
・機器のオペレーター、3次元データを取り扱える職員及び技術者の育成支援
・価格
・瑕疵担保責任
・機器等を年間どれだけ使用するかを考えると購入は難しい
・発注者側の単価とレンタル代金を比べると、レンタル代金の方が高価な場合がある。
・機材などのレンタル・購入に当たり設備投資に費用がかかる。また、周辺機器(パソコン等)も3Dに対応するパソコンでないと動作出来ないため新規に購入しないといけない。
・どうしても高価になるので、二の足を践むことが多いと思う。「試行」の考えを利用し。かかる費用についての補助も柔軟にお願いしたい。
項目3:i-Con時代に地域の建設人(高齢者を含む)を育むような砂防工事があるとすればどのようなものか?また、どのような行政側の支援が必要になるか?
・機器のオペレーター、3次元データを取り扱える職員及び技術者の育成支援
・事業毎にi-Conで全ての工程(測量、設計、工事、施工管理)について、受注者希望型ではなくi-Conで実施することを明確にしてほしい。
・高齢者が習得できるように講習会を複数回開催したり、習得のために必要な費用の支援が必要である
・砂防工事は山間部の厳しい条件下の工事のため、ドローンやLSによる施工管理を行うことにより安全性が向上する。また、CIM(3Dモデル)を施工箇所で使用することにより、「現場の見える化」で施工対象の構造や施工手順、周囲との干渉など画面に現れるため、共通のイメージを前提にして話が進められ、認識の摺り合わせを行う時間が大幅に短縮する。
・ICT機械を使用することにより、経験の浅い作業員でも可能。しかし、ICT機械を若手技術者が使用しても熟練技術者(高齢者)の今まで行った現場での経験工学も必要と思われる。
・i-Conでの施工を行うに当たり設備投資に費用がかかる。
・i-Con時代に地域の建設人を育むためには、i-Conに携わる環境を整えるしかないと思う。i-Conに携わる技術者やマシンオペレータの経験年数やi-Conの経験年数により加点を設けることで、経験の少ない人等を配慮し易い環境をつくり、育成するのが良いのではないか。
・i-Con時代に対応できる建設人を育むための行政側の支援として、i-Con対象工事を増すことは勿論のこと、i-Con育成対象工事を設定するのも手段であると考える。i-Con育成対象工事とは、その工事での技術者育成を考慮した工期設定をした工事のこと。i-Con技術活用は、活用当初(設計データの照査、収集等)と最終(まとめ等)が従来手法と比較して時間を要すると考えられ、特に私のような素人は時間を要し過ぎるのを恐れて敬遠しがちとなるので、「i-Conの経験日数が一定基準未満の技術者を配置し担当する」という条件で育成期間として余裕を含めた工期設定するのはどうか。
【参加者からの意見】
建設会社:今回の現場でUAVによる測量が可能であればコストは減少したか。
イビソク:UAVによるLS測量は谷が深い地形では運用が困難だか一部分でも使えて併行すれば効果がある。
設計会社:設計での3次元モデル構築に手間がかかり、作成してもデータを施工者に渡す際の取り決めがないことが課題であり、仕組み作りが必要ではないか。施工段階でどのようなモデルが役立つのか知りたい。
西建産業:現況不一致の線が明示され起工測量との差がわかりやすくなる。
国交省:詳細度の設定が課題であり現場としてどの程度の精度が必要なのか参考になる。
設計会社:データの交換方法やどの程度の情報まで含める必要があるのかわからないが課題である。災害後の緊急対応時に有効だが現場の施工としてはどの程度まで必要なのか。例えば基準点の設定は必要なのか知りたい。
西建産業:基準点を利用して丁張りを設置した。砂防堰堤であれば、法線とセンター杭を設置すれば施工できる。
設計会社:用地幅杭設置の場合、UAV測量に加え現地作業など二重に測量が必要になる。現地での作業の必要性を見直すべきではないか。
国交省:将来の測量は3次元データ取得を主として先に実施し、現地に入るにはその後になるのではないか。現地での法線やセンターの明示は現場施工での必要性に応じて実施することになるだろう。
建設会社:地山と砂防堰堤の取り合いなどについて3次元データを照査に活用できたか。
西建産業:照査時にはデータが完成しておらず利用していない。
建設会社:UAV写真測量の場合に点群データが確保できる高度は。
イビソク:よく使用されるUAVの場合は50~60mとなる。
国交省:データ受け渡しの事例を紹介する。データ完成段階に設計会社、発注者、施工する建設会社がお互い同程度の機能のPCを確保してデータ確認している。
国交省:今回の現場ではデータ取得は直営でなないが、必要なソフトウェアが200万円ぐらいするなどコスト面で課題があるため外注したのか。設計データ作成にコストがかかっている様だがこれが無くなればペイできるのか。
西建産業:社の人材が少なく現場での対応が出来ないことと、データも現場施工で活用できる部分が少ないため外注した。データ作成の前に何に活用できるか考えるべきである。
イビソク:設計時に3次元データが作成されていれば手間は減る。
建設会社:LS測量と従来の2次元測量を比較した利点は。
イビソク:測量作業は安全にできたこと。データ解析は現場を知らないパートで対応しコストを抑えられたこと。
国交省:現場作業で効率化できなかった部分は何か。砂防でのICT試行は可能性の手探り段階。完了検査時のポイントがハッキリしない。LS測量を適用する上で、効率化と検査の目的が合致する箇所での適用が必要。
西建産業:LS測量は測量業者に任せており、施工者としては効率化できなかった部分は分からない。
建設会社:どのようにすれば導入できるか。
国交省:ICTは手段であり目的は効率化や働き方の改革。部分的にでもLS測量を使用することで効率化や品質確保に有効であれば導入して欲しい。まずは慣れも必要。
国交省:年間どの程度ICT工事が受注できれば自ら機械を保有し作業できると考えるか。
西建産業:年間を通じた受注があれば自社でも保有できるのではないか。
建設会社:河川工事でLSを使用しCIMで図面を作成しているが本格的に行うには初期投資が必要である。
設計会社:データの互換性の問題もあり初期投資に慎重になる。スタンダードがあると広がりやすいのだが、
国交省:国際標準作成の動きがあるのでそれに対応することになるだろう。ただし標準化を待っていても世の中のうごきに遅れるリスクもある。
設計会社:苦労してCIMで設計したが発注が施工者希望型のため現場ではMC/MGが使われていなかった。発注者は使用を強制すべきではないか。
国交省:現在ではICT施工の7割が発注者希望型で施工されるなど率は上がってきている。インセンティブを与えているので積極的に採用し評価につなげて欲しい。MC/MGのコストが高いという意見もあるが施工計画段階からMC/MG採用前提で高効率の計画を組むと良い。積算も2018年からMC/MGに対応している。
国交省:初期投資を無くすため発注者がICT機器を貸与するのはどうか。発注者もICTに対応するようにしている。ICT機器導入には中小企業庁の補助金などがあるので利用できる。多くの現場で利活用すればメリットがでるだろう。
建設会社:MC/MGを活用した際にオペレーターから扱いにくいとの声もあった。講習会などがあると良い。
国交省:時代の変化により高齢者の建設労働者が増えている。安全確保の問題などから高齢者の仕事が減っているのではないか。
建設会社:高齢者でICTに慣れない人に合った現場に行くのではそれほど問題にならない。ICT施工の経験年数を加点要素にするなど導入しやすい環境づくりが必要だ。
建設会社:ICT導入をどこまで進めるのか手探りの段階である。技術者も高齢化が進んでおり別枠でICTが評価されれば導入しやすい。会社としてもノウハウを作る必要があり取り組みたい。
設計会社:建機メーカーは初心者でも操作できると言う。準備が整っていれば可能だが実際には経験が必要となる。
国交省:MCをベテランが操作するとより施工性が上がると建機メーカーは言っている。
設計会社:次世代の技術者の確保が困難になっている。そのためにもi-Conの推進や導入が必要であり、技術者育成は発注者側にも必要である。
国交省:ICTの知識がある技術者不足への対応や地形状況は厳しい現場への対応はどのようにしているのか。
イビソク:社内教育により技術レベルの引き上げを進めている。現場に入るための作業道の整備を受注した建設企業にお願いしている。
西建産業:測量前の打合わで作業道整備などの実施を決めている。積算で見られるとありがたい。
国交省:ICTについて昨年度はやらされている感覚が強く外注が多かった。今年度は起工測量をICT機器を導入して内業で進めるなど積極的な現場が増えており、作業も楽になっているという声がでてきている。起工測量についても発注者が費用を負担すれば自ら行いたいとの声が多い。
砂防施工管理研究会:3次元データが発注者から渡されれば受注者のメリットも高い。
国交省:活発な意見を得て課題はあるが積極的に進める意見を認識した。川上の設計から川下の施工へうまくデータを渡す方法を考えたい。砂防は全ての業者は参加するこの様な場があるのでデータの受け渡し方法やルールを自らつくり、越美のモデルとしても良いのではないか。河川や道路にも対応できると考える。
意見交換会
【西建産業のコメント】
ICT技術活用は、コスト面は別にして現場従事者が安心安全に作業できるツールのひとつであると再認識できた。現場管理をしながらICT技術を使いこなすことは大変な負担になると思われるが、人材不足の解消、生産性の向上に繋がるので、ICT活用を指定された工事に限らず県町発注工事に於いても自ら何らかのICT技術を活用していけるように努めていきたい。
【国土交通省砂防部からの話題提供】
国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課の蒲原土砂災害対策室長より、全国の直轄工事におけるICTの活用状況、i-Con導入における企業や地方公共団体への支援策や補助金、砂防工事におけるICT、CM、無人化施工の取り組み、砂防工事における品質向上等を目的とした適切な設計等に関する取り組みについて話題提供が行われました。
国土交通省砂防部からの話題提供
【まとめ】
意見交換会での発言は以下の5点に集約されました。
1)ICTの測量設計(川上)~施工(川下)への仕組みづくり・ルール化など
2)講習(公的・社内)・ICT技術導入のレベルアップ
3)コスト・効率・初期投資
4)高齢化対策・安全確保・現場環境
5)データ精度
今回の意見交換会では測量、設計、施工に携わる技術者と発注者が意見を交わし、ICT技術の導入における課題解決への取り組みを進めることが出来ました。今後も積極的に情報共有や意見交換を進めるとともに、上記の課題の解決を図り、各組織におけるICT技術の導入による建設産業全体の効率化を進めて参ります。
-----------------------
Twitter、やってます♪
越美山系砂防事務所が所管する揖斐川及び根尾川上流域の砂防事業に関する情報を中心に発信しています。
みなさまのフォローをお待ちしております!

国土交通省 越美山系砂防事務所
@mlit_etsumisabo
発行
国土交通省中部地方整備局
越美山系砂防事務所
〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺137
Tel:0585-22-2161 Fax:0585-22-2174
E-mail:cbr-ibigawasabo@mlit.go.jp
※クマタカ通信を含むHPの更新と概要を定期的にメール配信します。配信希望の方は上記E-mail宛に「配信希望」とメールを送信して下さい。
※クマタカ通信の感想やご意見もお待ちしています。
※文中の敬称は省略しています。
.jpg)
越美山系砂防事務所は、事業開始50周年を迎えました