 |
|
|
|
トップページ > 事務所関連情報 > 各出張所通信 > こまくさ通信 第28号(2011/8/26)
こまくさ通信 第28号(2011/08/26)
 |
 |
現場つれづれ |
安全協議会といいものつくろう会の安全部会が国道の現場へ(平成23年8月25日 木曜日)
 国道153号伊南バイパス飯島工区における飯田国道事務所の安全パトロールに参加しました。
国道153号伊南バイパス飯島工区における飯田国道事務所の安全パトロールに参加しました。
私ども飯島砂防出張所では、管内の現場を巡視する安全点検を定期的に実施しています。そうした安全巡視が不十分と言うことではありませんが、当出張所が所在している長野県上伊那郡飯島町で施工されている国道のバイパス工事の安全管理や、定期的に開催されている安全協議会の様子を観させていただくことで、違った角度で対象を観る(物理的にも違った角度で対象物を観ました。)良い機会となりました。
おかげさまで、河川・砂防・道路等の工事における安全という共通課題を客観的な目で見ることができ、当出張所の工事関係者や飯島いいものつくろう会のメンバーも安全施工への思いをあらためて高められたと思います。
また、7月30日のところで紹介した「県南部防災対策協議会」からも巡視に参加されていました。
最後になりましたが、国道153号伊南バイパス工事を施工されている現場の皆さんと飯田国道事務所関係者の皆さん、ありがとうございました。
バイパス工事が無事にゼロ災害で施工されることを祈念し、感謝の意にかえたいと思います。
石を使った土側溝 (平成23年8月24日 水曜日)
 路肩の崩れを防ぐことや、落ち葉などによって側溝の機能低下が生じないように、また、多様な生態系を守る(例えば生物の移動の阻害要因をつくらない)という観点も取り入れ、現場で不要となった石を巧みに利用した土側溝を施工しています。
路肩の崩れを防ぐことや、落ち葉などによって側溝の機能低下が生じないように、また、多様な生態系を守る(例えば生物の移動の阻害要因をつくらない)という観点も取り入れ、現場で不要となった石を巧みに利用した土側溝を施工しています。
石は、取り壊し対象となっていた老朽化した蛇篭(※)を撤去するにあたって発生したものです。
その石の有効活用が、土側溝への再利用です。
一般的なコンクリート二次製品であるU字型の側溝に比べ、側溝の底の部分が滑面でなく、側溝内の石が適度な粗度を生みだし、流速を低減させます。
その結果、側溝が急勾配であっても、流れる雨水は一気に流末にまで達するということはなく、流末や集水部分が溢れることや、浸食されてしまうといったことを抑制できると期待しています。
※:一説には網状の筒に石を詰めた外観が、蛇の胴体のよう見えることから、その名がついたとも言われています。
お盆休みの渓流保全工沿いの公園利用者 (平成23年8月16日 火曜日)
 一般的に世間では「お盆休み」と言われる日、砂防施設(渓流保全工)が群になっている当出張所管内の松川町を流れております片桐松川の親水施設の利用状況を見てきました。
一般的に世間では「お盆休み」と言われる日、砂防施設(渓流保全工)が群になっている当出張所管内の松川町を流れております片桐松川の親水施設の利用状況を見てきました。
平成23年3月に遊具などが整備された「むらやま公園」と浸水施設が連続的に一体となっており、利用者(写真は駐車場の様子)は、親水護岸が設置されている渓流保全工沿いや中央高速道路の高架橋下において、バーベキュー等を楽しみつつ、そうしたグループの子ども達は公園や川の中で元気に遊んでいる様子が目につきました。
家族や友人らと楽しく過ごす場となっているようで、夏の憩いの場の提供を親水護岸が一役買っているようでした。
宮田村民会館の実物「暴れみこし」(平成23年8月8日 月曜日)

太田切川の砂防事業概要を説明する機会を頂きました。
会場となった宮田村民会館のロビーには、宮田村の津島神社で行われる祇園祭(今年は7月16日土曜日に開催)の際に“壊された”はずの実物大の「暴れみこし」が展示されていました。
展示されている御輿は、祭り当日、勇猛果敢な男衆により激しく破壊される運命の、暴れみこしと同一のものだそうです。
一般的に、みこし(御輿)は神社の「ご神体」を安置してかつぐ「輿」ですので、これを壊すと言うことは、とても驚きです。天下の奇祭と言われる所以ですね。
祭り当日はこのサイズより小さい簡素な作りの「子どもみこし」も登場し、元気な子どもらによって、同様にかつがれ壊されます。
「暴れみこし」の実物を間近で観たい方は、ぜひ、宮田村民会館にお出かされることをお薦めします。
信濃川下流の浸水被害の支援に出発 (平成23年7月30日 土曜日)
 新潟県や福島県を襲った豪雨への臨機な対応。
新潟県や福島県を襲った豪雨への臨機な対応。
天竜川と同じく長野県にその源がある信濃川。その信濃川下流の浸水被害の復旧支援に出発する職員と、県南部防災対策協議会傘下の建設会社社員の方々。
県南部防災対策協議会は、東日本大震災の復旧支援にもご尽力頂いており、災害協定団体として中部地方整備局長からの災害対策関係功労者として表彰されています。
「今日は何の日?」 (平成23年7月23日 土曜日)
7.23長崎大水害…我が国で観測史上第1位の時間雨量を記録した日
 「・・・21日は晴、22日曇りと2日間だけ無降水ののち、23日夕刻から集中豪雨の直撃を受け、長与町役場では23日477mm、24日73.5mmを記録した。特に23日の午後7時から8時までの1時間に187mmという驚異的な降水量で、日本の観測史上第1位の記録となった。また、午後7時から10時までの正時最大3時間降水量330mmを記録した。・・・」(注1)
「・・・21日は晴、22日曇りと2日間だけ無降水ののち、23日夕刻から集中豪雨の直撃を受け、長与町役場では23日477mm、24日73.5mmを記録した。特に23日の午後7時から8時までの1時間に187mmという驚異的な降水量で、日本の観測史上第1位の記録となった。また、午後7時から10時までの正時最大3時間降水量330mmを記録した。・・・」(注1)
187mm/hの豪雨は、昭和57年(1982年)7月23日に長崎県西彼杵郡長与町(ナガサキケンニシソノギグンナガヨチョウ)の町役場での記録値です。一方、統計上の気象庁の最大1時間降水量としての同日の記録では、長崎県長浦岳観測所において153mm/hの観測値があります。いずれにせよ、当時、長崎県内では時間雨量で150mmを超す猛烈な豪雨が発生していました。(注2)。
また、この豪雨がきっかけとなり、後に「記録的短時間大雨情報」の創設につながったと言われています。
なお、気象庁発表では、153mm/hの降雨は、平成11年(1999年)10月27日にも千葉県香取において観測されています。(気象庁気象統計情報歴代全国ランキング参照 (http://www.data.jma.go.jp)
注1:長与町地域防災計画(平成21年6月1日修正板)P.15より転載
注2:気象庁が解説している雨の強さと振り方は5段階に分かれ、1時間雨量が80mm以上の雨は、予報用語として「猛烈な雨」で一括りされています。
掲載した写真(私が7月3日(日)に家族で訪れた際に撮影)は、駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアムのアルプス体験館に隣接の「あめ太郎(降雨体験車)」による180mm/hの降雨体験の様子です。
7.23長崎大水害の豪雨相当の「土砂降りの雨」を疑似体験できます。
近づいてみると息苦しくなるような圧迫感がりました。
|
 |
 |
国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
 |
0265-81-6411
0265-81-6421 |
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所






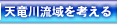
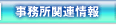




 路肩の崩れを防ぐことや、落ち葉などによって側溝の機能低下が生じないように、また、多様な生態系を守る(例えば生物の移動の阻害要因をつくらない)という観点も取り入れ、現場で不要となった石を巧みに利用した土側溝を施工しています。
路肩の崩れを防ぐことや、落ち葉などによって側溝の機能低下が生じないように、また、多様な生態系を守る(例えば生物の移動の阻害要因をつくらない)という観点も取り入れ、現場で不要となった石を巧みに利用した土側溝を施工しています。 一般的に世間では「お盆休み」と言われる日、砂防施設(渓流保全工)が群になっている当出張所管内の松川町を流れております片桐松川の親水施設の利用状況を見てきました。
一般的に世間では「お盆休み」と言われる日、砂防施設(渓流保全工)が群になっている当出張所管内の松川町を流れております片桐松川の親水施設の利用状況を見てきました。 新潟県や福島県を襲った豪雨への臨機な対応。
新潟県や福島県を襲った豪雨への臨機な対応。 「・・・21日は晴、22日曇りと2日間だけ無降水ののち、23日夕刻から集中豪雨の直撃を受け、長与町役場では23日477mm、24日73.5mmを記録した。特に23日の午後7時から8時までの1時間に187mmという驚異的な降水量で、日本の観測史上第1位の記録となった。また、午後7時から10時までの正時最大3時間降水量330mmを記録した。・・・」(注1)
「・・・21日は晴、22日曇りと2日間だけ無降水ののち、23日夕刻から集中豪雨の直撃を受け、長与町役場では23日477mm、24日73.5mmを記録した。特に23日の午後7時から8時までの1時間に187mmという驚異的な降水量で、日本の観測史上第1位の記録となった。また、午後7時から10時までの正時最大3時間降水量330mmを記録した。・・・」(注1)