ICTレポート
| 現場レポート 「ICTボックホウに乗ってきました!!」 |
平成21年2月3日(火)11:30。 くもり。
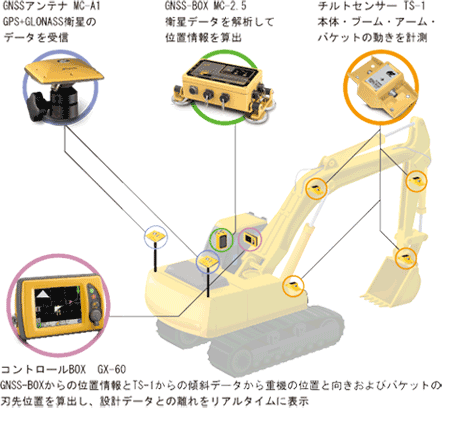
今回お邪魔した現場は浜松河川国道事務所発注の「平成20年度天竜川池田河道掘削工事」です。
この工事は、天竜川に堆積した土砂を河道確保のため掘削する工事で工事延長約570m、掘削土量は50,000m3ということです。
そして、土砂掘削を行うバックホウ数台のうち1台をICTバックホウで試験施工を行い、作業量、施工精度等の検証を行っています。
先ほどから「ICTバックホウ」といっておりますが、技術名としては「油圧ショベルのマシンガイダンス技術」(情報化施工推進戦略より)と言います。
簡単に仕組みを説明しますと、GNSS(GPS)と角度センサ等の組合せで、機械本体及び掘削バケットの位置・高さを情報取得し、あらかじめシステムに入力された設計データ(図面)との差を計算してモニターでオペレータに知らせる(ガイダンスする)技術です。(構造は右図を参照してください。 画像:
(株)トプコンHPより)
本技術の導入により、工事施工前に行っていた丁張り作業の必要がなくなり、施工の効率化が期待されています。
今回残念ながらオペレータさんの昼食中におじゃましたため、インタビューすることができませんでしたが、その時間を利用して乗ってみました!!
資格はとったものの、バックホウの運転は2回目というペーパードライバーの僕がどこまで操作ができるのか試してみます。。
まず運転席に座って操作の説明を受けます。操作は簡単。要はモニタを見て、法線にバケットの刃先を合わせてけばいいんですね・・・

モニタを見ると、今自分が3D図面上のどこにいて、どの面を掘削するかが表示されていました。
まずは法面に平行になるように旋回させます。(ガイダンス画面左上の三角がまっすぐになればOK)
次にバケットの刃先を法線に合わせてと・・・ (これもガイダンス画面で上下の矢印や数字で教えてくれます)
ココまではOK!OK! がっ・・・ ここから先どうやって掘っていいのやら見当がつきません。ちょこちょこ削るのか?それとも一気にガサッと?
試行錯誤すること約20分 あっという間に時間が過ぎ、昼休み終了で選手交代となりました・・ 惨敗・・
やはり、いくらガイダンス機能がついていると言っても、バックホウを使いこなせる人じゃないと全然ダメなんです。(当然ですが)
建設ICTが普及すれば熟練工が必要なくなるとか、いなくなると聞きますが、実際にはそうはいかないと思いました。やはりどこにでも熟練された技術は必要で、操縦技術とICT技術をうまく持ち合わせる事によってはじめて施工性のアップや品質のアップにつながるのではないでしょうか。恐らく(間違いなく)このICTバックホウに熟練工が乗れば最強の施工手段となることでしょう・・
【マシンコントロールがあれば・・】
試乗の後、敗北感をひきずりながら現場の状況を見ているとちょうど施工者の方がレベルとスタッフで掘削面の高さを測っていました。
「7センチ下げー」、「23センチ下げー」
その後、ブルトーザに乗り込み、高さを調節。オペレータの方はさっき図った数値を覚えているのか、それとも感覚でか、スイスイと整形していました。
「すいませんっ!!話聞かせてくださいっ!!」 ここからインタビュースタート(○:僕、△:施工者)
○「いつもこのようにされているんですか?」
△「そうですよ」
○「そうですか・・ オペの方はさっき測ったのを覚えてるんですね」
△「だいたいの数字は分かってるけど後は感覚。ブルはなかなか難しいよ。」
○「そうですよね。実はこんな現場にぴったりな機械がありまして・・・ ブルの排土板を走る場所によって自動制御するのがあるんです。」
△「それ(今来ている)研究所の人から聞きました。 それ使ってみたかったなぁ・・ 」
○「確かにこの現場は広いので、そのブルを使えばさっきみたいに測らなくてもいいですもんね。もしよければ次回ぜひどうぞ・・」
△「・・・」
○「すいません。どうもありがとうございました。」
2年後のこの現場は・・・・
・ICTバックホウで仮掘削
・マシンコントロールブルトーザで自動整形+出来形自動計測
・計測データはリアルタイムに現場事務所・出張所等へ送信し出来形管理/工程管理
・監督検査もそのデータを使用
となっているでしょうか・・・
| 試行工事現場の様子 |
今回の現場も河川敷ということもあって広いです。

|
ツノみたいに見えるのがGPSアンテナ

|
試行錯誤で掘削中

|
レベル計測中「7センチ下げ~」

|
バックホウで掘削後整形のブルトーザで整形

|
現場にはGPS受信機もありました

|
|
|
|

