 |
|
|
|
トップページ > 事務所関連情報 > 各出張所通信 > こまくさ通信 第34号(2012/ 2/ 3)
こまくさ通信 第34号(2012/ 2/ 3)
今日は節分 (平成24年 2月3日 金曜日)

画像は伊那市の某スキー場から臨める天竜川と三峰川合流点とその背景を飾る南アルプスの山並みです(掲載の画像は、1月初旬の休みの日に撮影したもの)。
暦の上では明日から春。
スキーヤーやスノーボーダーの皆さんはまだまだ雪が恋しい季節かもしれませんが、県内北部などで豪雪被害を受けている方々などは、速やかな雪解けを望んでいらっしゃることでしょう。
四季の最初に位置づけられている春(プリマベーラ)。
新しい事への期待と不安を感じる季節でもあります。
と、同時にスギ・ヒノキの花粉アレルギーに悩まされている方々にとっては「今年の花粉飛散量は少なめ」という予報に、少々安堵しつつも、嫌な季節であったりもします。
ちなみに、花粉症の元凶のように言われているスギ・ヒノキは、諏訪湖の釜口水門から天竜峡に至る天竜川上流部ではあまり分布せず、どちらかといえばミズナラ等の落葉広葉樹林やカラマツ等の針葉樹林が広がる豊かな自然環境となっています。
ただし、名勝天竜峡から鹿島に至る中流部の渓谷沿いの山地には、天竜美林と称されるスギ・ヒノキの人工林が広がっています。
本日の締めくくりとはなりますが、節分の「豆まき」のかけ声になぞられ、地域の皆さまをはじめ国民の皆さまの安全・安心のために「福」が内外に行き渡ることを祈念したいと思います。
明日から2月 (平成24年 1月31日 火曜日)
早いもので、明日から2月。今年は閏年のため2月の末日は29日です。
2月の日数が例年より1日多いと、寒風厳しい月が1日多いという感覚になり、少々辛い気分になったり、逆に、1日多いことで得した気分になったりはしませんでしょうか?
特に、納期や工期といった期日が2月末日を含める場合には1日多いことのありがたみを実感されることも多いのではないでしょうか。
さて、この2月といえば、「渓流釣り」の解禁日や、「ザザムシ漁(12月1日〜)」の解禁最終日が、訪れる月であるなど渓流河川が話題にのぼる季節ではないでしょうか。
このザザムシからネーミングした姉妹通信が、「ざざむし通信」です。(ちなみに、1月26日のところで紹介した「よたっ子通信」第1号も、「ざざむし通信」を発行されている伊那出張所内にて発行されています。)
ザザムシとは、伊那地方(天竜川上流域)の砂礫河原の瀬に生息するヒゲナガカワトビケラを中心に、カワゲラ・トビケラ・ヘビトンボなどの水生生物を総称した呼び名で、これを食材にした佃煮こそ、全国にその名を知られる伊那地方が誇る珍味です。
また、このザザムシを含む水生生物は、日本全国の河川の水質判定指標といった役目も担っています。(天竜川上流部の「平成23年度水生生物調査の結果」はこちら)。
例えば、この調査結果によりますと、駒ヶ根市内を流れる天竜川支川の太田切川下流部(大田原橋)では、きれいな水に生息するヘビトンボをはじめ、カワゲラ・ナガレトビケラ・ヒラタカゲロウ等が見つかり「きれいな水」に分類できることが分かります。
こうした水生生物はやがて成虫になり飛翔・産卵して一生を終えるものや、肉食性または主に肉食性の有用魚類(地元漁協の活動によって放流されるイワナやアマゴといったサケ科の淡水魚で、渓流釣りの格好の対象)の餌資源として生態系を支えることで一生を終えるものもいます。
その一方で、前述したサケ科のサカナに対してコイ科のサカナにも肉食性(雑食性)のものが多種存在します。コイ科の魚類の中でも、今、特に気になるのがカワムツです。
このカワムツの生息域の分布が飯田下伊那地方で拡大しているといった専門家による調査結果が、昨年11月に県内地元紙に掲載されました。この記事を読み、あることが気になり始めました。
どういうことかと申しますと、このエリアにはカワムツと生息域や餌資源が競合するカジカを積極的に保護している片桐松川という川があります。そしてこのカジカ自体を私たちも在来魚種として保護してきているからです(「こまくさ通信」第11号参照)。
もしも、今後カワムツの分布が拡大してゆけばカジカとの生存競争が激化し、場合によってはカワムツが優占種となりうることも考えられます。
いずれにせよ、今後もこうした魚類の往来や分布については、専門家による生物調査の結果を見守りながら、情報交換を進め、関係機関との調整に努めてゆければと考えています。
与田切ネットワーク新年初会合 (平成24年 1月26日 木曜日)
夜、与田切川の砂防林を育んで頂いている与田切ネットワークの会合に参加しました。
皆様それぞれに一日の仕事などを終えた後に、こうしたボランティア活動の会合に集まって来てて頂けることは実にすばらしく、頭が下がる思いです。
与田切ネットワーク事業の反省や来年度事業への検討についての話し合いが進むと、昨年11月3日に開催した「よたっ子と遊ぼう2011」での反省点になり、「よたっ子通信(表面)」・「同(裏面)」の話題が持ち上がりました。
この通信のおかげもあり、眉間にしわの寄らない、なごやかで前向きな会議となりました。
会員の皆さまを牽引している代表者の方々それぞれが、自分たちなりにもてる責任の範囲で、できる限りの努力をされていることによって、この会が存続しているのだと、この会に顔を出す度に思う次第です。
ぜひ、来年度も会の活動が成功することを願っています(与田切ネットワークの最新ブログはこちら (http://blogs.yahoo.co.jp))。
駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアムと深いつながりの… (平成24年 1月22日 日曜日)

日曜午前、駒ヶ根ビジターセンター(駒ヶ根観光協会事務所)にて、上原裕子さんによる山野草の寄せ植え指導がありました。
写真の寄せ植えは講師の上原さんの作品です。
作品を鑑賞させて頂くことで、心がとても和みました。
なお、当センターでは上伊那郡中澤村(現在の駒ヶ根市中沢)出身の登山家である木下寿男さんの常設展も開催されています。
山登り・スキー・アウトドア体験が好きな方や、その道具の変遷に興味がある方にといっては必見です。
( 信州 駒ヶ根ガイド
次回の“山野草寄せ植え講座”の開催日時はこちらです。 (http://www.kankou-komagane.com) )
阪神・淡路大震災から17年 (平成24年 1月17日 火曜日)
西日本の大都市を震撼させたあの大地震から17年の時が経ちました。
当時、中部地方整備局管内の隣県西部(西濃地方)でも目が覚めるほどの大きな揺れがありました。
その当時、地震速報を確認しようとしてテレビの電源をONにしたのですが、小さな揺れの地域だけの速報しか表示されず、時間だけがむなしく過ぎ、震源地がどこなのかが分かるのはずいぶん経ってからだった印象が、今の私の記憶として残っています。
そして、近畿地方の周辺の震度から予測し、大阪・神戸を中心に何か恐ろしい事態が起きているのではないかと感じたことを今でも憶えています。
その後、支援チームの一員で現地に行き、テレビの映像だけでは伝えきれていない多くのことを感じとることができました。
ちょうど、この震災を機にインフラ(国土交通省の英語標記の単語の1つにもなっているインフラストラクチャー[注、当時は建設省])という言葉が拡がりました。
同年(1995年)の夏には、インターネットという技術が飛躍的に発展するきっかけとなったコンピュータの基本となる某社のオペレーション・システム(OS)が「95」という西暦年をキーワードに発表された年でもあります(この年、世界が注目した出来事として、地下鉄サリン事件、大リーグで野茂投手が新人王獲得、ノルディック複合の萩原選手がW杯で史上初の個人3連覇、世界貿易機関[WTO]発足など)。
このインターネットという通信技術の発展によってパーソナル・コンピューターの一般家庭への普及が始まったといっても過言ではないでしょう。
しかも、この震災後、コンピュータの普及と重なるように一般の方々による携帯電話の使用が急速に進みはじめました。
こうした情報化社会の中で、再び私たち日本人だけでなく世界を震撼させたのが、昨年、東日本を襲った巨大地震です。
目を覆いたくなるような生々しい惨状の画像や言葉が津波のごとく地球を伝播するように、情報の波として世界中へ伝わって行きました。
今年が日本の復興元年となり、日本が早く元気を取り戻し、世界中に元気と心の豊かさを広められるよう願うとともに、私たちも微力ながらその力の支えになれるよう、頑張りたいと思います。
安全パトロールを実施 (平成24年 1月12日 木曜日)

 新年最初の合同安全点検です。
新年最初の合同安全点検です。
この日の昼のニュースでは、県内はこの冬一番の冷え込みとのこと。
厳冬期に入り、現場では施工対象物の凍結対策は当然のことですが、作業される方々が使用される各種器具等の凍結にも注意の目配りが必要です。
例えば、足場の凍結により足を滑らせるといったことや、凍結した器具の可動部を力任せに動かそうとして、その弾みで思わぬ事故に繋がったりとか・・・。
発生しうる事故を想像し可視化した上で(現場では「危険箇所・危険要因の見える化」などと呼んでいます。)、こうした事故を未然に防ぐ努力がなされています。
画像は12日に実施した安全点検の状況の様子と安全を心がけるための場内の安全標語看板の掲示例です。
朝日を浴びる駒ヶ岳 (平成24年1月某日)

 出勤前、駒ヶ根市内から西方を眺めると、沈んでゆく月と朝日を浴び美しく赤色に染まった山肌(モルゲン・ロート)の中央アルプスが見えました(写真上)。
出勤前、駒ヶ根市内から西方を眺めると、沈んでゆく月と朝日を浴び美しく赤色に染まった山肌(モルゲン・ロート)の中央アルプスが見えました(写真上)。
別の日(晴天の休日)の昼、同じ場所から同じアングルで眺めた中央アルプスが下の写真です。
青空に映える美しい山肌が見えました。
天候や時間によって美しい山麓が千変万化する中央アルプス。
南信州のすばらしい景観を構成している観光資源だと思います。
与田切通信第3号を発行


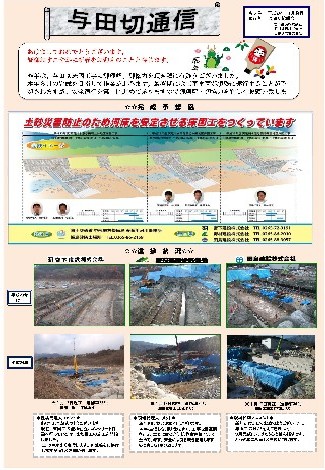
『こまくさ通信 増刊号“与田切通信第3号”』が発行とになりました。
添付画像は晴天時(1月12日)と降雪時(1月20日)に、異なるビューポイントにて撮影したものです。
降雪に見舞われた日には、工事区間への進入ルートの生活用道路も、工事協議会の協力で除雪がなされており、協議会としての地域への気配りが行き届いていました。
クリックでPDFファイル(842KB)をダウンロードできます。
|
 |
 |
国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
 |
0265-81-6411
0265-81-6421 |
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所






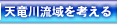
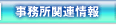




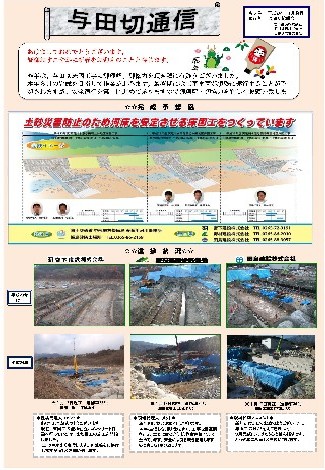





 出勤前、駒ヶ根市内から西方を眺めると、沈んでゆく月と朝日を浴び美しく赤色に染まった山肌(モルゲン・ロート)の中央アルプスが見えました(写真上)。
出勤前、駒ヶ根市内から西方を眺めると、沈んでゆく月と朝日を浴び美しく赤色に染まった山肌(モルゲン・ロート)の中央アルプスが見えました(写真上)。