 |
|
|
|
トップページ > 事務所関連情報 > 各出張所通信 > こまくさ通信 第29号(2011/9/20)
こまくさ通信 第29号(2011/09/20)
 |
 |
現場つれづれ |
宝剣岳や千畳敷カールを映す「駒ヶ池」※ (平成23年 9月某日)
 飯島砂防出張所の砂防工事対象河川である太田切川。この太田切川が流れる駒ヶ根市でも日中は暑い日が続いていますが、朝夕はめっきり涼しくなり、秋の気配を感じられるようになりました。
飯島砂防出張所の砂防工事対象河川である太田切川。この太田切川が流れる駒ヶ根市でも日中は暑い日が続いていますが、朝夕はめっきり涼しくなり、秋の気配を感じられるようになりました。
駒ヶ根市内でこの時期にお薦めなのは、駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアムの『七名石コース』です。コースを歩かれると、秋の気配をさらに深く感じることができます。ぜひフィールドミュージアムのガイドマップ (http://field-museum.kankou-komagane.com) を片手に朝の散歩でもどうでしょう。その時、立ち寄っていただきたいところが「駒ヶ池」です。天気が良く風の弱い日の朝は、陽光を浴びた宝剣岳や千畳敷カールが、静かな水面に険しくも美しい姿を映し出しています。
私も天気の良い日の早朝には時々訪ねている場所の一つです。
さて、『七名石コース』はそのネーミングの由来でもあります巨石が、コースの各所に点在しております。その巨石は約9万年前に氷河によって千畳敷カールからしらび平まで運ばれ、その後、2万年前後の土石流頻発時に、土石流によって太田切川扇状地へ運ばれた物だと考えられています。
伊那谷の形成過程や砂防事業の大切さを実感する上でも貴重な天然資源です。
ところで、一般的に沖積平野を流れる河川では、大雨が降ると水かさが増し、物を押し流そうとする力“掃流力(河床の砂礫を掃くように流そうとする力)”が大きくなります。すると、川底(河床:かしょう)や川岸(河岸:かがん)が削られ(浸食し)ます。こうした大雨で幾度となく川が削られると、谷が深くなったり川幅が広がったりします。
しかし、伊那谷の天竜川では、こうした一般的な谷の形成ではなく、特に数十年前に起きた速度の早い中央アルプスの隆起が影響した特殊な形成過程だと考えられています。詳しいことはまた、別の機会に紹介していきたいと思います。
参考資料:天竜川サイエンス編集委員会『天竜川サイエンス』
駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアムのウェブサイト(http://field-museum.kankou-komagane.com)
※:ガイドマップ (http://field-museum.kankou-komagane.com) の中央に位置する人工の池。
灌漑用に水を温めることを目的に三六災害2年前の昭和34年に完成。
実りの秋と「田切」の地形 (平成23年9月8日 木曜日)
 朝晩、急に涼しくなりました。皆さん体調はいかがでしょうか?ブタクサなどの花粉症で悩んでみえる方もみえるとか・・・。
朝晩、急に涼しくなりました。皆さん体調はいかがでしょうか?ブタクサなどの花粉症で悩んでみえる方もみえるとか・・・。
季節の変わり目です。体調管理には十分お気を付け下さい。
早朝、自宅の部屋の窓を開け、空を見上げれば昨日に続く気持ちの良い秋晴れ。
そこで、いつもより早めに自宅を出で、南駒ヶ岳・田切岳・摺鉢窪カール・百間ナギといった、中央アルプス東麓の美しくも険しい地形景観を眺めたるために、飯島町内の某所を訪ね、中央アルプスを背景に稲穂を配した写真を撮影してきました。
 私自身は「『米どころ』として知られた飯島※1」らしさがあふれる、美しい癒しの光景だと思っています。
私自身は「『米どころ』として知られた飯島※1」らしさがあふれる、美しい癒しの光景だと思っています。
左の写真、左から、
・仙涯嶺 2734m
・南駒ヶ岳 2841m
・田切岳 2730m)。
また、その稲穂からは農家の方々が丹誠込めて育ててきた思いも伝わってきます。日本の主食を支える努力に、あらためて頭が下がる思いです。
※1:『田切区誌』より引用。
 さて、この中央アルプス東麓の景観構成要素でもあり、いくつもの川の名前にもなっている田切地形(左の写真.写真の右下隅に見えるのが与田切川)。
さて、この中央アルプス東麓の景観構成要素でもあり、いくつもの川の名前にもなっている田切地形(左の写真.写真の右下隅に見えるのが与田切川)。
この田切地形は、天竜川を挟んだ南アルプス側では見られません。
「南アルプス側は堆積岩地層からできており、降雨後に岩盤浸透があるのに反して、中央アルプス側は花崗岩の地層で、降雨によって飽和側方流が起きやすく、表層崩壊が頻繁に発生しやすいことが原因と言われており、地層と土壌内の水の流れが密接に関係していることが、最近の調査から明らかになりつつある。※2」と言われています。
※2:『天竜川サイエンス』より引用。
飽和側方流とは、透水性が低い地層の上の土層が降雨により飽和状態になった時、土壌中で斜面方向に発生する水の流れのことです。
この表層で起きる、表層崩壊という現象に対し、深層崩壊とは、表土層だけでなく、深層の風化した岩盤も崩れ落ちる現象で、発生頻度は表層崩壊によるがけ崩れなどより低いですが、一度発生すると大きな被害を及ぼすことがあります。
 花崗岩の表層崩壊は、岩の風化により発生が助長されます。例えば、風化の要因の一つに樹木の根が地中深くに張りめぐることが挙げられます(左の写真)。
花崗岩の表層崩壊は、岩の風化により発生が助長されます。例えば、風化の要因の一つに樹木の根が地中深くに張りめぐることが挙げられます(左の写真)。
林業の衰退によって、森林の手入れがされないまま放置されると、森林の荒廃により地表の「保水力」が失われてゆくだけでなく、表層崩壊が助長されるという悪循環となり、土砂災害や洪水の増大に結びつきます。
森林は、光合成により大気中から二酸化炭素を吸収し、木材として炭素を貯蔵することで地球温暖化防止に重要な役割を果たしています。特に、健全な針葉樹の人工林などは、面積当たりの二酸化炭素の吸収量が大きいことから、間伐などの適切な森林整備を行い、その健全性を保つことが重要です。
また、伐採した木材を住宅や家具などに利用することは、木材の中に貯蔵された炭素を固定し続けることであり、同様に地球温暖化防止に貢献します。
さらに、木材をバイオマスエネルギーとして用いることは、それによって二酸化炭素が排出されても、もともと大気中にあった二酸化炭素が戻るだけ(いわゆるカーボンニュートラル)ですから、これによって化石燃料の使用を減らせば、地球温暖化防止に寄与することとなります。(中部森林管理局 『国民の森林 国有林』より転載)
以上のように森林管理は、直接的な森林の荒廃を防ぎ、保水力低下を抑制するだけでなく、地球温暖化防止対策として機能しており、間接的にも地球温暖化といった気候変動が原因での豪雨発生の抑制にも役立っているようです。
こういったっことからも治山(森林管理など)と治水(砂防事業)は土砂災害を防ぐための力強い両輪と言えます。参考に、間伐木材については砂防工事においても残存型枠として利用しております。
飯島いいものつくろう会 (平成23年9月5日 月曜日)

今年度第2回目となる「飯島いいものつくろう会」を、飯島町農村環境改善センターで行いました。
講演は、天竜川流域の土砂に関する学習という位置づけで、2部構成(各1時間)にて進めました。講演後には、各部会毎の討議と活動報告を行いました。
まず、飯島砂防出張所長が『天竜川流域の現在、その流域土砂について』と題して、セグメント・土砂生産・流砂・土砂バイパス・土砂移動の連続性・河床材料の変化・河川環境というキーワードで綴る河床材料に焦点をあてた天竜川の河道概論的な話題を。
続いて、当事務所砂防調査課専門官が、与田切川流砂観測施設を使った継続的な調査に基づく、土砂移動特性・土砂動態観測などについて、天竜川の竜西支川である与田切川に焦点を当てた特論的な話題を。
さらに特論的な話題で取り上げた与田切川の流砂観測施設を、現地にて会員の皆さんへ解説しました。
今日も、台風12号がもたらした豪雨による洪水氾濫や土砂による災害が全国のニュースで伝えられています。こうした土砂災害を直接防ぐための砂防施設を施工する際の知識としてだけでなく、河川全体の自然の営みを視野に入れた多自然川づくりを推進していく上でも、河道内の土砂移動といった基礎知識や関連する最新知見を学ぶことはとても重要です。「飯島いいものつくろう会」の目指す工事の安全や施工面での工夫として、これからもこうした取組みを続けていければと思います。
21世紀与田切森と川づくりネットワークの会合 (平成23年8月31日 水曜日)

夕刻、「21世紀与田切森と川づくりネットワーク(通称、与田切ネットワーク)」の会合が飯島町農村環境改善センターにて行われました。
テーマは11月3日(祝・木曜日)に与田切川砂防林で開催予定の『よたっ子と遊ぼう2011』での取組みについて。
ワークショップ形式を取り入れた会合ということで、仕事帰りのお疲れの中にも関わらず出席していただいた会員の皆さんは、積極的に“KJ法※”を使って色々なイベント案を提案されていました。
今年は8月のフェスティバルin与田切が降雨で中止となりましたので、ぜひ11月3日の与田切でのイベントは成功させたいという皆さんの思いが伝わってきました。
※:KJ法は川喜田二郎の発案でローマ字読みの頭文字から名付けられたと言われています。詳しいことは、川喜田二郎の著書をご参考下さい。
|
 |
 |
国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
 |
0265-81-6411
0265-81-6421 |
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所






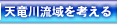
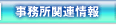




 午後、飯島砂防出張所管内での砂防工事のゼロ災害を目指し、工事現場の安全点検を行いました。(ただし、以下の内容は、9月12日に書き加えたものを含みます。)
午後、飯島砂防出張所管内での砂防工事のゼロ災害を目指し、工事現場の安全点検を行いました。(ただし、以下の内容は、9月12日に書き加えたものを含みます。) 朝晩、急に涼しくなりました。皆さん体調はいかがでしょうか?ブタクサなどの花粉症で悩んでみえる方もみえるとか・・・。
朝晩、急に涼しくなりました。皆さん体調はいかがでしょうか?ブタクサなどの花粉症で悩んでみえる方もみえるとか・・・。 私自身は「『米どころ』として知られた飯島※1」らしさがあふれる、美しい癒しの光景だと思っています。
私自身は「『米どころ』として知られた飯島※1」らしさがあふれる、美しい癒しの光景だと思っています。 さて、この中央アルプス東麓の景観構成要素でもあり、いくつもの川の名前にもなっている田切地形(左の写真.写真の右下隅に見えるのが与田切川)。
さて、この中央アルプス東麓の景観構成要素でもあり、いくつもの川の名前にもなっている田切地形(左の写真.写真の右下隅に見えるのが与田切川)。 花崗岩の表層崩壊は、岩の風化により発生が助長されます。例えば、風化の要因の一つに樹木の根が地中深くに張りめぐることが挙げられます(左の写真)。
花崗岩の表層崩壊は、岩の風化により発生が助長されます。例えば、風化の要因の一つに樹木の根が地中深くに張りめぐることが挙げられます(左の写真)。