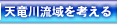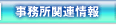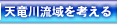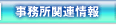|
|
|
|
トップページ > 事務所関連情報 > 事務所通信 > 天竜川上流ニュースレター 50号(2015/11/11)
天竜川上流ニュースレター 50号(2015/11/11)
中部のいい川づくりシンポジウム
〜「多様化する“いい川づくり”の制度」運用促進に向けて〜
【会 場】駒ヶ根市文化会館 大ホール
【日 時】平成27年10月3日(土) 10:30〜16:30
【主 催】特定非営利活動法人天竜川ゆめ会議
【共 催】国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所、
三峰川総合開発工事事務所、天竜川ダム統合管理事務所、
駒ヶ根市、駒ヶ根市教育委員会、長野県、長野県治水砂防協会、
(一社)長野県建設業協会、(一社)長野県測量設計業協会、
(一社)長野県南部防災対策協議会、(一社)南信防災情報協議会、
(一社)建設コンサルタンツ協会関東支部長野地域委員会
【出 席 者】約150名
全国各地の河川管理の現場では、河川環境も含めた地域実情に応じた多岐にわたる河川管理が求められてきており、そのためには地域住民との協力が欠かせない状況にあります。今回の「中部のいい川づくりシンポジウム」は、このような背景を踏まえ「多様化する“いい川づくり”の制度運用促進に向けて」を主題として開催されました。シンポジウムでは河川管理の充実を図るために進められている河川環境行政の制度整備状況や、中部地域において活躍されている市民団体の活動状況について報告がありました。その上で、近年、導入が進んできている河川協力団体制度を含む「いい川づくり」の制度運用促進を目指した公開討論が行われました。
【基調講演】
■まちづくりと川づくり
(NPO法人まちの縁側育み隊 代表理事 延藤 安弘氏)
いい川づくりの制度運用推進は何のために行うのか、また地域住民と協力した形の川づくりをどのように進めて行くにあたっての目標、コンセプトをどう考えていくのかについて、いろいろな絵本に込められた思いを読み解きながら確認していくスタイル(幻燈会)でお話いただきました。
例として、「3びきのかわいいオオカミ」という絵本では、オオカミとブタの位置づけが逆転した話のなかで、強さに対して強さで対応してもダメであること、自然の強力な力に対して、より強固なもので対応するだけではなく、柔軟な考え方を学ぶ必要があると言った形でお話は進みました。
その他、川の自然そのものに地域住民が触れあうことの大切さや、自然の不思議さや美しさを感じる感覚を養うこと、川と人との様々なふれあい方など、絵本というシンプルな絵や言葉の中に込められた思いを読み解くことで、地域住民が関わって川づくりを進めて行くことが大切であることを再認識させてくれる時間となりました。
【現状報告】
■河川環境行政について
(国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 三橋 河川環境評価分析官)
はじめに、河川管理に環境という考え方が入ってきた歴史的な流れや、これまで行われてきた取組(多自然川づくり、子どもの水辺等)を説明しました。それに続き、川を舞台として環境教育や防災事業、河川環境行政を進めていく上で、それぞれの地域で活動している団体との協力が大切であり、その地位向上が求められる中で、「河川協力団体制度」が作られた経過について紹介しました。
■中部地方整備局管内の河川協力団体の動向
(国土交通省 中部地方整備局 川瀬河川部河川環境課長)
国土交通省指定の河川協力団体は全国で193団体、都道府県知事指定は2団体が活動しています。このうち中部地方整備局管内は20団体を数え、天竜川水系においては6団体が指定されています。中部地方整備局管内における河川協力団体の登録状況や活動の内容、団体に指定による活動の利点や、また今年度の公募状況などについて紹介しました。
【事例報告】
■ゆめ会議の川への関わりと課題
(NPO法人天竜川ゆめ会議 副代表理事 橋爪 和也氏)
本シンポジウムの主催者であり、河川協力団体にも指定されている「天竜川ゆめ会議」のこれまでの活動の経過について紹介がありました。
天竜川上流部を活動拠点とし、外来植物の駆除活動や天竜川水系各地への見学ツアーの実施、イベントの開催など河川環境保全に関連した多岐にわたる取り組みについて報告がありました。活動を進めて行く上で、組織の高齢化や活動資金の問題、多くの地域住民の理解を深めていくことの難しさなど、課題点の提起もありました。
■ようこそ藤前干潟へ!
(藤前干潟クリーン大作戦 実行委員長 坂野 一博氏)
藤前干潟の環境の様子やこれまでの活動内容の紹介。
長年にわたり、清掃活動、地元の学生や環境省等と協力した調査などについて詳しく報告いただきました。特に、近年、藤前干潟で問題となっているヨシ原環境の維持・復元に向けた取り組み(中部大学等と協力して実施)については、ヨシ原の減少要因を探るための調査や淀川への現地視察の様子などについて紹介いただきました。お話の中で、事務局を担う人間の労力の大きさや関係団体との調整ごと、多くの地域住民に関心を持ってもらうことの難しさなど、これまでの活動の苦労や課題もお話いただきました。
■泳げる諏訪湖から泳ぎたい諏訪湖へ!
(下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会 田中 香奈氏)
水質が悪化し、湖岸も全てコンクリート護岸されてしまった諏訪湖の環境を改善させるため、昭和55年8月の設立以来、「諏訪湖にトンボを」、「よみがえれ諏訪湖」を合言葉に、湖岸清掃、住民への啓発活動、学習活動等について報告がありました。
浄化運動部会、クリーン祭部会、浄化啓発部会、総合研究部会の4つの部会により計画を立て、活動を長年にわたって継続してきたことにより、諏訪湖の水質は大幅に改善し、また湖岸も自然湖岸に近い状態まで復元が進むなど、成果についての報告がありました。水質が泳いでも問題ないレベルに改善された今、次は「泳ぎたい諏訪湖」を目指して活動を継続する旨の決意が述べられました。
【公開討論】
■多様化する“いい川”づくり制度の運用推進に向けて
<コーディネーター>
山道 省三氏(NPO法人全国水環境交流会)
<パネリスト>
三橋さゆり氏(前出)、坂野一博氏(前出)、近藤朗氏(愛知・川の会)、
福澤浩氏(NPO法人天竜川ゆめ会議)
河川協力団体全国協議会の山道代表によるコーディネートのもと、3つの河川協力団体の代表者と、この制度創設に関わった行政担当者で構成されたパネリストにより、いい川づくりのために河川協力団体制度等をどのように運用推進していけば良いか公開討論が行われ、基調講演者である延藤氏も加わって、いい川づくり促進のための意見集約がなされました。
・住民と行政で双方向コミュニケーションをもっと大切に
・苦労する維持管理を楽しく、はぐくむ視点
・手作りの伝統文化を伝承していく
・持続可能な生命のつながり
・取り組みの目的の明確化と参加してもらうことによる
地域の河川環境への思いの醸成
・安全と美観と活用をバランスよく
・目標コンセプトをただしつつ、ソフトとハードうまく絡める
・どう進めるかを地域での話し合い、行政は適切な支援を行う
・トラブルをエネルギーに変えて取り組む
・杓子定規ではなく、川の流れのように柔軟に
基調講演・事例報告から発展した公開討論により、いい川づくりにおける河川協力団体の現状と将来像について深い議論が展開されました。今回の意見を参考にしつつ、河川協力団体のみなさんとの活動を重ね、より良い制度運用を目指し、歩みを進めてまいります。
【河川協力団体制度】
河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。河川協力団体に認定されると、活動に必要となる河川法上の許可申請の簡素化や、河川管理施設の維持など、これに類する河川管理に関する作業を委託されて実施することが可能になります。
|
 |
 |
国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
 |
0265-81-6411
0265-81-6419 |
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所