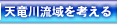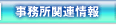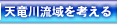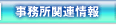|
|
|
|
トップページ > 事務所関連情報 > 事務所通信 > 天竜川上流ニュースレター 27号(2013/10/25)
天竜川上流ニュースレター 27号(2013/10/25)
日本の源流シンポジウム
〜河川環境保全と地域防災力向上の両立〜
【主 催】特定非営利活動法人天竜川ゆめ会議、NPO法人全国水環境交流会
【共 催】長野県、長野県治水砂防協会、飯島町、飯島町教育委員会、下諏訪町、諏訪湖浄化推進連絡協議会、(一社)長野県建設業協会、(一社)長野県測量設計業協会、(一社)長野県南部防災対策協議会、(一社)南信防災情報協議会、(一社)建設コンサルタンツ協会関東支部長野地域委員会
【場 所】飯島町文化館 大ホール(長野県上伊那郡飯島町飯島2489番地)
【日 時】平成25年8月31日(土)〜9月1日(日)
【参加人数】約250名程度
■開催概要
長野県は、天竜川、木曽川、信濃川、富士川などの多数の河川の源流域を有しています。日本の源流地域は、自然景観、水資源などの観点で重要ですが、地形が脆弱で災害が頻発する場所でもあります。本シンポジウムは、日本有数の河川である天竜川上流域において、自然環境保全や防災力向上をめざし、河川整備の進め方や防災対策をテーマとして開催されました。1日目は、基調講演とパネルディスカッションにより目的に関する考え方を学び、2日目は、講座と事例報告・討論会により実際の河川整備の手法に関して理解を深める内容で開催されました。
ここでは1日目のエクスカーション・基調講演・パネルディスカッションについてレポートいたします。
■エクスカーション
天竜川上流域における河川整備の事例見学として、「与田切川流路工」、「上穂沢川ふれあい広場」、「太田切川流路工」の3か所をバスで回りました。地元の小学校の子供達とともに計画して整備した上穂沢川のふれあい広場が作られた経過や、様々な個人、団体の協力のもと進められている与田切川の河畔林整備などについて、説明を受けながら現地を見学しました。
■基調講演1
河村忠男 氏(前・土木学会事務局企画広報室長)「重厚長大から生活優先へ」 〜日本の土木が溶ける〜
戦後の土木事業の進歩や、それら事業に環境や景観への配慮の観点が組み込まれてきた経過について、その歩みに関わってきた人物も紹介しながら、お話いただきました。戦後、経済や安全などを重視し、より安く、強く、長持ちすることにだけ目が向けられがちだった土木事業に、自然環境や景観、住民参加という視点や動きが加わってきた流れについて知ることができました。
■基調講演2
高橋 裕 氏(東京大学名誉教授)「治水・防災における源流の役割」
国土の保全を考えていく上で、源流がもつ役割の重要性について、お話いただきました。近年、源流において人口の減少が進むとともに、気候変動による豪雨の発生と、それに伴う土砂災害、河川の増水などが頻発するなか、流域一環で協力しながら河川整備を進めていくことが大切であることをご教授いただきました。
■パネルディスカッション 〜河川環境と防災〜
○パネラー
・平山直子(伊那ケーブルテレビジョン)
・有澤俊治(多治見砂防国道事務所)
・加藤輝和(牛伏鉢伏友の会)
・田中秀基(長野県建設部砂防課)
・中山透(下諏訪町諏訪湖浄化推進協議会)
○コーディネーター
・平松晋也(信州大学農学部教授)
パネルディスカッションでは、各パネラーより情報提供いただきながら、様々な視点から今後どのように河川の整備を進めていくべきか、活発に議論が展開されました。パネラーからの情報提供では、平成18年豪雨の際の地域放送が果たした役割や、過去の防災の取組伝承の大切さ、国や県による河川整備事業の現状と課題、地域住民による活動体制づくりなどについて紹介がありました。
討論の最後には、今後の防災力向上のための河川整備にあたって、施設整備に加え、ソフト的な取組(防災マップづくりなど)、森林整備や周辺住民の意識向上など総合的な取組を自然環境にも配慮しつつ、進めていくことが大切であることが確認されました。
|
 |
 |
国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
 |
0265-81-6411
0265-81-6419 |
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所