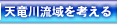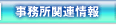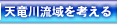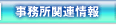|
|
|
|
トップページ > 事務所関連情報 > 事務所通信 > 天竜川上流ニュースレター 21号(2013/7/3)
天竜川上流ニュースレター 21号(2013/7/3)
【講 演】昭和三十六年災害(三六災害)の教訓から災害に備える
【講演者】信州大学名誉教授 北澤秋司 先生
【場 所】飯島町文化館 中ホール
【日 時】平成25年6月26日(水)15:15~17:00
【参加人数】約80名
天竜川上流河川事務所では、毎月1回程度、職員の勉強会「天竜塾」を開催しています。「天竜塾」は、職員の技術力向上を目指し、業務遂行の一助となる知識・経験・情報等を取得することを目的としています。今回で50回の節目を記念し、北澤秋司先生をお招きして、一般の方も聴講可能な公開講座を開催いたしました。
北澤先生のご講演では、まず52年前の6月末、伊那谷全域を襲った三六災害の概況をご説明いただきました。つづいて、災害当時に勤務されていた生田中学校(下伊那郡松川町)での教員としてのお立場から、災害に直面した人びとの避難状況や対応について、ご自身の経験を詳しく語っていただきました。
北澤先生の体験談の中には、豪雨災害の前兆を示す現象の観察や、それらへの適切な対応など、重要なポイントがいくつかありました。
①数日前から降り出した雨が27日午後より豪雨となり、グランド全体が【雨の跳ね返りで1mほどの高さまで茶色くなるほど】であった。
②先生は、早めの帰宅をすることとなった生徒達に、【自宅(谷)ではなく、より危険が少ないと思われる公民館(尾根)へ向かうよう指示】を出した。
③体育館に避難し、【土石流の兆候である沢の水位低下がないか】交代で監視した。
「子供たちを死なせてはいけないという一心」での行動の中、ご自身の足元を土石流が襲いかかるという、まさに「九死に一生を得る」体験をされました。このようなご経験から、災害に対する備えとして以下のように重要な点を提言いただきました。
・日々暮らしている地元の地形を詳しく知っておくこと。
・土石流が発生する仕組み、前兆現象などについて学び、雨の降り方、土石流の流れなどから、状況を正しく判断・予測出来るよう学習しておくこと。
・災害時の家族の動きについて、事前に話し合っておくこと。
北澤先生からお聞きした貴重な体験談は、災害の恐ろしさと、事前の備えや状況判断の対応の重要さを改めて認識する機会となりました。
北澤先生のお話を教訓として、当事務所では今後も、当時の災害の記憶を風化させないよう次代に引継ぎ、また災害への備えの大切さについての普及啓発を今後も続けて参ります。
|
 |
 |
国土交通省 中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
〒399-4114
長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
TEL
FAX |
 |
0265-81-6411
0265-81-6419 |
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所