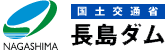- トップ
- ダム内部見学Q&A
ダム内部見学 Q&A
見学を体験された方からの質問と、その回答です。
Q.見学はよく来ますか?
A.年間で平均1500人くらいの人が来ます。
Q.セメントはどこから運んできたの?
A.大井川港から島田市経由で運ばれました。
Q.反対運動はなかったのですか?
A.多くのダム同様、水没する家屋などもあったので、反対運動はありました。
Q.たまった土砂はどうするのですか?
A.貯砂ダムにより土砂の流入を抑制し、堆積土砂を掘削除去しています。
Q.堆砂の処理はいつしてるのですか?
A.夏場、洪水に備え貯水位を低下させている間に行います。
Q.干上がった事はありますか?
A.ありません。
Q.ダムの厚みはどれくらいですか?
A.BL6付近が最大で、L=110.37mです。
Q.減勢工の水深はどれくらいですか?
A.副ダムの低い方の高さが6mです。
Q.予備ゲートのワイヤーの太さはどれくらい?
A.直径42.5mmです。
Q.コンクリートは何BLまでありますか?
A.1BLから21BLまであります。
Q.コンジットゲートは何m上がるの?
A.7.11mです。
Q.コンジットゲートは何で出来ていますか?
A.ステンレスと鉄でできています。
Q.コンジットゲートは水漏れしないのですか?
A.ゴム板が付いていて水密化されるので、基本水漏れしません。
Q.ダムは何年保ちますか?
A. ダムの各種設備を適切に補修・更新すれば、半永久的に使用可能です。四国の満濃池は飛鳥時代製造、日本のコンクリートダムで最古は兵庫の布引五本松ダムで、1887年(明治20年)に作られました。
Q.台風の時に流すの?貯めるんじゃないんですか?
A.すべてを貯めることは不可能なので、安全な量を流します。
Q.停電は大丈夫?
A. 商用電力が断線した場合、予備電源設備(2機)にて自動運転を行うので、停電しません。
Q.噴水はどこのダムでもありますか?
A.無いダムが多いと思います。あるダムは、寒河江(さがえ)ダム(山形県)などです。
Q.噴水は浮いているのですか?
A.浮いています。ワイヤーロープにより3点で係留しています。
Q.噴水は深いところから水を取っているのですか?
A.水深3m程です。
Q.噴水の周りの丸いボールは何ですか?
A.装置を係留しているワイヤーロープの位置を表示するためのブイです。
Q.農業用水は牧之原の茶畑に供給しているのですか?
A.そうです。島田市、掛川市、菊川市、御前崎市にも供給しています。
Q.何故発電しないの?もったいない。
A.(上下流に発電ダムがあり、発電事業者はダムに参加しなかった。)管理用発電は行っています。
Q.地震は大丈夫?
A. 地震を考慮して設計されています。東北の震災後の新たな基準で照査した結果、大丈夫です。