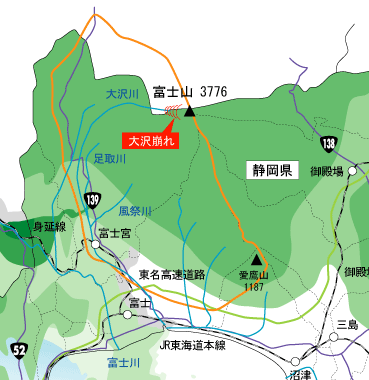| 水系概要 |
大沢川は静岡県富士宮市に位置し、富士山西斜面の大沢崩れを源頭域とし、流路延長約14km、流域面積約14km2、下流端の河床勾配1/22で、潤井川に流入し田子の浦港に流れる。また一部は芝川に流入し富士川に注ぐ。土砂生産源である源頭域は富士山西斜面の「大沢崩れ」で我が国最大級の規模を誇っている。
これまでに下流域への土砂災害を度々引き起こし、現在でも年間約16万m3の土砂が崩壊していると推測されている。 |
| |
| 直轄砂防区域の状況 |
| 大沢崩れ対策として、昭和32年静岡県にて「富士山大沢崩れ対策委員会」を設置し、その後昭和44年に直轄砂防事業に着手した。当初は大沢扇状地における砂防施設の整備を進めた。現在では導流堤の完成と床固工による遊砂地・沈砂地の整備と再度災害防止の除石工を行っている。昭和57年度からは、大沢崩れにおいて発生源拡大防止対策の検討のため、「源頭部調査工事」を行っている。また、昭和58年度から、富士山の南西山麓に位置する南西野渓(普段は水の流れはなく、大雨時に土砂を伴い流下する。)の対策工事に着手した。 |
| |
| 崩壊地の概要 |
当事業区域内における代表的な崩壊地は、富士山の土砂発生源である源頭域、富士山西斜面に位置する「富士山大沢崩れ」で、延長約2.1kmに渡り最大幅約500m、最大深さ約150m、崩壊面積約1km2崩壊土量約7,500万m3と推測され、我が国最大級の規模を誇っている。
現在でも崩壊が進んでおり、年間約16万m3の土砂が崩壊し、下流域に土石流をもたらしている。 |