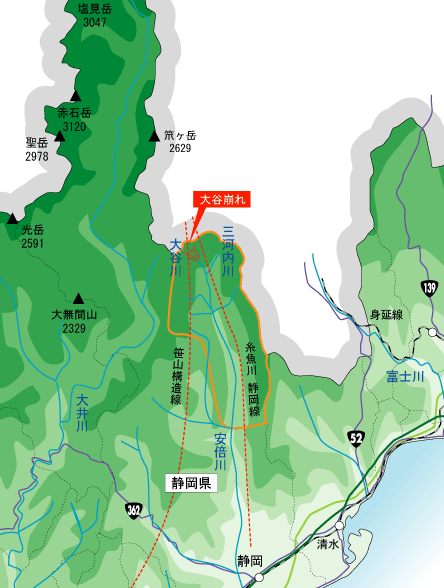| 水系概要 |
安倍川は静岡県と山梨県の県境である大谷嶺に源を発し、いくつかの支川を合わせて駿河湾に注ぐ全流域面積567km2、幹川流路延長50.8kmの一級河川である。
本川は南北にほぼ直線的に流れ流路延長は短くさらに2000m級の高山から一気に駿河湾に注ぐ典型的な急流河川である |
| |
| 直轄砂防区域の状況 |
静岡河川工事事務所の直轄砂防事業は、大正3年(1914年)8月29・30日の静岡市街の大災害を契機として、昭和12年(1937年)から実施されており、直轄砂防区域は145km2、そのうち重荒廃面積35km2(全体の約24%)、一般荒廃面積110km2(全体の約76%)となっている。
安倍川下流部には、JR東海道新幹線・国道1号等物流や人の交流を支える大動脈がある上、県庁所在地とともにこの地域の経済・産業・文化の中心となっており、河川と同様各砂防施設は、非常に重要な役割を果たしている。 |
| |
| 崩壊地の概要 |
当事業区域内で代表的な崩壊地が「大谷崩れ」である。これは、宝永4年(1707年)の大地震がきっかけとなったらしく、宝永6年(1709年)に書かれた古文書(古文書名;村差出明細帳)では、すでに崩壊が発生しているとの記載がある。
宝永の大地震といえば富士山の噴火の引き金となったであろう地震として知られている。この大地震は静岡県の各地で大きな災害をもたらした地震であったといわれている。 |