 |
|
||||||||
 |
 |
 |
 |
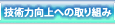 |
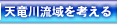 |
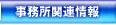 |
 |
 安全部会
飯島管内工事に携わった施工業者の安全アピール資料の中から、「これは良い、よく考えられている、他現場でも取り入れた方が良い」を基準に、安全部会の独自の視点から抜粋したものです。
安全巡視チェックリストは平成18年度の安全部会活動の成果です。
平成19年度には飯島砂防出張所での安全パトロールで活用され、
会員の関係する現場での試用を経て、使いやすさアンケートを行いました。
その結果、このチェックリストに馴れると使いやすいとの声も多く寄せられ、
公開に至りました。
安全巡視チェックリストの公開 砂防工事を念頭に作成されたものですから、 その他の工事での利用を考え、PDF形式とEXCEL形式をダウンロードすることができます。 平成21年度に改訂しました。
安全部会では安全関係の提出書類をまとめてみました。
このリストは標準的なもので、確認のために利用することを目的に作成されています。
工事によっては必要の無い書類もあれば、
さらに必要な書類も考えられます。
すべての書類の提出を義務づけるものではありません。
提出書類 完成検査で提出する安全対策書類 施工体制台帳関係書類
参考にする指針・要領・マニュアル
作業主任者の選任
法第14条の規定による作業主任者の選任は、
別表第一の上覧に掲げる作業の区分に応じて、
同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行うものとし、
その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。(安衛則 第16条)
作業主任者の職務の分担
事業者は、別表第一の上覧に掲げる一の作業を同一の場所で行う場合において、
当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、
それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。(安衛則 第17条)
作業主任者の氏名等の周知
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
(安衛則 第18条)
作業主任者の職務
作業主任者の資格要件 資格等の必要な業務 作業指揮者の選任
安全巡視に関する根拠を法令等からまとめてみました。
労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号) (特定元方事業者等の講ずべき措置)第三十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が 同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、 次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 一 協議組織の設置及び運営を行うこと。 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。 三 作業場所を巡視すること。 四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、 設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号) (安全管理者の巡視及び権限の付与)第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、 直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 (作業場所の巡視) 第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。 2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 【参考・・・土石流による危険の防止】 砂防工事の現場では施工現場内の安全巡視だけでなく、施工現場外の外的要因にも注意を払う必要があります。巡視という表現ではありませんが、 現場周辺の状況を調査し、記録しなければならないことを定めた条文として第五百七十五条の九があります。 (調査及び記録) 第五百七十五条の九 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において 建設工事の作業(臨時の作業を除く。 以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、 その結果を記録しておかなければならない。 (以下、第五百七十五条の十六まで関連の条文があります。) 土木工事共通仕様書(平成23年6月) 第1編 共通編 第1章 総則1-1-26工事中の安全確保 6.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。 特記仕様書(中部地方整備局) 第1編 共通編 第1章 総則 1-1-26工事中の安全確保 11.受注者は、共仕」第1編1-1-26工事中の安全確保の6項に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。 1) 安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、 施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、 適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。 安全巡視をする者とは 特記仕様書(中部地方整備局)にはじめて「安全巡視者」という名称が登場する。 保持しなければならない資格要件は特に記載がないし、 専任の必要もない。 安全巡視者は常に腕章を着用(特仕)し、次の巡視することで工事施工の安全確保を行うことが任務である。
【参考・・・雇入れ時等の教育】 労働者の雇い入れ等が生じた際には、事業者が安全又は衛生のために教育を実施しなければならないことも規則として条文に示されています。 第三十五条の五号には、当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること、が明記されています。 例えば、炎天下作業での熱中症予防に関することもその一つでしょう。 また、七号には、事故時等における応急措置及び退避に関すること、が明記されています。例えば、土石流発生時の現場からの退避に関することもその一つでしょう。 なお、本条文では教育する者は事業者としており安全管理者とは限定していません。 (雇入れ時等の教育) 第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、 次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 ただし、令第二条第三号 に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。 一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 三 作業手順に関すること。 四 作業開始時の点検に関すること。 五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、 当該事項についての教育を省略することができる。 |
| 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 〒399-4114 長野県駒ヶ根市上穂南7番10号
|
Copyright(C) 2006 天竜川上流河川事務所