|
|
||||

|
||||
|
||||
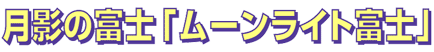 |
||||
| ●太陰暦 江戸時代まで日本では、月の満ち欠けの周期を1ヶ月として月日を定めていました。これを太陰暦と呼び、月の満ち欠けは平均29.53日、このため、現在、地球の公転周期から1年を定める太陽暦では、1年は365日ですが、当時1年は354日でした。また、太陽と違い、月は毎年同じ所を通 過せず、およそ16年周期で元の位置に戻ります。昔の人は、月の様子や位置からも月日がわかりました。 ●月影の富士の望み方 山頂に月が掛かる状態を月影の富士と呼ばれ、富士山を撮影するカメラマンの間でも話題になっています。 表紙上の月影の富士は、御殿場市の足柄峠から2月14日の午前6時23分頃に撮影されたものです。明け方の赤富士の上に丸い月が掛かっていて、とても幻想的な雰囲気になっています。次に御殿場方面 (足柄峠)からこのような明け方の「月影の富士」を望むには、2007年では、2月4日、9月28日などとなります。 表紙右下は、富士宮市人穴の東側より5月25日の午前4時30分頃に撮影されたものです。 月影の富士は日没や月の出の時間の関係で見える場所、時間帯が変化していきます。その為、カメラマンは皆、独自に、あるいは、インターネットなどを利用して月の動きを把握しているようです。 |
||||
|
||||
 |
||
|
|
||

