|
|
||||||||
 |
||||||||
| 長野県下伊那郡大下條村(現阿南町)は全国屈指の山間地であり農家の耕地面積は平均0.5ヘクタールで、零細のため多く人を満州開拓に送っていました。 昭和20年、終戦により復員軍人、満州からの引揚者など多くの人々が村に帰って来ました。村にとって、これらの人々をどうするかが大きな課題でした。 この年、政府が戦争引き上げ者の就業対策と食糧増産を目標とした「緊急開拓政策」を発表、この一環として富士西麓の開拓が開始されました。 大下條村は逸早く開拓計画を村の事業として進めることを決め、愛知県や静岡県などの候補地を見て回り、ついに西富士地域を大下條村の“分村的開拓地”として決め、入植者を募りました。 <西富士への入植>
|
 |
|
|
入植後半年、西富士長野開拓団の団長が伊藤義実氏に決まり、伊藤団長のもとに団結を強めてゆきました。
開拓団での共同生活は、自給自足であり開拓団の中に“製塩部”“製炭部”“輸送部”などを作り、開墾以外の仕事もやりました。例えば、製塩部は富士市元吉原の海岸で塩作りをし、製炭部は現金収入を得るために富士山麓の山に入り炭作りをし、輸送部はトラックを購入し、物資の運搬やバス代わりもしました。
<村の建設>
昭和23年に入ると、いよいよ広見、荻平、富士丘という村の建設が始まりました。今までの共同生活から一人一人による個人経営の始まりです。住む家は、戦争当時、兵隊が使っていた建物を壊して出てきた柱や板などを使っての“ほっ立て小屋”でした。家は雨もりがし、冬はすきま風で寒く、つらい毎日でした。特に困ったことは、水がなく、雨水をためて使わなければなりませんでした。しかし自分の家ができたことは大きな喜びでした。この頃は、陸稲、さつまいもや、大根、キャベツなどの高冷地野菜などを多く作っていました。
 |
|
|
水道は昭和24年着工、根原から水を引き、33年には完了。電気は32年迄全部の地区に電灯がともされました。道路は開拓幹線が51年に着工、57年に開通しました。これが現在の富士宮・鳴沢線です。このように村作りは確実に進められていきました。
<酪農の本格化>
昭和29年、西富士地域は「高度集約酪農地域」の指定を受けました。国から西富士地域は酪農に適した地域だと認められ、いろいろな補助をうけられるようになったのです。昭和30年国の補助でオーストラリア産のジャージー種乳牛約260頭が導入され、以後酪農一本で行くとの方針を決めました。ついに西富士での長野開拓団による酪農経営が本格的なものとなりました。
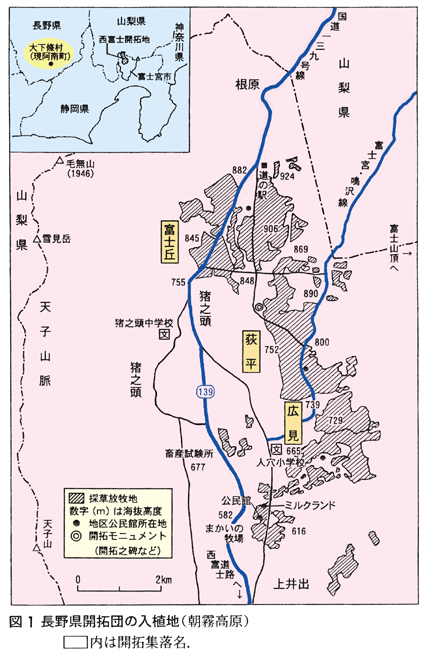
<富士マサとの闘い>
今や牧草地も約1,000ヘクタールにも広がっていますが、大規模な草地の拡大には富士山麓特有の土壌との闘いを強いられました。「富士マサ」「マサ土」と呼ばれる黒ボクの下の層で、緻密で透水性は少ないため、草木の根を通さず保水性が乏しく、表土の侵食が甚だしいという悪質土壌と向き合うことになったのです。
しかし、表面の黒ボクとその下のマサ土はうまく混ざり合うと牧草がよく育つ土になる事がわかりました。そのため、ブルドーザーに特殊アタッチメントをつけて深く掘り、表面の黒ボクと呼ばれる火山灰土と、数十センチ下のマサ土を混ぜ合わせ(「マサ抜き」と呼ぶ)その後を整地してゆくという大きな草地造成事業が行われました。
さらに、草地として牧草をまくまでに、クマザサの根や芽を三本鍬で耕し、ふるって除去し、リン酸分の少ない土壌に石灰を入れ、土壌改良をしていきました。そのような努力と苦労の末、現在の朝霧高原の広大な牧草地が出来上がってきたのです。
 |
|
草地造成事業 「富士開拓三十年史」より
|
 |
||
|
|
||