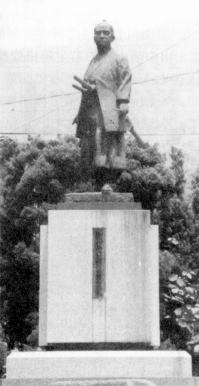| ふじあざみ 第53号(2) | |||||||||
|
|
|||||||||
 |
|||||||||
|
|||||||||
| ■噴火収束後も長く影響を及ぼす降下火砕物 足柄地域を含む富士山麓地域には膨大な量の降下火砕物が堆積し、多い所では5~7尺もの深さがあったとの記録があります。(1尺は約38cm。7尺だと約2m60cm以上積もった事になります。)足柄地域では、田畑を埋めつくし、農民を窮地に追い込んだ降下火砕物は、その後雨とともに酒匂川に流れ、川底に堆積していきました。このため、大雨の際には洪水となり、足柄平野一帯を水びたしにすると同時に、水とともに溢れ出た大量の堆積物が各地の田畑を埋めつくしました。このようなことが10年以上も続いたのです。現在はほとんど降下火砕物は残っておらず、その大部分は下流に流出したと考えられます。 一方、大量の降下火砕物に見舞われた御厨地域も、農作物などに大きな被害が生じ、噴火直後から深刻な食料問題が生じました。その他にも道が埋まって交通が困難になったり、水路が破壊されたり、土地の境界が不明瞭になるなどの問題も発生しました。また、この地域で飼われていた家の数を上回るほどの馬は、農耕馬であると同時に旅行者が須走から山中湖への道を抜ける際に人や荷物を運んで収入を得るための生活の糧でもありました。しかし、噴火による降下火砕物で牧草地も埋もれてしまい、牧草が極端に不足し、馬を飼うことが困難な状況になりました。生活が立ち行かなくなった人々は、いくらかの現金を手にいれようと、仕方なくこれらの馬を手放しました。さらに、この地域の冬場は相当に寒く、暖をとる薪や炭も不足し、人々が災害前の暮らしを取り戻すためには植生の回復を待つという長い時間が必要となりました。 ■被災住民の苦労と復興 宝永の噴火により、御厨地域の須走村も廃村になりかけていましたが、富士参詣者などを泊める宿泊施設となっていた家屋の再建資金を幕府が支給することになりました。幕府が須走村の復興に積極的に手を貸した背景には、須走村が甲斐と駿河を結ぶ交通の重要な場所であったためでした。 |
|||||||||
|
|||||||||
| ●参考文献:国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所発行 「富士山宝永噴火と土砂災害」 :御殿場市発行 「御殿場市史(通史編 上)」:小山町発行 「小山町史(第ニ巻)」 |
|||||||||