| ふじあざみ 第53号(1) |
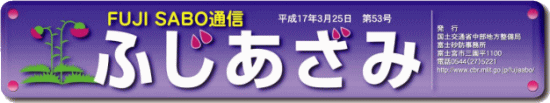 |
| ふじあざみ 第53号(1) |
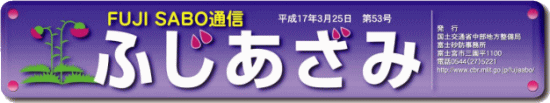 |
 |
||
| ■火山弾や火山灰が大量に噴出 宝永4年(西暦1707)11月23日、富士山南東側の中腹で大爆発が起こりました。これが宝永の大噴火です。噴火地点に近い駿東郡印野村(現在の御殿場市)の当時の様子を、地元に伝わる古文書は次のように伝えています。「午前8時ごろ、山麓に大きな地鳴りの音が響き、大地が揺れ動いたかと思うと突然、印野村の上手で大爆発があり、それと同時に火柱と噴煙がうずを巻きながら噴き上がった。しばらくすると大量の石や砂が降下し始め、あたり一面は暗闇のようになった。」 |
||
| ■広い範囲で甚大な被害 宝永の噴火は溶岩をほとんど流出せず、火山弾や火山灰を多量に噴出しました。特に麓の山村は大きな被害に見舞われ、登山口のひとつ須走村(現在の駿東郡小山町)では、全75戸数のうち埋没・倒壊した家38戸、焼けた家37戸と、ひとつの村全体が被災するという状況でした。火山灰は須走で2.6m、小山町で1m、御殿場で0.7mも堆積しました。 火山灰は小田原、大磯、戸塚、川崎、そして遠くは江戸にまでも降り、時の六代将軍徳川家宣の学問の師新井白石は、自伝の中で「江戸でも地震がひどく、雷のような音が響き、火山灰が地面をおおい、草も木も真っ白になっている。降灰のため日中でも暗く、灯をつけて進講(学問をおしえること)しなければならないほどだ」と書いています。 また、御殿場の七つの村の被災から約1年後の様子をまとめた資料によると、人口2,070人のうち、死者または他村へ避難した人728人、飢えのため救済を求めている人1,109人、運良く被災せずに自力で生活できる人233人という記録も残っています。 |
||
|
||
| ●参考文献:国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所発行「富士山の自然と砂防」 |
|
|
 1 〔2〕 〔3〕 〔4〕 |