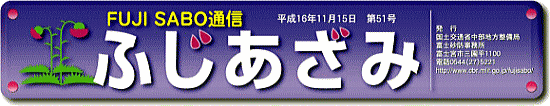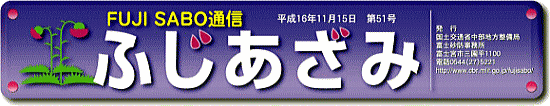|
| ▲富士川河川敷に広がる紅色のじゅうたん(桜えび干しの様子) |
|
 |
■宿場町として栄えた由比町
かつて東海道五十三次16番目の宿場町だった由比は、温暖な気候で海と山に囲まれ自然に恵まれた町です。浜石岳から富士山を望む景観は東海道随一と言われ、サッタ峠から見る富士山や駿河湾も絶景です。
そんな由比町の代表的な特産物が桜えび。由比の桜えびと言えば全国的にも最高の食材と珍重されています。 |
■特産「桜えび」の生態
桜えびは甲殻類(カニ・エビのなかま)サクラエビ科に属し、体の表面に160個余りの発光器を備えた体長4~5センチの一年生の小さなエビです。海中で生息している桜えびは、甲殻が美しい透明な桜色をしていて、名前の由来はここから来ています。
深海性の生物である桜えびは、昼間や月夜には、200~300メートルの深さの海中に生息しています。闇夜には20~30メートルの上層まで浮遊して厚い群れを作りますが、明け方にはまた、群れは散って下降し始めます。 |
| 桜えびは駿河湾だけでなく、駿河湾近海の遠州灘・相模湾・東京湾でも生息しているようですが、駿河湾に比べ、その数は極めて少ないそうです。桜えびは本来深海生物として知られているにも拘わらず、駿河湾内の桜えびは富士川・安倍川・大井川の河口付近沿岸の淡水の混入する河口付近におり、 かつ200メートル程度の比較的浅い水深に生息しており、このような例は極めて珍しいといわれています。 |
 |
| 写真提供:由比町役場企画観光課 |
|
■桜えび漁のはじまり
今では由比の名物として定着している桜えびですが、桜えび漁がはじまったのはそれほど昔のことではありません。100年ほど前に、ちょっとした偶然からはじまりました。当時アジ漁をしていた漁師の網の浮き樽がはずれて網が深く沈んでしまいました。ところが、それを引き上げると大量の桜えびが入っていたのです。この偶然によってどこまで網を入れれば桜えびがとれるかわかり、この「大発見」以来たちまち桜えび漁が発展していったということです。そして、一年中漁をおこなっていたようですが、現在は春漁と秋漁の2回に制限しています。春漁は3月下旬から6月上旬まで、また秋漁は10月下旬から12月下旬までの間で行われています。 |
■富士川河川敷の紅色のじゅうたん
富士川河川敷では、春と秋の漁期間中の早朝から桜えびの天日干し作業が行われます。その光景は、まるで紅色のじゅうたんを敷き詰めたような壮観です。この地方の風物詩にもなっている天日干しは天気の良い日に行われ、じゅうたんの向こうには美しい富士山も望むことができます。 |