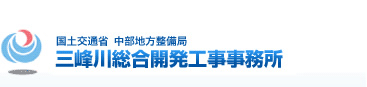|
1.構造線とは? |
断層の大規模なものを一般的に「構造線」とよびます。中央構造線は、ドイツのE・ナウマンにより命名
された世界第一級の大断層です。中央構造線は九州の八代から、徳島、伊勢をへて諏訪の南を通り、群馬県の下仁田、埼玉県の寄居付近でも確認された、連続し
て陸地を1000km以上追跡できる大断層です。
中央構造線とフォッサ・マグナ、糸魚川―静岡構造線とは全く別のものです。ナウマンは、本州中部の新潟県から静岡県を結ぶ大きな陥没地帯を見つけ、フォッ
サ・マグナと名付けました。フォッサ・マグナは、本州を胴まん中で真っ二つに切り離しています。糸魚川―静岡構造線はフォッサ・マグナの西縁の断層です。
糸魚川―静岡構造線は中央構造線よりずっと後にできた断層で、中央構造線を横切っています。

 |
2.なりたち |
「中央構造線」は日本列島ができる時代に形成された断層です。
日本列島周辺では、太平洋のプレ−トが、太平洋側の海溝でユ−ラシアプレ−トの下に沈み込んでいます。太平洋のプレ−トがユ−ラシアプレ−トの下に潜り
込むときに、太平洋の方からずれてきた岩石を「そぎ削る」ようにおいていったものを「付加体」と呼びます。
この付加体がアジア大陸の縁に沿って大きく横ずれしたものが中央構造線です。

 |
3.外帯と内帯 |
中央構造線をはさみ、太平洋側を外帯(西南日本外
帯)、日本海川側を内帯(西南日本内帯)といいます。内帯の伊那山地側には、花崗岩・高温低圧型の領家変成岩・外帯の南アルプス側には低温高圧型の三波川
結晶片岩と、できた場所が全く違う岩石が接しています。これらの岩石は深さにして20km、距離にして60km離れた場所でできた岩石です。

 |
4.溝口露頭部 |
南アルプスの中央構造線は、両変成帯が直接接して
おり、立派な露頭が観察できる重要な場所です。(溝口、北川、安康各露頭部)

中央構造線に関する詳しいお問い合わせは下記までお願いします。
| 長谷教育振興係 |
電話0265−98−2009 |
| 大鹿村中央構造線博物館 |
電話0265−39−2205 |
|