| 明治改修1 明治時代中期(約100年前) |
|
明治改修は、第一期工事から第四期工事完了まで、25年を費やして完成しました。 この工事でつくられた施設は、現在でも重要な働きをしています。 明治政府は河川や港湾の工事を行うため、オランダから10人の技師団を招きました。 当時オランダは世界でもっとも優れた水工事技術を持っていました。 その一人ヨハニス・デ・レイケは明治11年から木曽三川流域を山から海までじっくりと調べて回り、その結果をもとに改修計画を作成しました。 明治20年から25年間をかけて三川分流工事が行われ、木曽三川はほぼ現在の姿になりました。 この工事は近代的な河川改修工事の幕開けとされています。 デ・レイケが日本滞在中の30年間に残した功績は大きく、日本の河川・港湾事業の近代化に一生を捧げたと言えるでしょう。 |
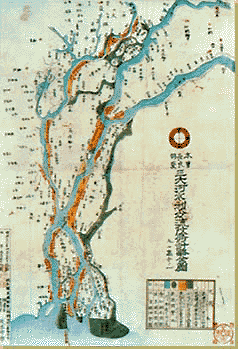 明治改修計画図 |
|
改修計画の主な内容
・木曽三川を完全分流する・佐屋川を廃川にする ・立田輪中に木曽川新川を通す ・長良川の派川、大槫川(おおぐれがわ)、中村川、中須川を締切る ・高須輪中に長良川新川を通す ・油島洗堰を完全に締切る ・船頭平に閘門を設ける ・木曽川、揖斐川の河口に導流堤を設ける |
 トップへ トップへ |
 明治改修2 明治改修2 |
|
国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表) |
copyright c 2013 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所. all rights reserved.