| KISSOこぼれネタ VOL.30 祖父江町特集号 |
| ●佐屋川の廃川と敷地払い下げ |
| 祖父江町は濃尾平野のほぼ中央、木曽川左岸に開けた町です。かつて町内を流れていた佐屋川用水は、江戸時代までは木曽川の第一派川。江戸初期に実施された改修工事により放水路的な河川をもつ人工河川となり、明治29年から着工された木曽三川下流改修(明治改修)により廃川に。用排水路の機能をもった佐屋川に代わり、佐屋川用水が整備されました。 |
|
佐屋川の廃川が竣工したのは明治34年。この工事の完成によって佐屋川敷地の払い下げ運動が盛り上がりましたが、その処分問題はなかなか結論が出ませんでした。 当時の記録によると、千余名の住民は破格に安い値で土地を買収され、木曽川改修の犠牲になっています。この補償的な意味もあって、当時の自治体首脳陣は無代に近い価格での払下げを要求しています。 その一方、祖父江町一帯の住民は、改修の進行と同時に払下げや土地の回復を期待して、佐屋川堤防にわら小屋や板囲いの仮住居を建てて生活しました。その間、半年毎の立退命令、時には「焼き払う」との威嚇手段もとられたといわれています。こうして払下げの陳情運動は盛り上がりをみせますが、その動向は以下のようです。
|
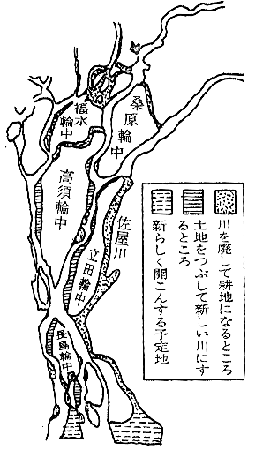
|
|
■参考文献 祖父江町史 昭和54年発行 |
| 印刷ミスと註釈漏れが招いた誤解 |
|
KISSO Vol.30の9ページに掲載したグラフ「伊勢湾台風時の名古屋港検潮記録」の潮位について「偏差値3.45mは3.55mではないか?」と疑問が寄せられましたので、下図のように訂正のお願いをしました。 気象台に確認したところ「偏差=実測潮位―天文(推算)潮位ですが、統計として扱う場合は1ヶ月単位の値を平均補正するなどの必要があり値が得られるのに時間がかかることから当時は速報値として公表された値(3.55m)が主になったようです。どちらも正しい値ですが、現在では統計値を使用しています。」とのことです。 また気象台が行う潮位観測は名古屋港検潮所の観測基準面(D.L)を0mとしてそこからの高さを標示しています。 これとは別に名古屋港工事基準面(N.P)があり、この0点高は前述の観測基準面(D.L)より50cm上にあります。 これを、東京湾平均海面(T.P. ±0)に換算すると名古屋港検潮所観測基準面の0点の高さは:T.P.−1.92m名古屋港工事基準面の0点の高さは :T.P.−1.42mとなります。 KISSO Vol.25の8ページのグラフは、名古屋港工事基準面(0点高:T.P.−1.42m)のグラフとなっています(T.P.の値も併記しています)。 このようにグラフなどの見方にも注意が必要ですが、立場によって記述や標示の違いから起きる誤解を避けるためにも、註釈や参考文献の記載が必要なことを改めて痛感しています。 |
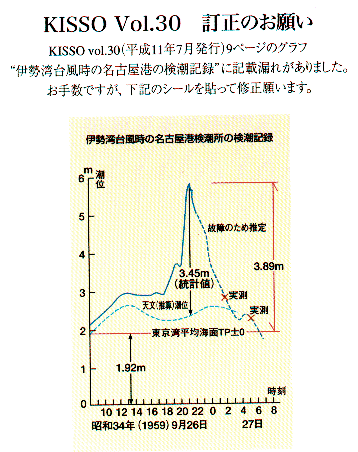
|
|
国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465 TEL:0594-24-5711(代表) FAX:0594-21-4061(代表) |
copyright c 2013 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所. all rights reserved.