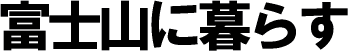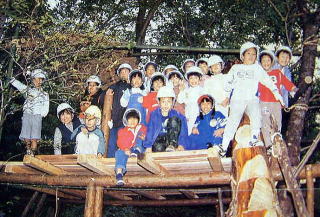| ふじあざみ 第47号(3) | ||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||
 |
||||||||
今回は富士山を身近に仰ぐ富士宮市で林業を営む遠藤誠さんにお話を伺いました。水泳やスキーなどのスポーツが大好きという遠藤さんですが、書の精神性にもひかれ書道もたしなむという静と動の両面性は、肉体的に過酷でもあり、静かで動じることのない森林の趣という林業に通ずるようにも思えます。 |
||||||||
| ■林業の国内自給率を高めることが大切 苗を植えてから資材としての木に生長するまで、最低でも50年の時が必要と言われます。そんな長い年月を要する林業のご苦労を伺いました。「木が資材として生長するには私は100年は必要だと思っています。現在の林業は安い外国産にたよりすぎていると同時に乱獲が進んで地球環境にも深刻な影響を与えています。本来森林資源は再生可能な状態を保ちながら活用すべきなのに、再生スピードが追い付かない過剰な伐採をしているのが現状です。」と、遠藤さんは現在の林業のあり方に疑問を投げかけます。では、どのように森林資源を活用していけばよいのでしょうか。「現在日本で消費される木材は約8割が輸入です。国産の木材が敬遠されることで日本では本来優良な木材が産出できる森林が荒れてしまっているんです。森林は生きています。木が健康に育つように人間が手助けしてやれば、はっきりと応えてくれます。太陽の光が地面にあたるよう、間伐などの陽光管理をすれば地面に草木が育ち、表土を保持し、土が肥え、木々はりっぱに育ちます。日本の林業がもっと自給力を付け、荒れた森林を整備し、国産で6割がまかなえれば世界の自然環境にも少なからず良い影響が期待できると思います。」 ■木や自然とのふれあいとマナー 遠藤さんはご自身の木や自然に対する想いから様々な活動を行っています。静岡県森林会議所のメンバーの中から、遠藤さんの想いに賛同された方々が集まり「森の熊さん」を発足させたのです。この団体の精神と活動について伺いました。「今の日本人のマナーの悪さは実に嘆かわしいものがあります。山に来て、山や自然と親しんでもらうことは大変良いことなんですが、山林に平気でゴミを捨てていく人がたくさんいます。それどころか、トラックいっぱいの廃棄物を捨てて行く心ない者もいます。山林は私有地ですが、昆虫を捕えたり山菜や薬草を自家用に採る位なら大目に見ております。しかし山菜や薬草を採るために木々を傷つけたり、地面に穴をあけたままにしたり生態系に影響が出るくらい根こそぎ採っていってしまったりする人も少なくありません。これは自然に対する慈愛の念が希薄になっているからではないかと思います。そういった意識やマナーを育てて行くためにはまず、自然に直接ふれ、親しんでもらうことが大切と考えました。普段あまり自然と触れあう機会の少ない子供達に、親御さんとともに自然を体験してもらうことを目的としています。」 |
||||||||
|
||||||||
■富士山の恩恵に感謝しお返しを 「富士山は子供のころからあたりまえのように見ていましたので、あまり意識はしていませんでした。しかし大人になるにつれ、その偉大さも自然に感じるようになりました。」遠藤さんは富士山頂は女性のように見えると言います。うっすらと雪が降った富士山頂はしわの入った年輩の女性に。真っ白く雪が積もった富士山頂は色白の若い女性のように見えるそうです。そんな母なる富士山は、周辺の山林の環境にとって大切な影響を与えています。富士山からのわき水や地下水が周辺の山林を育てているのです。遠藤さんは富士山も含めて、自然の恩恵に感謝の念と人が自然に対して何ができるか常に考えていると言います。「人は古来から自然の恩恵によって生かされてきました。私達はその恩恵を自然環境をこわさないように使う義務があります。林業を営む私達も、できるだけ環境に負荷をかけないような伐採を心がけています。そうやって自然からいただいた素材を大切に使い、使えなくなった時は自然に還すのです。プラスチックなどの人工の素材は自然に還すことができず、有害物質に変化したりします。人間は便利に慣れすぎて、それがかえって人間や地球に悪影響をおよぼしはじめています。今こそ人間は襟を正して地球に恩返しをする時なのではないでしょうか。」 ■木とのふれあいから自然の大切さを学ぶ 「森の熊さん」が企画、運営の手助けをする「ジュニアフォレスターズスクール」では、子供たちと親御さんたちとで様々な体験をすることができます。山歩きやわき水の探索、ツリーハウスを建てたり、間伐体験、火熾し体験などもあり、今年も3月20日・21日の2日間を予定しています。自分たちで伐採した木をつかって鳥の巣箱を作る企画もあるそうです。「火熾し体験などは、火が付いたときの子供たちのキラキラした嬉しそうな顔は感動するほどです。関心のある方はぜひお問い合わせください。」 |
||||||||
|
||||||||