|
|
|
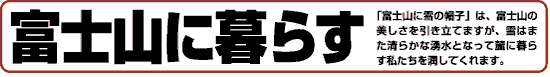 |
|
|
●初雪と終雪はどう決めるの?
真夏の7月や8月にも雪が降る富士山では、雪が降る時期と降らない時期の区別がつきません。このため、一日の平均気温が年間で最高となった日を境に、その日の後で最初に降った雪を「初雪」、その日の前で最後に降った雪を「終雪」としています。
●初雪と初冠雪のちがいって?
「初雪」とは山頂で観測された最初の雪のこと、「初冠雪」とは下界から見て山頂が雪で覆われた時のことをいいます。
今年の初雪は9月26日で、昨年より3日遅く、平年より12日遅い。また、初冠雪は10月6日で、昨年より9日、平年より5日遅い記録でした(富士山測候所御殿場基地事務所)。
●富士山頂に最も雪が多いのはいつ?
富士山は太平洋側にあります。日本海側が季節風の影響で雪が降り続いている頃、太平洋側は晴れの日が多く、富士山の積雪量はあまり増えません。
春になって季節風が弱まり、低気圧や前線が太平洋岸に雨を降らす時期になると、気温の低い山頂では雪になり、積雪も増えます。そして、山頂部では4月中旬に最も積雪量が多くなります。
●万年雪ってほんとうにあるの?
7月のお山開きの頃になっても山頂付近の登山道では1m余りの積雪があることがあります。夏の間にこれらの雪もほとんど溶けてしまいますが、富士宮口登山道の9合目付近「万年雪山荘」の裏では初雪の頃まで溶けきらず残ることがあります。
●富士山でも雪崩はあるの?
普通、雪崩には、積もった雪の表面だけが滑り落ちる「表層(ひょうそう)雪崩」と、全体が滑り落ちる「全層(ぜんそう)雪崩」があります。
富士山にはこの他に、「スラッシュ雪崩」という雪崩も起きます。スラッシュ(slush)は、「雪解け」「どろどろのどろ土」といった意味です。雨水を含みシャーベット状になった雪が地表を流れ出します。途中、多量の表土や岩塊、立木などを巻き込んで流れ落ち、大きな被害を起こすことがあります。山麓の人々はこれを「雪代(ゆきしろ)」と呼び、「春一番が吹くと、富士山に雪代が起こる」と古くから恐れてきました。
スラッシュ雪崩は、春だけでなく、冬のはじめにも、雪が途中から雨に変わった時などに発生します。最近では平成4年12月8日に、富士山西側斜面で初冬型のスラッシュ雪崩が広範囲に発生し、滑沢では雪崩が10km下流の栗の木沢まで達しました。しかし、到達点では栗の木沢砂防ダムが効果を発揮し、災害を未然に防ぐことができました。 |
|
|
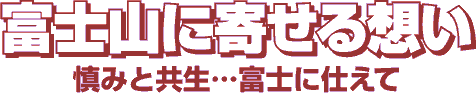 |
|
|
 |
|
 |
|
|
富士山本宮浅間大社 宮司
渡邉 新(わたなべしん) |
|
|
外面如菩薩・内面如夜叉(げめんぼさつのごとく・ないめんやしゃのごとし)。
富士山は日本一高い山というだけでなく、美しく伸びた山裾、雪をいただく神々しいまでの気高さ、四季折々の趣き。この峻厳にして雄大な山容は、真・善・美を兼ね備えた我が日本民族の、理想の姿と言えましょう。
冒頭の“げめん ぼさつのごとく”はまさにそのことを指すのであり、一方“ないめん やしゃのごとし”は、神という心を宿した生きものの、もう一つの姿を捉えた表現と考えられます。
神という命を宿した山体は、時として夜叉の如き怒りをあらわします。富士山がさかんに噴火を繰り返していた時代、古代の人々はその都度それは“神の怒り”とひたすらその怒りの鎮まることに祈りを捧げてきました。この地域の数々の発掘遺跡に、祈りを捧げたであろう遙拝(ようはい)施設をみるのも、その事情を物語っています。
日本民族は、元来自然は“静”と、時には荒々しい“動”を繰り返してはいるが、そこには必ず一つの調和・秩序があり、人間を超えた、ある崇(とうと)いものが含まれていると考え、自然の風景、山や河、巨石やこんもりとした杜など、それぞれに命が宿り、その背景には真理があると信じてきました。
自然と人間とは対立したもの、あるいは人間が征服すべき対象としてではなく、そのなかでともに生きる共生の念が、ごく自然に受け継がれてきました。それが日本人の宗教心意“上代からの心の道”=かむながらの道=神道と捉えられています。
アマゾン奥地の民族での逸話。河が氾濫(はんらん)して住処(すみか)を失ったとき、そこの古老が「われわれは、つつしみを忘れて神の領域に入り込んでしまった」と言い、その一言でそこから後退して居を構えたそうです。このことは現代に生きる我々に“自然との共生とはなにか”に深い示唆を与えています。
往古、当大社では山宮神事が行われていました。4月初(さる)の申(はつ)の日、本宮から富士山寄り6キロの地点にある山宮に於いて富士の神霊を迎え、里宮である本宮に神儀を納め、11月初申(はつさる)の日に里宮から山宮に神霊をお送りする神事です。この神事は大同元年(806)坂上田村麻呂が、浅間大神を山宮から本宮に遷座(せんざ)した盛儀を物語るとともに、神々の領域である富士山内から、人々の生活の場である里宮へと神社を遷(うつ)し、慎みの心を以て神にお仕え申し上げた経緯をも窺わせると言って良いでしょう。
共生の念は、自然界に在りとし有る万物に対する慎みの心によって培われ、神道として受け継がれてきた様子の一端を御紹介申し上げた次第です。 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|