| ふじあざみ 第38号(3) | |||
|
|
|||
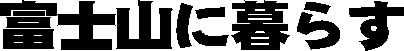 |
|||
人はもちろん、あらゆる生き物になくてはならない水。とりわけ富士山麓に暮らす人々にとって、富士山の白雪が溶け、長い年月をかけて山麓各地で湧き出す水は様々な恩恵をもたらしました。 |
|||
■湧水に秘められたロマン 富士山麓に住まう人々は、古来より富士山の地下水脈の恩恵を大きく受けてきました。富士山は五合目以上はほとんど森林がありません。この広大な富士山に降った雨や雪は、そのまま全て地下に浸透し、地下水脈を通ってふもとの平野部に達し、ところどころで自噴します。富士山の地下水は、なんと100年以上もかかってふもとの町に達するという説もあり、神秘的な富士のロマンをひときわかき立てられます。しかし、一方で70日でふもとに達するという説もあります。これは、富士山の降水量と、ふもとの湧水量の相関関係を調査したところ、富士山の降雨後、約70日後に湧水量が増加したという結果に基づいています。これは、大半の雨水は浅い層を通ってふもとに達するためです。地下の深部での圧力を受けて自噴する湧水は100年かかる水脈を通っているとしても不思議ではないと言われています。 |
|||
|
|||
|
|||
| ■車イスで富士山頂登山? 僕は、富士宮で診療所をしています。一応外科医ですが、多種の病を診療しています。そんな僕が、ある小学校で集団予防接種をやっている時、後ろから看護婦さんが「先生、富士山登ったことあります?」と話しかけてきたのが事の始まりでした。話を聞いてみると、障害者を富士山の山頂に登山させる計画が有るとの事で、それに医者が同行すると高山病などの時心強い、との事でした。 その後何日かして、会合に呼ばれました。この頃はどのように障害者に登山してもらうのか、いろいろな意見を出し合っていました。何回かの会合の時に役職を決める事となり、僕は「代表者」にならされてしまいました。 障害者の富士山頂登山の話は徐々に進んで行きましたが、僕には一つ問題が有りました。それは、僕自身が五合目までしか行った事が無かったのです。そこで、僕は息子達と富士登山に行きました。一度目は「元祖七合目」を少し過ぎたところで息子達が高山病になり、引き返して来ました。 二度目の登山では、長男と剣ヶ峰まで行きました。これらの登山で、高山病や歩くペースを考え、障害者が一般登山道を使って山頂に行くのは無理だと確信しました。「障害者だから……」と言わせないように、一般登山道を使いたかったのですが、ブルドーザーの通る「ブル道」を使用する事を皆様にもご理解いただきたく思います。登山に使う車イスは、一般的な車イスのタイヤを、一輪車(いわゆる“ネコ”)のものに換えた三輪の車イスです。これに、ロープを掛けて、それを引っぱって登山する事も徐々に決まっていきました。ここに達するまで試行錯誤を重ねました。幾度の練習登山をして、三輪の車イスを引っぱり新七合目に行った時には、天気が良ければ絶対に頂上まで行ける事を確信したのです。 ■車イスで登頂す 一回目は、21世紀元年8月25~26日。みんなで馬車馬のように車イスを引っぱり九合目で宿泊。翌日7時00分登頂!車イスから降り寝っころがった障害者の「ありがとう」の笑顔が印象的でした。 二回目は、平成14年8月31日~9月1日。昨年同様に九合目で一泊し、翌日7時15分登頂!幾つかの涙と、天気が良すぎたための、ブル道の火山灰の埃が印象的でした。 障害者と2回登山しましたが、僕は思う所があります。診療所を臨時休診にして山登りしていて良いのだろうか?町を掃除したり、五合目以下の不法廃棄物の除去をする方が一般的なボランティアじゃないのか?と。この富士登山のボランティアの目的は何なのだろうか?障害者が車イスに乗り、それを引っぱってもらって富士山の頂上に行くことにどんな意味があるのだろうか?僕もきちんと答える事が出来ません。 でも、富士山に登る権利の無い人はいない。誰でもが登っていい日本一高い山。障害者が「登ってみたい」と言えば、それに協力する人がいる。障害者も車イスにただ乗っているわけではない。薄い酸素、ガタガタと揺れる車イスなどに耐え、努力している。そして登頂し山下を見下ろすと、今までとは異なる世界が見えてくるかな? |
|||
|
|||
|
■関 泰(せき やすし)氏 プロフィール 昭和31年10月23日神奈川県に生まれる。平成2年富士宮市に移住。平成9年診療所を開院。オートバイでのツーリングを趣味とし、オートバイで往診に行くことも…。いつも心に夢を持ち続ける医師であり、4人の息子さんたちの良きお父さんでもある。 |



