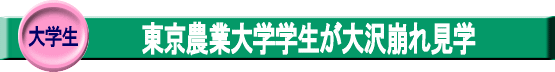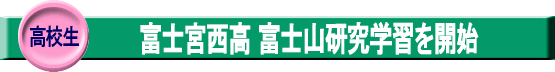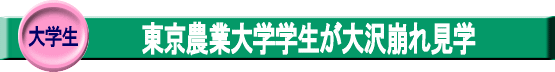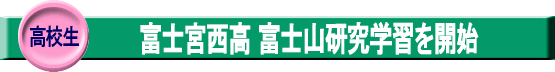| ふじあざみ 第34号(8) |
|
 |
|
 |
教職員夏期研修会 「富士山三昧(ざんまい)」 が8月6日・7日で富士常葉大学を中心に行われ、屋外体験研修では、大沢扇状地施設と大沢崩れ踏査の2グループが訪れました。扇状地班は、フジアザミの説明を受けたあと圃場で育苗した苗をプランターへ移植する作業にも取り組みました。
翌、7日に行われたシンポジウム 「富士山を世界遺産にしよう」
では、花岡所長が 「富士山麓の地域と自然を保全する―富士砂防の30年と新たな展開」
と題し、登山家野口健氏とともに約600人に基調講演を行いました。 |
 |
 |
| ▲大沢扇状地班 |
▲砂防施設見学班 フジアザミ苗移植 |
|
| 重川希志依助教授の感想 フジアザミの名前を聞いたことはありましたが、実際に見て触れるのは初めて。見かけはあまり強そうに見えないのにしっかり根を張り、地面を安定させる力にビックリしました。 |
|
|
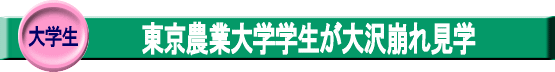 |
| 東京農業大学 治水緑化工学研究室 福永健司講師、長佐智子幹事ほか、26名が学生実習として富士砂防管内に来訪され、御中道を源頭部調査工事現場まで踏査し、大沢崩れとヘリコプター資材運搬を見学しました。 |
 |
| 源頭部の調査工事現場までおりて視察 (9月20日) |
|
|
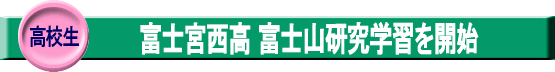 |
 |
 |
県立富士宮西高校では、富士山研究の学習として、富士山の地質、民族、植生、砂防の学習を実施しています。富士宮山岳会副会長でもある工藤誠志教諭から、富士山大沢崩れと砂防対策について、出前講師の依頼があり、花岡所長が講演し、現場見学と植栽体験を実施しました。
富士宮市内小中学校で取り組んでいる富士山学習には従来から積極的に協力していますが、高校としては初めての受け入れとなりました。 |
| ▲スライドとビデオを駆使した講義 (9月13日) |
▲リサイクルポットで植樹をする生徒たち (9月20日) |
|