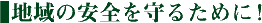 |
 |
富士山大沢崩れの崩壊した土砂は、降雨や雪代(ゆきしろ)により土石流となって人家等を直撃し、さらに河道に流出した土砂は潤井川をも氾濫させてきました。このため標高600~900m付近の扇状地に延長約4km、最大幅1.5kmに及ぶ我が国最大級の土砂を堆積させる砂防施設大沢遊砂地を設置しました。この遊砂地がおおむね完成した後に発生した土石流はことごとく捕捉し、下流域への被害を未然に防ぐことができました。また、堆積した土砂は施設の機能を発揮させるために除石を行い、その土砂は土地改良、道路建設、海岸事業等地域づくりに有効活用しています。
主な施設としては、
渓岸工延長1,200m、床固工 7基 砂防樹林帯74ha
流路工延長5,700m
|
 |
| 昭和44年頃の大沢扇状地の状況 |
 |
| 昭和48年3月 改築後の大沢第7床固左岸導流堤
|
|
 |
| 昭和51年9月 大沢第5床固落差工 |
 |
| 渓岸工 |
 |
| 樹林帯補強工 |
 |
| 潤井川流路工 |
|