| 2.1.1 流域と三河湾(図−2.1.1) |
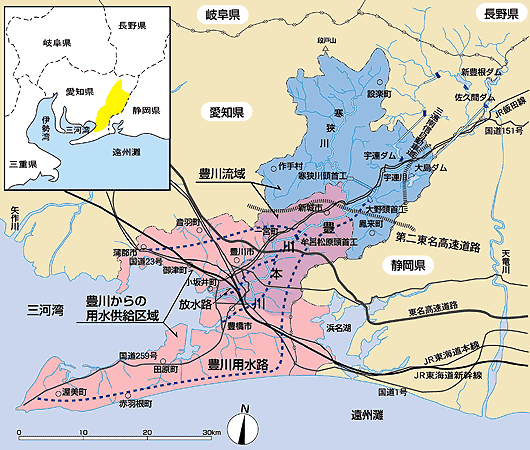 図-2.1.1
豊川流域の概要 図-2.1.1
豊川流域の概要 |
| 豊川の流域は愛知県東部に位置し、流域面積は724km2(愛知県全体の面積に占める割合は約14%)。東三河工業整備特別地域、東三河地方拠点都市地域などを擁していて、第2東名高速道路や三遠南信自動車道等の交通ネットワークの整備に伴い、今後一層の発展が期待される地域でもある。流域の中心を流れる豊川の水は、豊川本川、放水路、豊川用水などを経由して三河湾に流れ込んでいる。 |
|
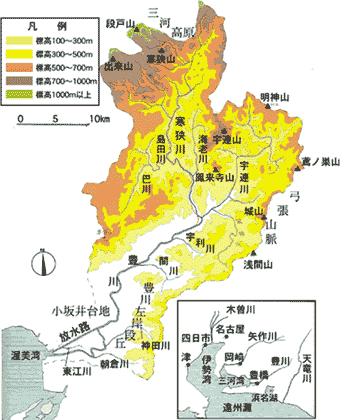 |
2.1.2 流域の地形(図−2.1.2)
豊川流域は、北西部に広がる起伏の少ない三河高原(標高600-700m)と東側に連なる急峻な弓張山脈(標高400-600m)に挟まれた地形を基盤にして形成され、下流域の豊橋平野は東西両山地の間に形成された三角州、扇状地の平地であり、山地の麓には低い小坂井台地と豊川左岸段丘があり、その間がもともと河川氾濫原であった豊川低地になっている。 |
| 図-2.1.2 豊川流域の地形 |
|
|
|
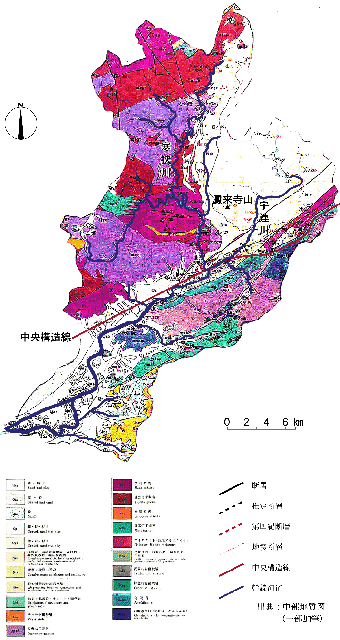 |
2.1.3 流域の地質(図−2.1.3)
豊川流域は中古生層(6500万年前以前に形成された)を基盤とし、主として1600万年前以降の火山活動と、それに続く海退現象、さらに第四紀の隆起によってできあがった陸地から形成されている。宇連川から豊川本川中下流部の川筋沿いには「中央構造線」と呼ばれる活断層が走っており、古い運動(中生代白亜紀〜)が現在の豊川流域の地形の大枠を決め、鳳来寺山の火山活動以降の新しい断層運動(〜第四紀)が、寒狭川と宇連川を始めとする主要な川筋を決定した。西方に位置する寒狭川流域は、地下深所から隆起した花崗岩類や片麻岩類が多くを占め、風化しやすいために雨水は地下に浸透しやすく、地表からの土砂流出が多いのに対して、東方に位置する宇連川流域は、硬い火山岩類が露出し雨水が地下にしみ込みにくいために水持ちが悪く、土砂流出は少ない。
|
| 図-2.1.3 豊川流域の地質 |
|
|
|
2.1.4 流域の植生
流域の北・中部山地には、スギ・ヒノキを主とした常緑針葉樹の人工林が広く分布しており、その北東部を中心としてブナ・ミズナラなどの広葉樹天然林が点在している。南部の台地上にはアカマツ、クロマツ、および広葉樹林が分布している。 |
|
| 2.1.5 流域の市町村と人口 |
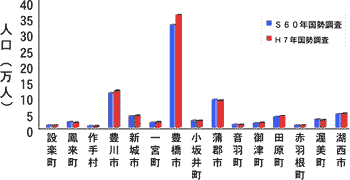 |
| 図-2.1.4 豊川流域の市町村人口 |
| 豊川流域は、豊橋市をはじめとする3市4町2村からなる。豊川用水を通しての利水地域を含めると5市9町2村にまたがり、その総人口は約78万人(平成7年)である。上流域(設楽町、鳳来町、作手村)に約2万人、中流域(豊川市、新城市、一宮町)に約17万人、下流域(豊橋市、小坂井町)に約37万人、利水地域(蒲郡市、音羽町、御津町、田原町、赤羽根町、渥美町、静岡県湖西市)に約21万人が、それぞれ生活している。昭和60年〜平成7年における人口遷移は上流域で減少傾向、下流域で増加傾向を、それぞれ示している。(津具村は豊川上流域の一部を構成しているが、山地部のみのため、当流域の人口・産業には集計していない) |
|
| 2.1.6 流域の産業 |
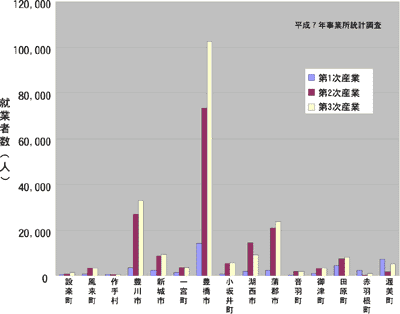 |
| 図-2.1.5 流域の産業構成(就業者数) |
| 豊川流域を中心の主要産業は、生産性の高い農業(メロン、電照菊など)や、輸送機器産業(自動車等)、および食料品産業(ゼリー、ちくわなど)で、生産額は、農業粗生産額約1,763億円(平成7年愛知県農林水産統計年報)、製造品出荷額約36,018億円の規模である(平成7年工業統計表)。このような産業形態を反映して第1次および2次産業における就業者数が全就業者数にしめる割合(第1次10.4%、第2次40.4%)は、全国平均(第1次6.0%、第2次31.8%)より高く、逆に第3次産業では(51.9%)、全国平均(62.2%)より低くなっている。 |
|
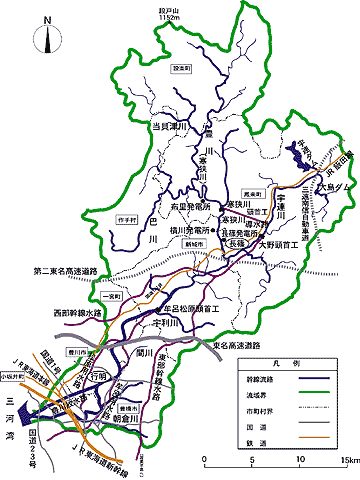 |
2.1.7 流域の河道網と主要河川構造物
豊川は、その源を愛知県北設楽郡設楽町の段戸山(標高1,152m)に発し、山間渓谷を流れて当貝津川、巴川等の支川を合わせながら南下し、南設楽郡鳳来町長篠地先で宇連川と合流する。その後、豊橋平野に入って宇利川、間川等の支川を合わせ、豊川市行明で豊川放水路を分派し、豊橋市内河川である神田川、朝倉川等を集めた後に三河湾へと注いでいる。幹川流路延長約77kmの一級河川である。
主要な河川構造物としては、1)豊川用水および豊川総合用水のための宇連ダム、大島ダム、寒狭川、大野、および牟呂松原の各頭首工、2)布里、横川、長篠の各発電用取水堰、3)石田地点下流部河道における河川堤防、放水路、および堤防前面に散在する水制工などをあげることができる。 |
| 図-2.1.6 河道網と河川施設の分布図 |
|
|
|
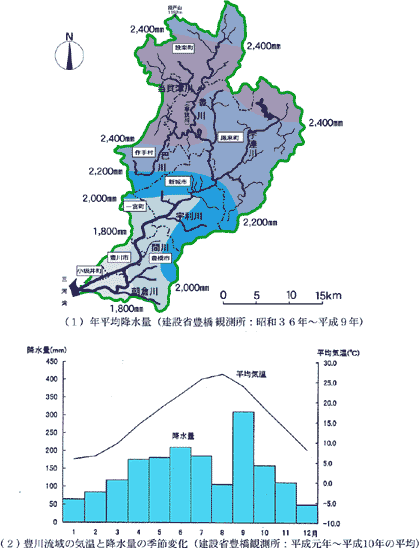 |
2.1.8 流域の降雨量
流域内の年間降水量は、昭和36年から平成9年の平均で、上流域で約2,400mm、中流域約2,200mm、下流域で約1,800mmであり、全国レベルで見れば多雨地域に属する。季節的には、夏の梅雨期および夏から秋にかけての台風期に降雨が集中している。 |
| 図-2.1.7 降水量の季節変化図 |
|
|
|

