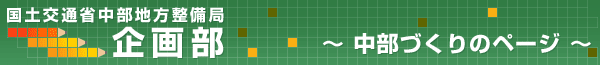 |
今回は前回と同数の68件の応募があった。割合的には相変わらず住民部門の応募が多く、地域住民自身が地域づくりの重要な担い手となっていることを改めて実感し心強く感じた。しかし内容的には今回は企業・学校部門と行政部門に光るものが多かった。
住民部門への応募は今回も多く、多様な活動を実施しておられることに敬意を表する。しかし、厳正な審査の結果、この部門では2年連続で大賞該当者がなかった。本表彰制度の趣旨をご理解の上、それに沿った活動内容を強調して申請頂きたいと思う。
今日、公共的な分野に対する多様な主体(住民、NPOなどの民間組織、企業等)の連携・協働が一層期待されている。国土マネジメントの分野でも、民間人の知恵や郷土愛が良質な社会基盤形成に果たす役割は大きい。受賞団体の熱意とご努力に敬意を表わし、今後のご発展と進化に期待を寄せるものである。
継続可能で発展性のある活動を期待したが、そういった見地からは、もの足りなさを感じた。各部門共通のキーワードは「協働」であろう。こういった協働活動は、今後、確実に増えていくので、とりわけ、住民部門では、行政とのより密接な連携も必要だと思う。
ことしは全部の案件について、現地調査に赴けなかったのだが、住民部門の不振は否定できない。資金と人材に乏しいのは恥じることではないが、小規模でも正しい知識と明確な目標を持つ着実な活動が生まれてほしい。
各地の活動を現地で見せていただいた。それぞれに地域の素材を活かし、地域に影響力を持つすばらしい活動だった。住民、企業・学校、行政の3つの部門に分かれているが、表には出なくても三者が協力体制をとっていることが大きな活動につながっていると感じた。しかし過去の大賞・優秀賞の例を見ても、ごくわずかな人数で始めたものが、長い年数をかけて広がりを築いていったものが多かった。無理なく継続できる楽しい活動を今後も期待する。