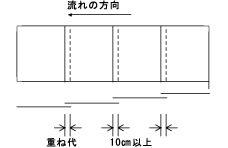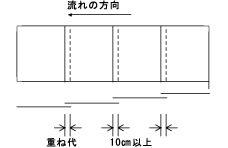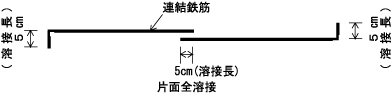| |
1. |
吸出し防止シートは、表1-1(1)、表1-1(2)の規格値を満足した「河川護岸用吸出し防止シート評価書」(建設大臣認可)を有しているシートとする。なお、上記評価書を有していない製品についても「公的機関による性能証明書」を有しているシートについては、使用できるものとする。 |
| |
|
|
| |
|
表1-1(1) 吸出し防止シートの規格値
| 項目 |
規格 |
性能確認 |
| 厚さ |
10mm以上 |
評価書及び公的機関の性能証明書による。 |
| 開孔径 |
0.2mm以下 |
引張り強度
(設計条件により選択) |
0.2,0.5,1.0tf/m以上 |
化学的安定性
(強度保持率) |
70%以上 |
| 耐侯性(強度保持率) |
70%以上 |
| 注)引張り強度0.2tf/mは、「化学的安定性及び耐候性」の規格値の規定は行わない。 |
|
| |
|
|
| |
|
表1-1(2)吸出し防止シートの品質及び規格
| 試験項目 |
内容 |
単位 |
規格値 |
試験方法 |
| 密度 |
|
g/cm2 |
0.10以上 |
JIS L 3204 |
| 圧縮率 |
|
% |
15以下 |
JIS L 3204 |
| 引張強さ |
|
tf/m |
0.2,0.5,1.0以上 |
JIS L 3204 |
| 伸び率 |
|
% |
50以上 |
JIS L 3204 |
| 耐薬品性 |
不溶解分 |
% |
90以上 |
JIS L 3204 |
透水係数
|
|
cm/s
|
0.01以上 |
JIS L 3204 |
| 注)引張強さについては、設計図書によるものとする。 |
|
| |
|
|
| |
2. |
かごマットの構造仕様については、図面及び表1-2によるものとする。 |
| |
|
|
| |
|
表1-2 かごマットの構造仕様
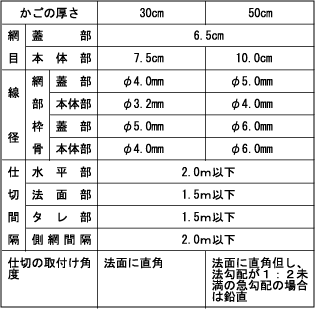 |
| |
|
|
| |
3. |
かごマットの鉄線の品質規格等は表1-3(1)、表1-3(2)に適合するものとする。
また、蓋鋼部においては、粗面鉄線を使用するものとする。 |
| |
|
|
| |
|
表1-3(1) 線材の品質及び規格 →クリックすると表がご覧いただけます。 |
| |
|
|
| |
|
表1-3(2) 合成樹脂被覆(ポリエチレン系樹脂被覆)の品質及び規格
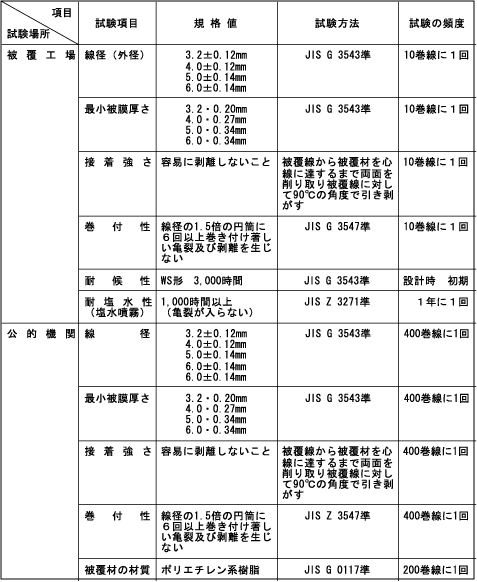
(1巻線とは、被覆工事における製造単位をいい約500㎏とする)
注)被覆鉄線の製造法としては「押出成形法」とし、JISG3543の規定を準用する。 |
|
| |
|
|
| |
4. |
請負者は、かごマットの製品について、底網、蓋網、側網及び仕切網毎に、網線に使用した線材のめっき工場名及びめっき線製造年月日を記載した表示標を付けなければならない。 |
| |
5. |
請負者は、かごマットは、側網、仕切網をあらかじめ工場で底網に結束しなければならない。ただし、特殊部でこれにより難い場合は設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 |
| |
6. |
請負者は、かごマットの線材は、現地において、施工面積2,000㎡毎に監督職員が指示する荷札表示された線材について、工場での品質試験結果を提出しなければない。
さらに、現地に納入される製品の荷札番号に近い線材の公的機関における成績証明書を提出しなければならない。 |
| |
7. |
請負者は、枠線、骨線、コイル線について、工事単位毎に私的、公的機関における品質試験結果を提出しなければならない。 |
| |
8. |
請負者は、生産表示と品質試験内容について、別途立ち入り等による検査を行う場合があるため、監督職員に協力しなければならない。 |