| |
1. |
レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査(JISA5308)は、請負者が自らもしくは公的機関又は生コン工業組合等の試験機関で行うものとする。現場付近に公的機関等の試験場が無い場合又は公的機関等で試験を行う日が休日となる場合等、やむを得ず生産者等に検査のための試験を代行させる場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得るものとする。 |
| |
2. |
JIS認定工場にて生産する日当り打設量が小規模(配合別50m3/日未満)となるレディーミクストコンクリートを使用する場合の品質管理については、「日当り打設量が小規模となるレディーミクストコンクリートの品質管理基準(案)」に基づくものとする。 |
| |
3. |
請負者は、レディーミクストコンクリート圧縮強度試験については、材令7日及び材令28日についても行うものとし、材令7日強度から材令28日強度の判定にあたって強度上疑義がある場合には、品質が確認されるまで一時当該レディーミクストコンクリートの使用を中止しなければならない。 |
| |
4. |
普通ポルトランドセメント使用の材令7日強度より材令28日強度の判定にあたっては、JIS認定工場の推定式を参考とするものとする。なお、これによりがたい場合は、次式を参考にするものとする。
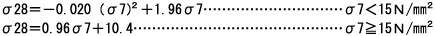 |
| |
5. |
高炉セメント使用の材令7日強度より材令28日強度の判定にあたっては、JIS認定工場の推定式を参考とするものとする。なお、これによりがたい場合は、次式を参考にするものとする。
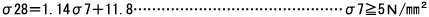 |
| |
6. |
請負者は、砂防ダム工事において、現場練りコンクリートを使用する場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 |
| |
7. |
一般土木工事に使用するコンクリートの配合は、設計図書に示す場合を除き表5-1とする。 |
| |
|
|
| |
|
表5-1 配合表 →クリックしてご覧ください。
|
| |
|
|
| |
|
| (1) |
請負者は、コンクリート用高炉スラグ粗骨材(JISA5011)を使用する場合には、高炉スラグ砕石コンクリート設計施工指針案(土木学会)によるものとし、高炉スラグ粗骨材の分類はBとしなければならない。 |
| (2) |
請負者は、表5-1の配合表において、高炉セメントにより難い場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 |
|
| |
8. |
コンクリート2次製品の目地・据付等に使用するモルタル配合は、設計図書に明示した場合を除きセメントと砂の重量比1:3程度とする。 |
| |
9. |
レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査におけるコンクリートの供試体の確認方法は、下記の方法のどちらかにより実施しなければならない。
| (1) |
A法
| ① |
コンクリートを供試体枠に投入したときの写真撮影時に、型枠外面に供試体を特定できる番号・記号等を記載し撮影すること。 |
| ② |
供試体頭部硬化後、型枠外面に記載した番号、記号等と同一のものを頭部にも記載し、2ヶ所の番号、記号等が1枚の写真でよくわかるように撮影すること。ただし、写真は型枠脱型前に行うこと。 |
| ③ |
写真については、ネガにて保存するものとし、工事アルバムには適宜掲載するものとする。 |
|
| (2) |
B法
| ① |
供試体型枠の内側にグリース塗布後、所定の事項を記入した供試体確認版(QC版)の表を上にして型枠側部におき、コンクリートを打設すること。 |
| ② |
強度試験前に供試体に転写した部分を写真に撮り資料採取時のものと同一のものか確認すること。 |
|
|