P地点:避難場所体育館の惨状
体育館に戻って、皆と話をしたり家族の面倒をみたりして時間が過ぎていきました。おそらく20時頃だったと思います。「ゴウー」という音がして、さっき見てきた地点の突然の決壊(トッピング)であることを知りました。後から下流の塩倉部落の人々に聞いたことですが、3mもの高さで土石流が流れてきたそうです。そのために、寺沢川は岩盤の露出した、まるで樋状の流路となってしまいました。
それから皆が、体育館の安全性について議論し始めました。年をとった先生が谷を見張ることを提案しました。この体育館は、グランド側に生徒の玄関があり、その2階が青年学級の2教室となっており、反対側には、シャッターで仕切った音楽室がある複合体育館でした。音楽室の山側には小さな谷があって、かつて土石流が発生したらしく、小さな谷止工が施工されていることに気がつきました。もし、この谷(Q地点)に土石流が走れば、避難している体育館が危なくなります。そこで、この谷を見張ることにしました。見張る内容は、濁流がひときわ濃くなって、少なくなったり止まったときに大声で呼ぶということにしました。見張り始めて20〜30分もした頃でしょうか、見張りにあたっていた先生が大声で「水が止まったぞ−‥‥‥」と叫びました。皆は玄関の方向に走って逃げました。寝とぼけていた誰かが逆の方向に走りました。私は「こっちだ」と叫んで皆を玄関に誘導しました。見張りの先生が体育館の中央まで走ったとき、「ドカーン」という音がして土石流が音楽室の壁に当たり、窓ガラスが飛び散りました(写真-2の左の明るい部分が土石流の入ってきたドア)。そして、ものすごい速さで泥水が柔道の畳をあっと言う間に浮かしてしまいました。体育館のステージやその下には、畑のコンニャクの芋がころがっており、サワガニがゆっくりと這っていました。こんな光景は、驚きながらではありますが、意外とロマンチックな瞬間でもありました。泥だらけの体育館(写真-3)、体育館のフローリングは波立って、生徒の清掃も痛々しいものでした(写真-4)。
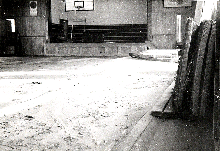 写真-1 土石流が侵入しフローリングが盛り上がっている。 畳は避難していた時敷いていたもの(1) |
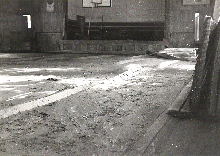 写真-2 土石流が侵入しフローリングが盛り上がっている。 畳は避難していた時敷いていたもの(2) |
|
 写真-3 西のドアーから東側を見た体育館のフローリング |
 写真-4 校舎が浮いて使用不能のため体育館を教室にするための清掃(災害1週間後に生徒を招集) |