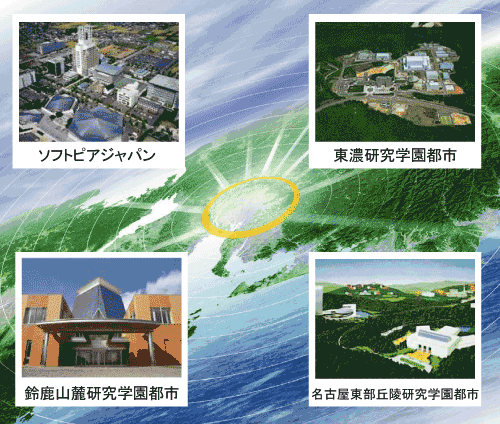 |
| 新たな交流が生まれる環状整備 |
| |
中部では、東海環状自動車道の整備により、日本初の環状型都市圏が形成されつつあります。
環状道路などの整備によって、日常の生活圏を拡大し、多様な生活者のニーズや経済活動に対応できる、広域交流圏の形成をめざします。 |
| ■分散した中部の拠点都市 |
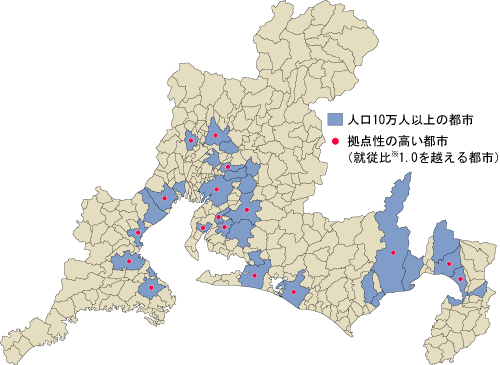 |
| |
| アウトカム目標 |
●環伊勢湾および東海環状都市間の交流基盤を築きます
●環伊勢湾および東海環状都市間の経済・文化活動の交流拡大を図ります |
 |
| 新たな交流が生まれる環状整備 |
| |
| アウトカム指標の例 |
| ●東海環状自動車道の着実な整備による交流の拡大 |
| |
| POINT |
| 中部における中核都市は比較的自立性の高い独自の圏域を形成していることから、住宅需要の分散により職住近接な持ち家を取得できるなど、仕事面と生活面のバランスが良いとされています。その半面、中部としてのまとまりに欠けるとともに、日常的な圏域外交流※が少ないことも特徴です。拠点都市間の連携を強化し、日常の生活圏域を拡大することによって、経済・文化活動の交流を活発にすることが重要だと考えています。 |
| |
| 語句の解説(※印がついた言葉) |
| 【東海環状都市圏(東海環状都市・環状型都市圏・東海環状自動車道・環状道路)】 |
| 東海環状自動車道とは、名古屋市の周辺30〜40km圏に位置する愛知・岐阜・三重の3県の豊田、瀬戸、岐阜、大垣、四日市などの諸都市を環状に連結する道路。これらの諸都市を東海環状都市と呼び、相互に連携を強化することによって、新たな交流の創出や、効率的に都市機能を分担しあえる環状型都市圏の形成を目指しています。 |
| 【環伊勢湾広域交流圏(広域交流圏・環伊勢湾)】 |
| 環伊勢湾地域とは、伊勢湾を囲む地域と熊野灘に面する地域、駿河湾・遠州灘に面する地域、中部山岳地帯に広がる地域からなり、これらの地域間で広域的な交流が行われる圏域の形成を目指しています。 |
| 【就従比】 |
ある地域に、実際に寝起きしている人口と、昼間に仕事や学校に通うために増えたり減ったりした人口の比率。
就従比が1.0を越える場合には、昼間の人口の方が夜間の人口より多いことを示し、職場や学校が多く存在する「拠点性の高い地域」と判断することが出来ます。 |
| 【圏域外交流】 |
| 余暇などに行われる、日常の生活圏を越えた観光やボランティアなどの交流です。 |

