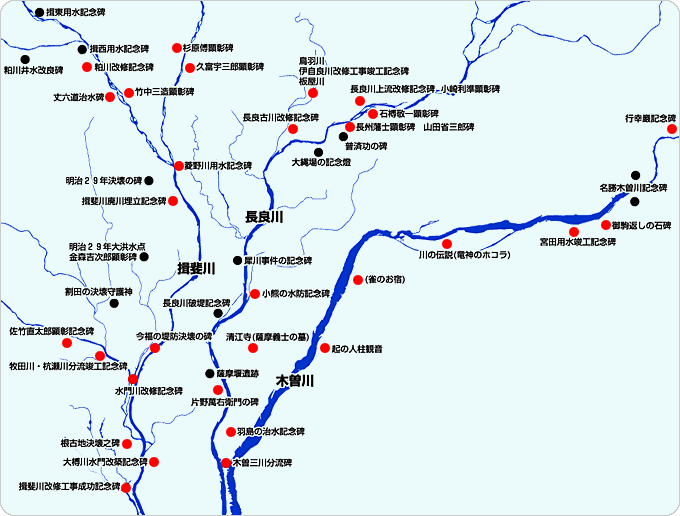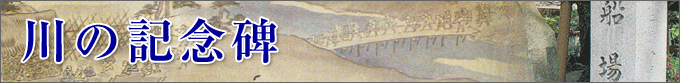幾度かの洪水を繰り返して、木曽川が現在の流れに落ち着いたのは、約400年前の天正14年(1586)の洪水の時でした。その22年後には『御囲堤』が築かれましたが、対岸の美農側は、本格的な堤防の築造が許されなかったため、いぜんとして洪水の被害にあげいていました。
この地に集まる人々が増え、治水の必要性が高まって、はじめて本格的に取り組まれた工事が宝暦4年(1754)の『宝暦治水』でした。それから150年後、海外の進んだ技術を採り入れた大規模な治水事業『明治改修』が完成したのは明治45年(1912)のことです。
木曽三川の水を得て発展した濃尾の人々は、その後も絶え間なく治水・利水の努力を重ねています。
三川の周辺に散らばる河川改修に関する碑は、こうした先人の偉大な努力と、自然への限り無い憧憬を永く後世へ伝えていくことでしょう。
みなさまも一度ごらんになってはいかがですか?
以下の地図よりご覧になりたい●ポイントをクリックしてください。詳細がご覧になれます。