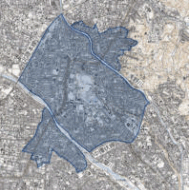| ◆行政の取り組み編 |
| 提言1.「街なか」居住者を増やそう | |||
| ① | まちの「暮らす」魅力を高めよう | ||
| ② | 様々な機能を「街なか」に集約しよう | ||
| ◇ | コミュニティビジネスも活かしつつ行政、福祉、商業、医療、教育等の機能を集約しよう | ||
| コミュニティビジネス ・地域住民やNPO等がその地域ニーズに対し、住民自らが取り組む地域密着型の小規模な事業活動。 ・生活支援(子育て、介護など)、環境対策(リサイクルなど)、地域振興(商店街活性化など)等、行政や一般企業では 対応できないサービスを提供。 ・主な担い手は、NPO、住民主体のベンチャー企業、企業組合など。 |
|||
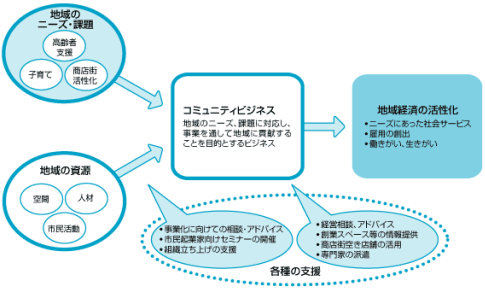 【出典:横浜市HP】 |
|||
| 【事例:中心市街地への商業施設等立地優遇税制(静岡県浜松市)】 | |||
| ③ | 郊外開発を抑制しよう | ||
| ◇ | 都市計画制度等の土地利用制度を有効に活用し郊外開発を抑制しよう | ||
| ◇ | 場合によっては税制度まで踏み込んだ抑制も検討しよう | ||
| 【事例.岐阜県高山市潤いのあるまちづくり条例】 | |||
| ④ | 「街なか」人口定着を図る誘導政策を積極的に講じよう | ||
| ◇ | 「街なか」居住を動機づける、選択的、集中的な支援措置を講じよう | ||
| 右図:石川県金沢市「まちなか区域」 | |||
|
|||
| 提言2.住民がお互いにコミュニケーションを深める仕掛けをしよう | |
| ① | まちづくりの中核となる人材を啓蒙・育成しよう |
| ◇ | 大学等と連携した「7人の侍」を意識した講座や講習会を積極的に実施しよう |
| 【事例.静岡県まちづくりリーダー養成講座】 | |
| ② | 住民が問題意識を持ってコミュニケーションを図る機会を提供しよう |
| ◇ | 街路の美化や見所マップの作成などの身近なテーマ・機会を提供し、住民を巻き込もう |
| ◇ | 「小さな成功体験」の積み重ねを意識し、活動の継続性の確保に努めよう |
| ③ | 住民相互の話し合いを促す外部人材を提供しよう |
| ◇ | 上述のような機会の提供にあわせたアドバイザーなどの派遣に努めよう |
| ◇ | 「専門家」のみならず①の人材を含めたテーマなどに応じた「人」を派遣しよう |
| 提言3.学校と連携しよう | |||
| ① | 大学等の高等教育機関とお友達になろう | ||
| ◇ | 行政の側から一歩踏み込んで学生を含めた学校との日常的交流を強化しよう | ||
| 右図:N/N(エヌ・ツー)(愛知県西春町) | |||
|
|||
| ② | 学生などの人的資源をまちづくりに活用しよう | ||
| ◇ | まちづくり協議会、イベントや空き店舗の模擬経営等へ幅広く参画してもらおう | ||
| ◇ | 学校まちづくりへ積極的に参画してもらうとともに、その促進方策を検討しよう | ||
| 右図:チャレンジ・アンド・ラン(愛知県豊橋市) | |||
・企画立案から運営に至るまで学生の自主性に任せた取り組みを行っている。 |
|||
| ③ | 総合学習などのテーマとして「まちづくり」を売り込もう | ||
| ◇ | 総合学習や社会科学習などへ「まちづくり教育」を積極的に売り込もう | ||
| ◇ | 調査型、参加型などまちづくり教育の形態に応じ教材を作成し、出前講座を創設しよう | ||
| 【事例.愛知県西尾市西尾小学校におけるまちづくりを題材とした総合学習】 | |||
| 提言4.若い人のパワーを呼び込む工夫をしよう | |||
| ① | 若い世代の地域生活者を増やしていこう | ||
| ◇ | 若い世代の「街なか」居住に対する選択的かつ集中的な支援方策に努めよう | ||
| ◇ | コミュニティビジネスの育成を含め生活支援サービスを充実しよう | ||
| ◇ | 既存グループとのタイアップ等により若手商業家・企業家を「街なか」へ誘致しよう | ||
| 右図:さくらアパートメント(名古屋市) | |||
・「クリマ」のネットワークなどを通じ、やる気があって個性的な多数の個店が進出し、面白くて魅力的な空間となっている。 |
|||
| ② | 「若手」に主体的に活動してもらおう | ||
| ◇ | イベント等実施に際し、企画段階からの「若手」の積極的参画を促そう 企画から実施に至るまで「若手」の自主性に委ねたイベント等の実施等 |
||
| にっぽんど真ん中祭り(どまつり)(名古屋市) ・名古屋の学生や市民たちの自発的な発想と行動をベースに1999年より名古屋において始められた祭り。全国各地から地域性豊かなチームが集い、さまざまな郷土色を交えた踊りを披露する。 ・企画、スポンサー集め、行政との調整から参加者募集に至るまで、学生などの「若手」グループが一手に手がけ、2002年に行われた第4回「どまつり」では100万人以上の観客を動員した。 【にっぽんど真ん中まつり】 |
|||
| ◆行政の心がまえ編 |
| 提言5.住民意識・活動の小さな芽を見逃さず応援しよう | |
| ◇ | 定常的な地域生活者等との対話に努め、「小さな芽」を見つけだすよう努めよう |
| ◇ | 広く様々な取り組み(種まき)をするのはもちろんであるが、その中で、まちづくり意識をもった(芽が吹き出た)地区を選択的、重点的に応援しよう |
| ◇ | 様々なまちづくり組織についても、意識、意欲の高い組織を重点的に応援しよう |
| 提言6.持続的な取り組みに努めよう | |||
| ◇ | インフラ整備が完了すれば行政の役割は終わりというわけではなく、一定の基盤が整備された後こそ、地域の真の活性化のためのまちづくりが本格化することを意識しよう | ||
| ◇ | 住民の自立的なまちづくり活動が安定軌道にのるよう根気と「まめさ」をもって住民等に持続的に働きかけよう | ||
| ◇ | 持続的な活動を支える「参加」と「協働」の必要性を強く意識しよう | ||
| 右図:築地地区防潮壁(名古屋市) | |||
・事業完了後もデザイン博、福祉のまちづくりモデル地区指定などの機会をとらえ、行政もタイミング良く働きかけや支援を行ったこともあって、今日では「築地ポートタウン21まちづくりの会」や「夢塾21」を中心に住民主体の自立的なまちづくり活動が展開されている。 ・右図は防潮壁の修景活動。 |
|||
| 提言7.各種の施策をそれぞれがまちづくりの要素としての意識をもって進めよう | |
| ◇ | 「まちづくり」行政は単にインフラ整備にとどまらない総合行政であることを念頭に置いて、各施策の遂行に際し、まちづくりの全体像とその動きを強く意識しよう。 |
| ◇ | 総合的なまちづくり行政が展開できるよう「まちづくり」全体を所掌する組織の設置を視野に入れながら、組織体制のあり方について検討をしよう。 |
|7つの提言TOP|