| |
1. |
無収縮モルタルおよびエポキシ系樹脂は、表16-2,3、シールおよびパテ用エポキシ樹脂については、特仕1編2-15-1
表2-18の試験項目と規格値に適合することを証明する試験成績表を1ロット毎に提出しなければならない。 |
| |
|
|
| |
|
表16-2無収縮モルタル(プレミックスタイプ)の試験項目と規格
| 項目 |
規格値 |
備考 |
| コンシステンシー (流下時間) |
セメント系:8±2秒 |
J14ロート試験 |
| ブリージング |
練り混ぜ2時間後でブリージン グがないものとする。 |
JISA1123 |
| 凝結時間 |
始発:1時間以上(500psi) 終結:10時間以内(4000psi) |
ASTMC403 米国工兵隊規格 |
| 膨張収縮率 |
材令7日で収縮なし |
土木学会「膨張材を用いた充てんモルタルの施工要領」※
|
| 圧縮強度 |
材令3日:25N/㎜2以上 材令28日:44N/㎜2以上
|
JISA1108 供試体径5㎝×高さ10㎝ |
※「土木学会」膨張コンクリート設計施工指針付録書 |
| |
|
|
| |
|
表16-3 定着アンカー注入用エポキシ系樹脂の試験項目と規格
| 試験項目 |
試験方法 |
試験条件 |
単位 |
規格値 |
比重
可使時間
粘度
圧縮降伏強度
曲げ強度
引張強度
圧縮弾性係数
引張せん断強度
衝撃強度
硬度 |
JIS K 7112
温度上昇法
JIS K 6833
JIS K 7208
JIS K 7203
JIS K 7113
JIS K 7208
JIS K 6850
JIS K 7111
JIS K 7215 |
20℃7日間
20℃
〃
20℃7日間
〃
〃
〃
〃
〃
〃 |
-
分
mPa・s
N/㎜2
〃
〃
〃
〃
KJ/㎡
HDD |
1.2±0.2
30以上
5,000以下
50以上
40〃
20〃
(1.0~8.0)103以上
10以上
3.0〃
80〃 |
|
| |
|
|
| |
2. |
塗料の種類、各層毎の標準使用量および標準膜厚は表16-4,5のとおりとする。 |
| |
|
|
| |
|
表16-4 補強鋼板外面の標準塗装仕様(地上部)
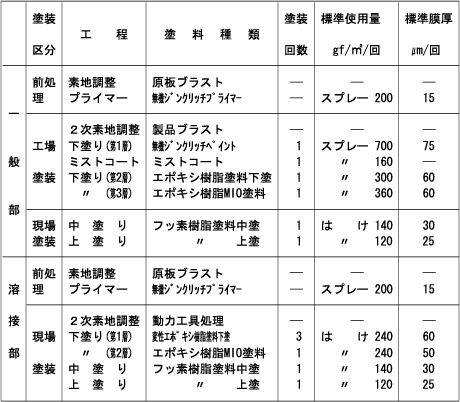
| (上記表はC-3塗装系の場合を示す。) |
| (溶接部とは、現場溶接部両側10㎝幅とする。) |
|
| |
|
|
| |
|
表16-5
無収縮モルタルおよびコンクリートに接する鋼材の標準塗装仕様
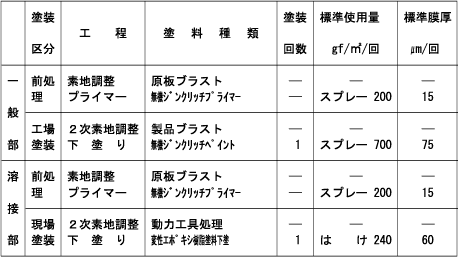
| *補強鋼板の溶接部は、コンクリートに接する外面を指す。 |
|
| |
|
|
| |
3. |
塗料の色調は淡彩色とする。なお、色彩の決定にあたっては、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 |
| |
4. |
根巻きコンクリートおよび中詰コンクリートに使用するシーリング材は、原則としてシリコーン系の2成分形シーリング材を使用し、表16-6の試験項目と規格値に適合することを証明する試験成績表を監督職員に提出しなければならない。 |
| |
|
|
| |
|
表16-6 シーリング材の試験項目と規格
| 項目 |
単位 |
規格 |
摘要 |
| 硬化前 |
押出し性
可使時間
タックフリー |
秒
時間
〃 |
3~8
1~5
1~12 |
JIS A 5758
〃
〃 |
| 硬化後 |
比重
50%引張応力
最大引張応力
伸び
加熱減量 |
―
N/‡
〃
%
〃 |
1.30±0.10
5~20
30~150
600~1200
1~3 |
JIS K 7112(硬化物)
JIS A 5758
〃
〃
〃 |
| 耐久性区分 |
― |
10030(9030) |
JIS A 5758 |
| 硬さ |
― |
10~20 |
JIS K 6301 |
|
| |
|
|
| |
5. |
請負者は、無収縮モルタルの現場管理項目と試験頻度は、表16-7によるものとし、規格値と比較してその性能に問題のないことを確認しなければならない。 |
| |
|
|
| |
|
表16-7無収縮モルタルの現場管理試験
| 項目 |
試験頻度 |
コンシステンシー
(流下時間) |
1日に2回(午前、午後各1回)
圧縮強度試験用供試体作成時 |
| 練り上がり温度 |
| 膨張収縮率 |
無収縮モルタル充填開始前に1回
(3個/回) |
| 圧縮強度 |
1m3に1回または1日に1回
材令3日:3個/回
材令28日:3個/回 |
|
| |
|
|
| |
6. |
請負者は、定着アンカーの注入用エポキシ系樹脂の現場管理は、以下の試験項目、検査頻度により行わなければならない。
| (1) |
施工中、1日1回、樹脂を紙コップに採取して、その硬化状態を観察するものとする。 |
| (2) |
上記にて硬化状態を確認するほかに、施工中1月1回、現場採取した供試体で下記の試験を行い、規格値と比較してその性能に問題のないことを確認するものとする。
試験項目:比重(硬化物)、圧縮降伏強度、曲げ強度、引張強度、圧縮弾性係数
なお、シール用エポキシ系樹脂については、注入用エポキシ系樹脂を注入する時に硬化を確認できるので省略してよい。 |
|