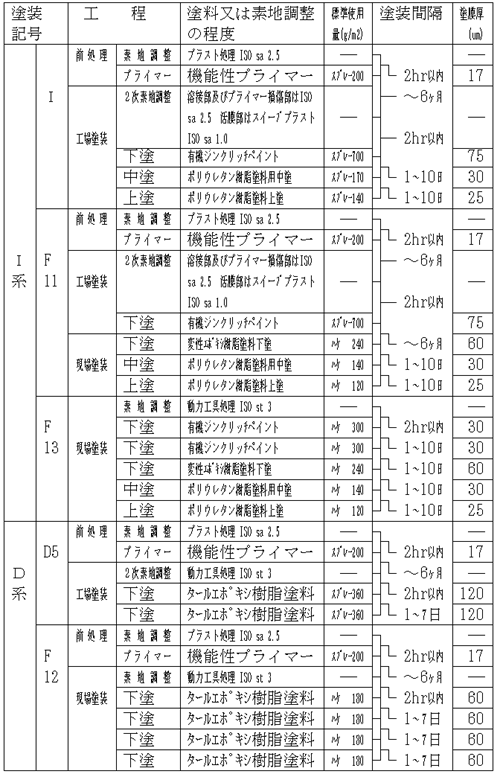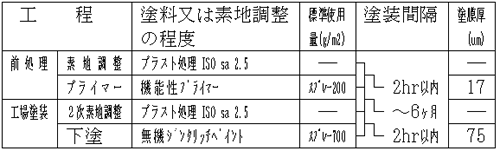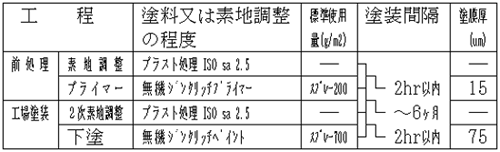| �@ |
�P�D |
���h��̐F�ʂ͎K�F�E�ԎK�F���͎�F�Ƃ���B |
| �@ |
�Q�D |
��ʊO�ʂ𔖖��^�d�h�H�h���Ƃ��邱�Ƃ��v�}���Ɏ����ꂽ�ꍇ�͕\�S�|�P�A�S�|�Q�̓h���d�l�ɂ����̂Ƃ���B |
| �@ |
|
�\�S�|�P
| �h���ӏ� |
�h���L�� |
��
��
�� |
��ʊO�� |
�h�n |
�h |
| �������� |
�c�n |
�c�T |
| ������t�����W��� |
��
��
�p
��
�� |
���̓{���g�ڍ��� |
�h�n |
�e11 |
| �������� |
�c�n |
�e12 |
| ������t�����W��� |
����n�ڕ��y��
���̓{���g���� |
�h�n |
�e13 |
|
| �@ |
�@ |
�\�S�|�Q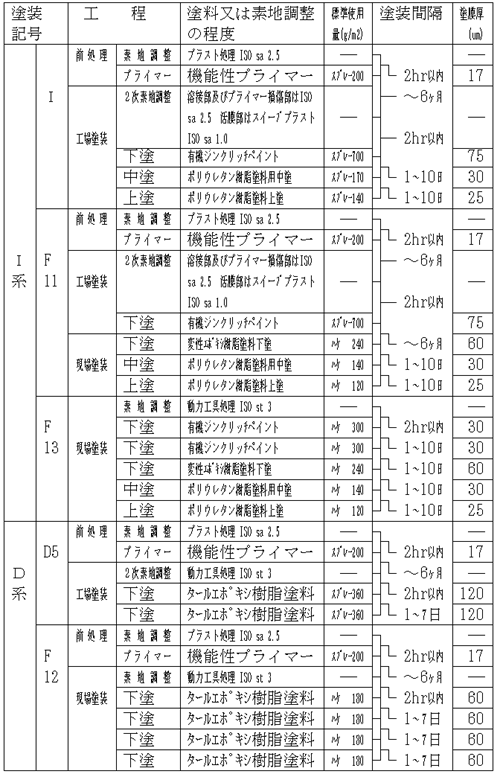 |
| �@ |
�@ |
| �i�P�j |
�O�ʋy�ѓ��ʓ��̕�ނƓY�ڔ̐ڐG�ʂɂ��ẮA�\�S�|�R�̎d�l�Ƃ���B |
�\�S�|�R
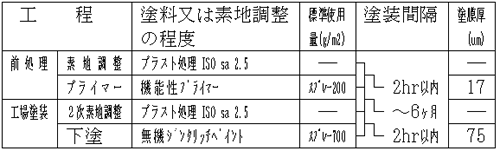
| �i�Q�j |
�O�����̃v���C�}�[�̖����͑��������ɉ����Ȃ����̂Ƃ���B |
| �i�R�j |
�h���Ԋu�̉�����20�x�̏ꍇ�������B�C�����Ⴂ�ꍇ�ɂ͓h���̊�����Ԃd���������Ă��邱�Ƃ��m�F���h��d�˂��s�����̂Ƃ���B
|
| �i�S�j |
�v���C�}�[����Q���f�n�����Ɏ���܂ł̓h���Ԋu���U�����Ƃ������A����͓h���E�{���E�ۊǁE�H����ړ����S�Ă̍H�����A�o����������̉e�����Ȃ��Ǘ����ꂽ�����ōs�����Ƃ�O��Ƃ������̂ŁA���̏����ɓ��Ă͂܂炸�A�v���C�}�[�h�z�ʂɂ��т��������Ă��镔���̓u���X�g�����̑f�n�������s�����̂Ƃ���B |
| �i�T�j |
�\�S�|�S�Ɏ��������͓h�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
| �@ |
�\�S�|�S
| �敪 |
�Ώە��� |
| �h���������Ă͂Ȃ�Ȃ����� |
�@�x���Ȃǂ̋@�B�d�グ�� |
�@�\���v���C�}�[���c����
�Ă��ǂ����� |
�@�|�ނƃR���N���[�g�̐ڐG�ʁi�����̏�t�����W��ʁA���r�̃x�[�X�v���[�g���A�L�k���u���j |
|
|
| �@ |
�R�D |
��ʊO�ʂ��b�h���n�ɂ����ꍇ�̓h���d�l�́A�u�����Q�N�U����)���{���H����|���H���h���֗��v�i�ȉ��u�h���֗��v�Ƃ����B�j�̕\�S�|�T�Ɏ����h���n�Ƃ���B |
| �@ |
�@ |
�\�S�|�T
| �h���ӏ� |
�h���n |
��
��
�� |
��ʊO�� |
�b�Q |
| �������� |
�c�R |
| ������t�����W��� |
��
��
�p
��
�� |
���̓{���g�ڍ��� |
�e�W |
| �������� |
�e�T |
| ������t�����W��� |
|
| �@ |
�@ |
| �i�P�j |
�O�ʋy�ѓ��ʓ��̕�ނƓY�ڔ̐ڐG�ʂɂ��ẮA�\�S�|�U�̎d�l�Ƃ���B |
�\�S�|�U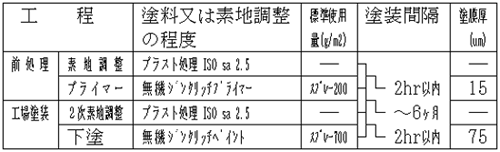
| �i�Q�j |
�v���C�}�[����Q���f�n�����Ɏ���܂ł̓h���Ԋu���U�����Ƃ������A����͓h
���E�{���E�ۊǁE�H����ړ����S�Ă̍H�����A�o����������̉e�����Ȃ� �Ǘ����ꂽ�����ōs�����Ƃ�O��Ƃ������̂ŁA���̏����ɓ��Ă͂܂炸�A�v���C�}�[�h�z�ʂɂ��т��������Ă��镔���̓u���X�g�����̑f�n�������s�����̂Ƃ���B |
| �i�R�j |
�\�S�|�V�Ɏ��������͓h�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
| �@ |
�\�S�|�V
| �敪 |
�Ώە��� |
| �h���������Ă͂Ȃ�Ȃ����� |
�@�x���Ȃǂ̋@�B�d�グ�� |
|
|
| �@ |
�S�D |
�f�n����
| �i�P�j |
�\�ʂ̑e����70��mRz�ȉ��Ƃ���B |
| �i�Q�j |
�f�n�����Ƃ��čs���u���X�g�����ɗp�����������ނ�JIS
Z 0311-1996�A���������ނ�JIS Z 0312-1996�u�u���X�g�����p���������ށv�ɋK�肷�錤��ނ̒�����I�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �i�R�j |
�o�������t�����Ă����艖���̕t���ʂ�100mg/m2�ȏ�̏ꍇ�ɂ́A����h�����s�����O�ɑf�n�����Ƃ��Đ������ɂ��\���Ȑ��|���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ȃ��A�����t���ʂ̑���́uJHS 408-1997�|���̕t�������ʑ�����@�v�ɂ����̂Ƃ���B |
|
| �@ |
�T�D |
�u���X�g���
| �i�P�j |
�u���X�g��Ƃ͌����Ƃ��Ď����ōs���A�u���X�g�J�n���O����h�������܂ł̊ԂɉJ��I���ɂ���ău���X�g�ʂɐ������t�����Ȃ��������ō�Ƃ��s�����̂Ƃ���B |
| �i�Q�j |
�u���X�g��Ƃɂ������ẮA���p�̏��K�x�ƕ\�ʑe������l�Ȍ���ނ̗��x�A���˂̏����i�m�Y�����a�E��C���E���ˑ��x�E���ԓ��j���������ł��炩���ߊm�F�����̏����ōs�����ƂƂ���B |
| �i�R�j |
�u���X�g�ʂ̓u���X�g�����O�ɖ����␅���A�X�p�b�^��X���O���u���X�g�ŏ����o���Ȃ��L�Q�t���������炩���ߎ�菜���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
| �i�S�j |
�u���X�g������A�u���X�g�ʂ͏\���ɐ��|���u���X�g�ɂ��_�X�g�⌤��ނ����S�ɏ�������B |
| �i�T�j |
�u���X�g�ʂ́A�u���X�g�{�H��Q���Ԉȓ��ɓh������B
�������A���x�E���x���Ǘ�����Ă��鉮���̏ꍇ�͂S���Ԉȓ��Ƃ���B |
|
| �@ |
�U�D |
�h�����
| �i�P�j |
�f�n�����y�ѓh����Ƃ��s���h����Ǝ҂́A�|���̓h���H���ɏ\���Ȍo����L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ȃ��A�h����Ƃɂ͍|�\�����h���̎��i��L����h���Ǘ��҂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �i�Q�j |
�g�p����h���͓h�����@�A�h�z�ʋy�ѓh�����̋C�����ɂ���ēK���ȔS�x�ɒ�������B���̏ꍇ�A��ނ���ߍ܁i�V���i�[�j���g�p����ꍇ�ɂ́A��ߍ܂̓Y���ʂ͍ŏ����Ƃ����m�ɔ��ʂ��ēY������ƂƂ��ɁA��ߍ܂͓h���Ɠ���̐�����Ђ̂��̂��g�p����B
�������A���n�܌`�h���ɂ͊�ߍ܂�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
|
| �@ |
�V�D |
�h����Ƌ֎~�̏���
| �i�P�j |
�h�����̍�Ɗ��A�h���ʋy�ѓh�����A�u�h���֗��v5-4�C�ۏ����̕\5-6�Ɏ�����Ԃ̏ꍇ�ɂ͓h�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�h���d�������܂ށj
�Ȃ��A�@�\���v���C�}�[�ɂ��ẮA���x�O���ȉ��E���x�T�O���ȉ��̏ꍇ�́A�h�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B |
| �i�Q�j |
���O�h���ō~�J�E�~��y�ы������̂���ꍇ�A���邢�͂��̋��ꂪ����ꍇ�B |
| �i�R�j |
�h���ʂ����I���ŔG��Ă���ꍇ�y�ш����������̏�Ԃ����������Ɨ\�z�����ꍇ�B |
| �i�S�j |
�h���ʂ̕\�ʉ��x���u�h���֗��v�T�|�S�C�ۏ����̕\�T�|�U�ɋK�肷�鉷�x�ȉ����邢��50�x�ȏ�̏ꍇ�B |
| �i�T�j |
�K��̑f�n�������s���Ă��Ȃ��ꍇ�B |
| �i�U�j |
�K��̓h��d�ˊԊu���Ƃ��Ă��Ȃ��ꍇ�B |
| �i�V�j |
�h���ʂɁA�D�E�����E�S�~�E�ق��蓙���t�����Ă���ꍇ�y�щ����̕t���ʂ�100mg/m2�ȏ�̏ꍇ�B
|
| �i�W�j |
�g�p�h�����K�肳�ꂽ�g���Ԃ��Ă���ꍇ�B |
|
| �@ |
�W�D |
�h���̕i��
�h���̕i���͌����Ƃ��āA�u�h���֗��v�̎����U�|���H���h���p�h���W���ɂ����̂Ƃ���B |
| �@ |
�X�D |
�n�ڕ��̓h��
�n�ڕ��͌����Ƃ��āA�f�n�����i�d���H����j���s������A���_�n�t�i�T�`10�e�ʁ��j�Œ��a���������������Ă���h�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������̏ꍇ�͂��̌���ł͂Ȃ��B
| �i�P�j |
���i�u���X�g�̏ꍇ�y�ь��u���X�g�ŗn�ڃr�[�g���u���X�g���ēh������ꍇ�B |
| �i�Q�j |
�n�ڌ�A���O�ɕ��u���ĐԎK���������Ă���ꍇ�B |
| �i�R�j |
�^�[���G�|�L�V�����h����h��ꍇ�B |
| �i�S�j |
�ᐅ�f�n�n�ږ_�ɂ���n�ڈȊO�̗n�ڕ��B |
|
| �@ |
10�D |
�{�H���ɓK�p����ʐF���v�}���ɂ����̂Ƃ���B
|