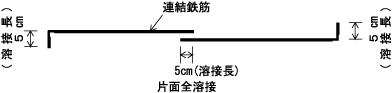| |
1. |
背面板(受音側の板)の材質は、JISG3302「亜鉛鉄板」に規定する亜鉛鉄板(SGH400又はSGC400Z27)又はこれと同等品以上とする。 |
| |
2. |
吸音板内部の吸音材料は、JISA6303「ロックウール吸音材」に準ずるもので、かさ比重0,15厚さ50㎜のもの、あるいはJISA6306「グラスウール吸音材」に規定するグラスウール吸音ボードで2号32K(かさ比重0.032)厚さ50㎜のもの又はこれと同等品以上とする。
なお、耐久性の向上のため吸音材は、PVF(ポリフッ化ビニール樹脂フィルム)厚さ21μm又はこれと同等品以上の強度・耐候性のあるもので、かつ吸音性を劣化させないフィルムで被膜しなければならない。 |
| |
3. |
吸音板の寸法の精度は表1-5のとおりとし、支柱間に容易に収まり、また脱落しない精度を有するものとする。 |
| |
|
|
| |
|
表1-5 吸音板の寸法の精度
| 支柱間用 |
長さ |
高さ |
厚さ |
| 4m |
±10㎜以内 |
±5㎜以内 |
±5㎜以内 |
|
| |
|
|
| |
4. |
吸音板の固定金具(バネ)については、JISG4801「バネ鋼」の(SUP6)又は、これと同等品以上のものを使用することとする。 |
| |
5. |
吸音板の固定金具は、下記の性能を満足するものとする。
| (1) |
支柱及び吸音板の寸法許容誤差を考慮した空隙に対して、固定金具として有効に働くこと |
| (2) |
空隙が12㎜のとき、バネ反力が150㎏以上であること |
| (3) |
最小高さの保証値は、8.5㎜以下とすること |
| (4) |
最小高さにおいて450㎏以上の荷重に耐え、かつ割れを生じないこと |
|
| |
6. |
遮音板の音響性能及び試験方法は下記によらなければならない。
| (1) |
透過損失
400Hzに対して25dB以上
1000Hzに対して30dB以上
試験方法はJISA1416「実験室における音響透過損失測定方法」によらなければならない。 |
| (2) |
吸音率400Hzに対して70%以上
1000Hzに対して80%以上
試験方法はJISA1409「残響室吸音率の測定方法」によらなければならない。 |
|