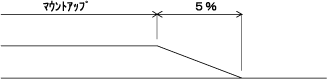| |
1. |
請負者は、粒状路盤材について、規格品の搬入可能量を監督職員に報告しなければならない。 |
| |
2. |
請負者は、「共仕」第1編3ー6ー2アスファルト舗装の材料によるアスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は認定書の写しを事前に提出することによって、材料の試料及び試験結果、品質証明書に変えるものとする。 |
| |
3. |
セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材の最大粒径は、40㎜以下とし標準粒度範囲は表3-4とする。 |
| |
|
|
| |
|
表3-4 骨材の標準粒度範囲
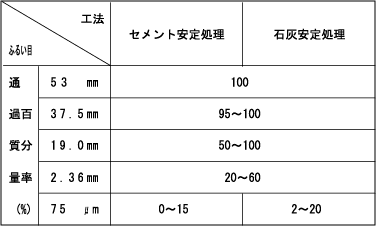 |
| |
|
|
| |
4. |
セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材は、表3-5に示す品質規格に合格したもので多量の軟石、シルト、粘土塊や有機物、その他セメントの水和に有害な物質を含んでいてはならない。 |
| |
|
|
| |
|
表3-5骨材の品質規格
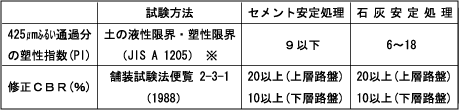 |
| |
|
|
| |
5. |
「共仕」第1編3-6-2アスファルト舗装の材料の5項における小規模工事とは、路盤材及び骨材の使用量が100m3以下をいう。 |
| |
6. |
「共仕」第1編3-6-2アスファルト舗装の材料第6項における小規模工事とは、合材量が100t以下をいう。 |
| |
7. |
加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径は40㎜以下とし、標準粒度範囲は表3-6とする。 |
| |
|
|
| |
|
表3-6骨材の標準粒度範囲
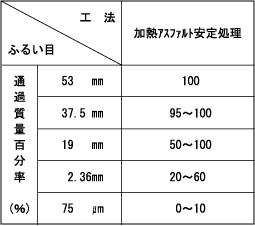 |
| |
|
|
| |
8. |
安定処理に使用する骨材は、表3-7に示す品質規格に合格したもので著しく吸水性の大きい骨材、多量の軟石、シルト、粘土塊や有害な物質を含んでいてはならない。 |
| |
|
|
| |
|
表3-7骨材の品質規格
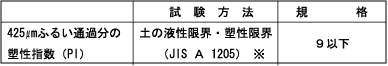
|
| |
|
|
| |
9. |
加熱アスファルト安定処理路盤材の基準アスファルト量は3.5~4.5%とする。 |
| |
10. |
示方アスファルト量と「共仕」第1編3-6-5アスファルト舗装工の5項の(5)による最終的な配合(現場配合)から決定した基準アスファルト量が表3-8の範囲を超える場合は、アスファルト量について変更するものとする。この場合、使用する骨材の比重が特に大きい(若しくは小さい)ためにアスファルト混合率が見掛け上変わった場合の取扱いは、容積に換算して計算するものとする。ただし、仕上りの密度が変わったための契約変更は行わないものとする。 |
| |
|
|
| |
|
表3-8混合物の種類とアスファルト量
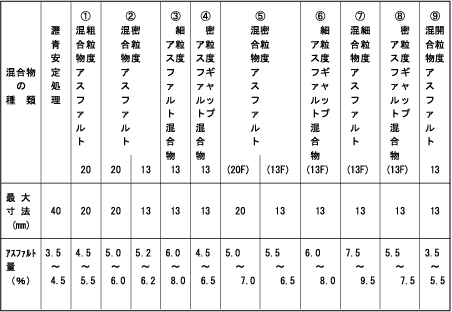 |