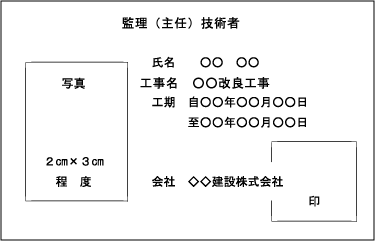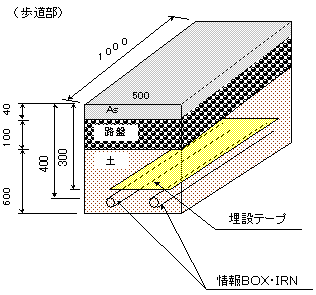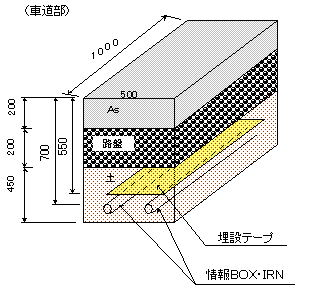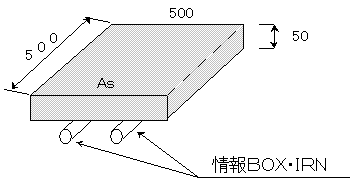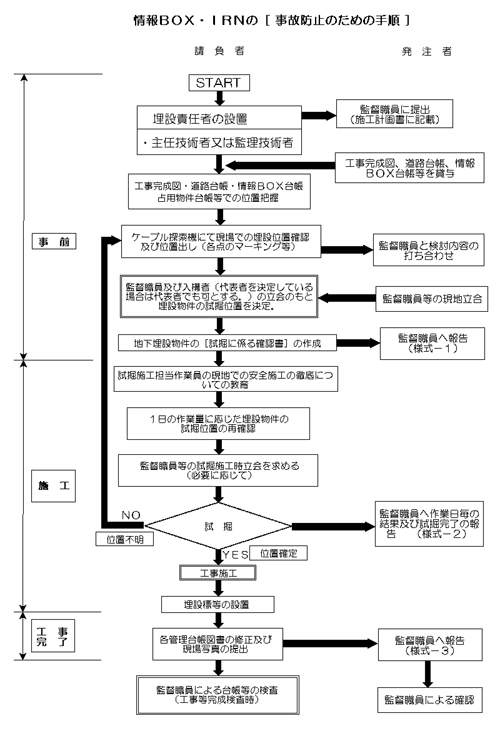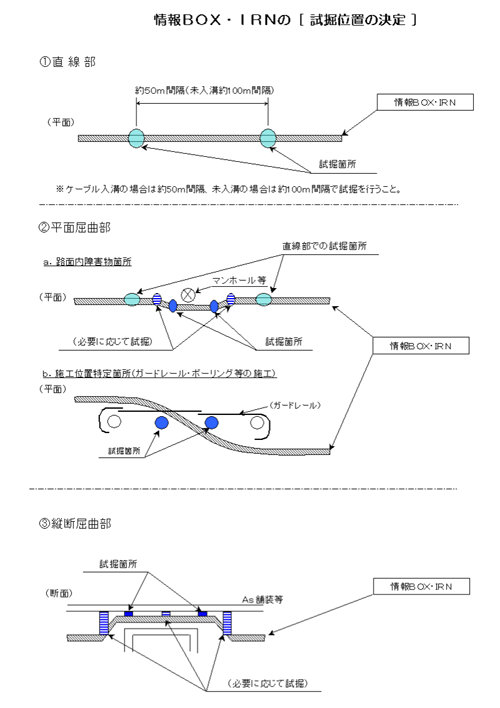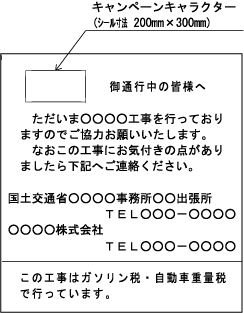| |
1. |
情報BOX等の埋設管路の事故防止
| (1) |
総則
本項目は、中部地方整備局が管理する国道に埋設及び添架されている情報BOX・IRN(以下「情報BOX」という)施設の周辺で行われる工事による事故を未然に防止し、これら施設の安全確保及び各種管理台帳の精度の一層の充実を図るために、統一的な手順・方法・確認等を取りまとめたものである。
なお、本工事の対象工事(以下「工事」という)は下記のとおりとする。
| ① |
情報BOXが埋設されている区間において、掘削及び付属物の建込みを伴う工事。(路面切削工・舗装打替工・管路推進工・舗装切断等を含む。) |
| ② |
橋梁等に添架されている情報BOXの移設及び撤去を伴う工事。(橋梁補修工・トンネル補修工・橋梁補強工・塗装工等含む) |
|
| (2) |
事故防止に関する施工手順
| 1) |
請負者は、図1−1に示す情報BOXの「事故防止のための手順」に従い、必要な措置を講ずるものとし、工事着手に先立ち当該措置の技術上の管理を担当する埋設物責任者(主任技術者又は監理技術者とする)を選任の上、施工計画書に記載し、監督職員に提出しなければならない。この者を変更した場合も同様とする。 |
| 2) |
発注者は埋設物責任者に、工事着手前の準備にあたり、工事完成図・道路台帳・情報BOX台帳等必要な資料を貸与するものとする。 |
| 3) |
請負者は、上記2)の各種台帳等での位置把握を行った後、ケーブル探索器を使用し、情報BOXの位置確認及び現場位置出し(各点のマーキング等)を行うとともに、埋設物責任者はその結果を書面に取りまとめ、監督職員と協議するものとする。
なお、ケーブル探索器については、必要に応じ発注者から貸与するものとする。 |
| 4) |
請負者は、上記3)の結果に基づき、監督職員及び入溝者(代表者が決定している場合は代表者でも可とする。)の立会のもと埋設物件の試掘位置を、(3)1)項に基づき決定するとともに、情報BOXの[試掘に係る確認書](以下「確認書」という)を取りまとめ、様式−1により、監督職員に報告しなければならない。 |
| 5) |
埋設物責任者は試掘前に試掘施工担当作業員を現地で立会させ埋設物件及び試掘位置の再確認を行うとともに、(3)2)項により安全施工の徹底について教育しなければならない。
また、試掘の結果埋設位置が不明の場合は再度、埋設位置の再確認を行い試掘を行わなければならない。
また、試掘に当たっては必要に応じ、監督職員等の立会を求めることができる。
なお、作業日毎の試掘結果を監督職員に電話等で報告するとともに、試掘完了後は情報BOXの確認書を取りまとめ、様式−2により、監督職員に報告しなければならない。 |
| 6) |
埋設物責任者は工事施工完了後、情報BOXの埋設位置の変更があった場合は、埋設標等の設置を行うとともに各管理台帳図書の修正及び現場写真を添え、情報BOXの確認書を取りまとめ、様式−3により、監督職員へ報告しなければならない。 |
| 7) |
監督職員は、上記6)の報告を受けた場合はその内容について確認をするものとする。 |
| 8) |
工事の検査職員は、情報BOXの確認書(様式−1〜3)に基づき、管理台帳図書の修正がある場合は検査するものとする。 |
| 9) |
請負者は、情報BOXの配管が露出管の場合で、工事により移設・撤去等の必要が生じた場合も、上記事故防止に関する施工手順に従い施工しなければならない。 |
|
| (3) |
試掘位置の決定及び試掘方法
| 1) |
請負者は、試掘位置の決定を下記のとおり行わなければならない。
なお、下記によりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。
| ① |
直線部
道路の直線部において、通信ケーブル等が入線されている場合は図1−2①に示す様に約50m以下の間隔で、入線されてない場合は約100m以下の間隔で試掘位置を決定するものとする。 |
| ② |
平面屈曲部
| a. |
路面内障害物箇所
マンホール等の設置により情報BOXの配管を曲げて布設等している場合は、図−2②aに示す様に変化点について試掘位置を決定するものとする。 |
| b. |
施工位置特定箇所
ガードレール等、施工箇所が特定できるものについては、図1−2②bに示す様に施工箇所での試掘位置を決定するものとする。
また、ガードレールと平行して情報BOXの管路が見込まれる場合は、直線部に準じて試掘位置を決定するものとする。
なお、埋設物責任者は、情報BOX施設と工事施工箇所の離隔が十分確保されることが明らかな場合で上記a,bによりがたい場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 |
|
| ③ |
縦断屈曲部
横断構造物等の箇所で、情報BOXの配管が上越と特定できる箇所については図1−2③に示す様に横断構造物の天端の起・終点について試掘位置を決定するものとする。
また、橋梁添加部手前や露出立ち上がり部付近において、縦断の屈曲が想定される箇所についても必要に応じ試掘位置を決定。 |
|
| 2) |
請負者は、試掘方法及び露出管通信ケーブルの確認方法を、下記のとおり行わなければならない。
| ① |
試掘にあたっては、情報BOXの損傷を避けるため、重機、動力機械の使用は確実に影響しない範囲のみとする。また、情報BOXの位置が不確実と思われる箇所及び情報BOXに50Cm程度に近接したと想定又は判断される箇所からは、人力による施工機具または手堀にて慎重に作業を行わなければならない。 |
| ② |
露出管において、施工上やむを得ず管路切断等を行う必要が生じた場合は、露出管の通信ケーブルの入線管路が既存資料等により特定できた場合でも、必ずケーブル探索器等により通信ケーブルの入線管路を再確認した上で施工しなければならない。
なお、切断する場合は、管の肉厚等が薄いことから切断方法は、鉄鋸などによる手びき作業を原則とする。 |
|
|
| (4) |
情報BOXの確認書の提出
| 1) |
埋設物責任者は、工事の事前・施工中・施工後において情報BOXの確認書(様式−1〜3)にて、工事の施工に関する所要の事項を記入し、監督職員に報告しなければならない。 |
| 2) |
埋設物責任者は施工後において、各管理台帳図書の修正が無い場合でも様式−3にて監督職員に報告しなければならない。 |
|
| (5) |
試掘の形状及び試掘費用
| 1) |
試掘の形状は、下記を標準とする。
|
| 2) |
試掘費用
試掘費用は上記1)の形状及び試掘箇所を対象として計上するものとし、試掘箇所は精算変更の対象とする。 |
|
|
| |
|
図1−1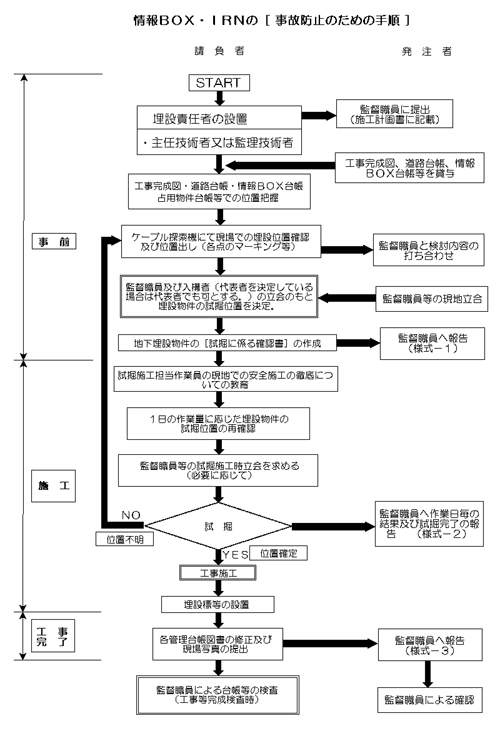 |
| |
|
図1−2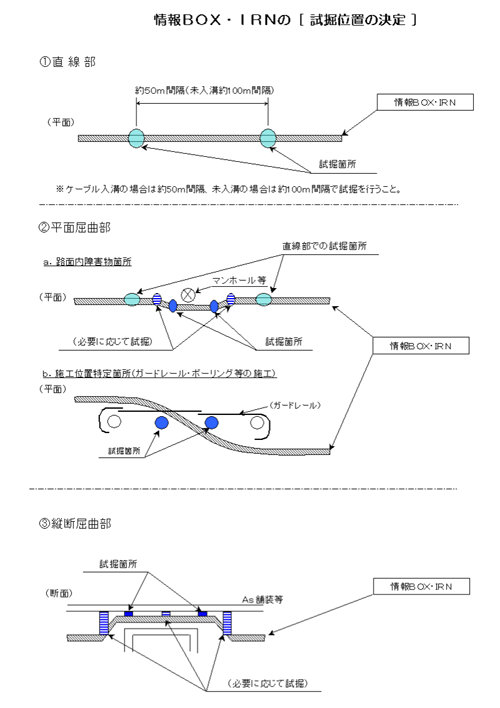 |
| |
2. |
請負者は、「共仕」第1編1-1-32工事中の安全確保の6項のほか、風に対しても注意を払わなければならない。 |
| |
3. |
工事現場のイメージアップは、地域との積極的なコミュニケーションを図り、現場で働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とする。よって、請負者は、施工に際しこの主旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施しなければならない。
また、工事現場のイメージアップの内容について、「共仕」第1編第1章1-1-6施工計画書第1項(12)現場作業環境の整備に記載しなければならない。 |
| |
4. |
請負者は、設計図書で安全提案モデル工事であることを明示した場合は、下記により実施しなければならない。
| (1) |
請負者は、作業員を主体とした安全検討会を組織するとともに、その運営方法については自主的に決定させるものとし、運営計画書を作成し、監督職員に提出する施工計画書に添付しなければならない。 |
| (2) |
請負者は、安全検討会の提言は原則として受け入れるものとする。ただし、契約書・仕様書に定められた範囲以外の提言については監督職員に報告し、甲乙協議によって実施するものとする。 |
| (3) |
請負者は、作業員に対して自主的に実施するよう、指導しなければならない。 |
| (4) |
請負者は、安全検討会の提言および実施した状況の資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 |
|
| |
5. |
請負者は、地震防災対策強化地域における工事にあっては、東海地震の判定会招集連絡報が発せられた場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
また、地震防災強化地域以外における工事にあっても、東海地震の判定会招集連絡報が発せられた場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講じなければならない。
| (1) |
上記保全処置については、共仕第1編1-1-6施工計画書の1項の(9)緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。 |
| (2) |
上記事実が発生した場合は、共仕第1編1-1-48(臨機の措置)の規定によらなければならない。 |
|
| |
6. |
請負者は、足場を設置する場合、安全ネット及びシートを設け、作業床からの転落防止と落下物による事故防止に努めなければならない。
なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が75cmを越える場合は、その間に単管パイプ等により中棧を設け、その間隔は50cm以下としなければならない。
また、安全ネット・手すりについて、工事写真により実施状況を記録し、完成検査時に提出しなければならない。 |
| |
7. |
請負者は、工事施工中における作業員の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等安全施設を設けなければならない。 |
| |
8. |
請負者は、工事中における作業員の労働災害防止を図るため昼休みを除いた午前・午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画書に具体的時間を記載しなければならない。
また、作業開始前に作業員に対し安全に関する指導を行わなければならない。
なお、上記の休憩時間については、実施記録を作成し、監督職員の要請があった場合はすみやかに提示するとともに検査時に提出しなければならない。 |
| |
9. |
請負者は「共仕」第1編1-1-32工事中の安全確保の8項に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。
| 1) |
安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。 |
|
| |
10. |
請負者は「共仕」第1編1-1-32工事中の安全確保の10項に基づいて下記に示す項目の具体的な安全・訓練の計画を作成しなければならない。
| (1) |
工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画 |
| (2) |
全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
| 1) |
月1回の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目 |
| 2) |
資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法 |
| 3) |
現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法 |
| 4) |
KY及び新規入場者教育の方法 |
| 5) |
場内整理整頓の実施 |
|
|