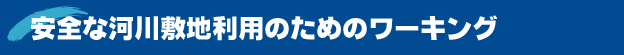
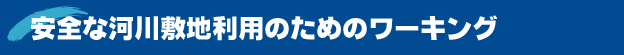 |
普段、川の穏やかな姿に接しているだけでは、急な川の増水による危険を知るのは困難です。河川利用にあたっては、一旦増水すると川がどのような状態になるか、川の状態から何を読み取ることができるかなど、基礎知識を身につけるようにしましょう。
河川は自由使用が原則であり、利用にあたって身の安全を確保することは自己の責任に委ねられます。基礎知識を身につけ、基本的なルールを守るという心構えの上にはじめて、安全で楽しい河川利用が成り立つのです。
テレビ、ラジオ、新聞、電話サービスなどが一般的でしたが、パソコンによるインターネットや携帯電話のサイトにも充実した情報がたくさんあります。日本気象協会や専門会社のサイト以外にも、新聞社や放送局のサイトには地域の気象情報が掲載されています。中部電力のパソコンサイトでは雷の発生状況をリアルタイムで見ることもできます。
http://www.chuden.co.jp/kisyo/
出かける川がどんな川なのか?上流にダムがあるのかないのか、なども事前に調べておきましょう。中部地方の河川については、国土交通省中部地方整備局河川部のサイトで調べることができます。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/
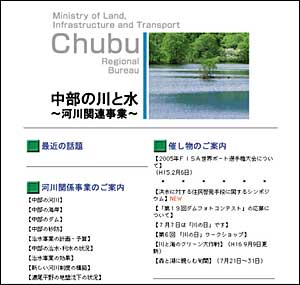
日本の渓流は急峻な谷が多く、ひとたび雨が降ると川が一気に増水し鉄砲水になるケースが少なくありません。
「雨が降ったらすぐに川から離れる」が鉄則です。

川の上流にみられる発電用、農業用水用などの利水ダムは、水の利用に合わせ、洪水とは関係なく放流することがあります。もちろん、洪水により水位が上昇するとゲートからの放流も行われることになります。
水が放流されれば天候等に関係なく川が増水して危険になる場合があります。
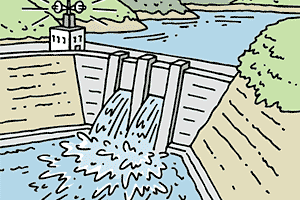
天候が悪化する前には、川や空や気温などにも様々な予兆が現れます。
これらの予兆から危険を察知して避難等に役立てることも重要です。
川の水が濁る、上流からゴミが流れてくるときには、上流で水位が上昇していることが考えられます。川の水位が徐々に増しているときなどはさらに危険なサインとみるべきです。川がそのような状態になったときは迷わず避難するようにしましょう。
また、大雨注意報は時間雨量が20mmになると予想されるときなどに発表されますが、わずかな雨でも上流部の雨が川に集まって思わぬ水位上昇を引き起こすことがあります。注意報が発令されたら非難する、が鉄則です。
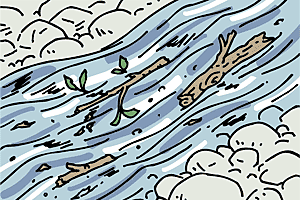
天気のよい日中は、上昇気流により谷から山へと吹き上がる「谷風」が普通です。
山から吹き下る「山風」が吹いてきたら、やがて天気が崩れ、雨が降るサインだと考えてください。

山の頂上を覆うような笠雲があるときは、上空に湿った空気がある証拠です。
湿った気流も天気が崩れるサインです。用心するようにしましょう。
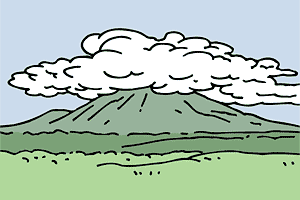
うろこ雲が空を覆うようだと天気は急に悪くなると言われます。また、雲の塊がやや大きいひつじ雲も同じように天気が急速に悪化するサインです。キャンプの準備中にこんな雲を見かけたら、注意しましょう。
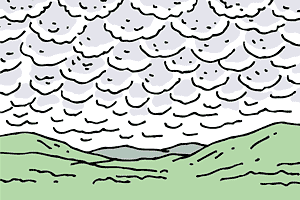
高気圧に覆われているときは空気が乾燥して音も拡散してしまいますが、空気が湿って低い雲におおわれると音の反射が良くなり遠くの音も聞こえやすくなると言われます。昔からの言い伝えですが、参考にはなると考えられます。
川の上流など山の朝は、夏でも外気が冷え込んでいたりテントに夜露が落ちていたりするとその日は晴れになります。反対に妙に暖かい朝は天気が下り坂になります。寒暖の差がなく、空気中に水蒸気が多いためで、雨になることが多いといわれます。
※出典:水辺の安全ハンドブック「川を知る。川を楽しむ。」