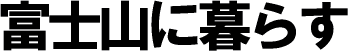| ふじあざみ 第44号(3) | ||||||
|
|
||||||
|
||||||
 |
||||||
|
||||||
 |
||||||
富士山麓はその地形や気候などにより酪農や農業にも恩恵を与えてきました。今回は富士山を身近に仰ぐ富士宮市北山で約100年、3代にわたり農業に従事する遠藤澄男さんにお話を伺いました。 |
||||||
| ■試行錯誤の末にたどりついた有機農法 農業という仕事の過酷さを物語る褐色に日焼けした肌と笑顔が印象的な遠藤さん。現在の農法を確立するまでに、さまざまな紆余曲折があったと言います。遠藤さんが農業を引き継いだ当時は農薬を使った農法が主流で、なかば当然のように農薬を使っていたそうです。「でも、しばらくして農薬を使う農法に疑問を感じるようになったんです。農薬を使うと、思うように育たないことも多く、第一おいしくない。農薬は見た目がきれいに見えるように、虫が食べないようにするためだけのものです。虫も食べない野菜を人間が食べるなんて、おかしいじゃないですか。」消費者に対する誠意が、遠藤さんを有機農法に導いたのでしょう。「有機農法に変えてから、作物の味も格段に変わりました。とうもろこしなども甘味が増し、本場とも言える北海道からも注文があります。」消費者のことを第一に考えた結果が成果としてあらわれているようです。 |
||||||
|
||||||
| ■有機農法ゆえの苦労 有機農法は農薬や化学肥料の使用を最小限におさえた農法です。消費者が安心・安全に食べられることはもちろん、本来の作物の味を引き出します。それだけに虫などが付かないように、日々の作業には手間がかかります。「肥料は畜産動物の糞尿を処理した堆肥を使っています。堆肥も牛、豚、鶏など様々ありますが、それぞれの堆肥によって作物の育成や味が微妙に異なります。」野菜作りの繊細さを物語るお話です。さらに「堆肥についても細心の注意をはらっています。抗生物質や化学物質がいっぱいの餌を与えられた畜産動物の糞尿ではダメなんです。動物の餌によっても、作物の育ち方が違ってきます。農業とは、本来それくらいデリケートなものなんですよ。」と語ります。遠藤さんが作物にかける愛情の深さがうかがえます。 ■地域の農業発展に富士山の恩恵 「私の畑では、とうもろこし、キャベツ、里芋、茄子、生姜、米など、様々な作物を栽培しています。駿河湾から富士山に至る地域は、その標高差により、日本全国の環境が凝縮されているようなものなんです。ですから、露地栽培の野菜なら、ほとんどの作物が栽培できます。なんといっても野菜にとっては露地栽培がいちばんですからね。あたたかい地域の環境を無理矢理作ってしまう施設野菜も否定はしませんが、やはり味はいまひとつですね。」富士山の恩恵と自然の環境を最大限に活かし、丹誠込めた作物は、地元の産地直売の会や道の駅「朝霧高原」などで直売されています。今年は冷夏や台風で野菜が深刻な打撃を受けたと言われますが、遠藤さんの場合はどうだったのでしょうか。「もちろん大変な打撃でした。出荷量は通常の4分の1程度じゃないでしょうか。市場では野菜の価格が高騰していますが、私たち生産農家が持ち寄る直売店は安いですよ!(笑)しかも品質はかわりません。いつもどおり新鮮でおいしくて、安心・安全な野菜たちです。ぜひご利用ください。」生産量が少ないからと言って、むやみに価格を引き上げるわけにはいかないと、ここでも消費者第一の意識が優先してしまう遠藤さんのコメントでした。 ■これからも今のままの富士山と共に 「子供の頃は富士山は空気みたいなもので、あまり意識したことはありませんでした。それでも富士山の美しさにはハッとする瞬間があります。特に絶好のタイミングで見る紅葉の時期がいちばん好きですね。」さらに、奥様は中国でお生まれになり、小学6年の時に日本に引き上げてこられたそうで、そのとき初めて見た富士山には圧倒され、声も出なかったと、興奮して語っていただきました。「気象による土砂災害や、地震、噴火などの災害から私たちを守ってくれるための事業は別ですが、それ以外はなるべく人間が手をかけないで、自然なままの富士山が保たれるのがいちばんいいんでしょうね。私たちの野菜も自然、富士山も自然、人間はそれにちょっと手を貸してあげるだけでいんじゃないでしょうか。」 |
||||||
|
||||||